自治医科大学医学部同窓会報「研究・論文こぼれ話」その48 同窓会報第103号(2023年1月15日発行)
「そのセンスで常識を作り変える」
自治医大循環器内科・成人先天性心疾患センター 甲谷 友幸(埼玉20期)
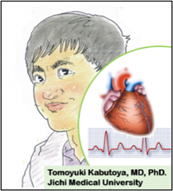
臨床研究で長らくお世話になっている星出先生からバトンをいただきました。本稿では、義務年限中に1本も書いてなかった私が上から目線で、まだ原著論文を書いたことがない迷える義務年限中の先生へのアドバイスとして書いてみます。
私は卒後2年間さいたま赤十字病院で初期研修、3~5年目は僻地勤務を行っていて大学病院とは縁がなく、面倒な大学の書類書きやカンファレンスなどと無縁な生活を楽しく送っていました。恩師の日赤循環器内科(当時)の淺川喜裕先生(埼玉8期)に、『これからは不整脈の時代だから不整脈の勉強をしてこい』と言われ、渋々(?)6年目に自治医大の循環器内科で後期研修を行いました。不整脈を三橋武司先生(茨城7期)に教わり自分では不整脈のスキルアップができてそれなりに満足していたのですが、当時講師であった現循環器内科教授の苅尾七臣先生(兵庫10期)から『時間があるんやったら研究やったらどうや』といわれ(そんな暇そうにしている感じだったのかな..)、残りの義務年限の中で多施設合同研究のJMS-1研究、JHOP研究に参画し患者さんの登録を行いました。たしかに時間は余っていたので半強制的に研究を行いながら、週1回研究日に自治医大で三橋先生にアブレーションを教えてもらう日々を続けていきました。そんな生活をしているうちに不整脈の臨床以外にも研究も継続したくなり、日赤も不整脈チームが整ってきたこともあり、義務年限明けは日赤ではなくて大学に入局することにしました。それでも結局私の最初の原著論文が出版されたのは入局2年目、医師11年目のことでした。大学病院勤務でいわゆるチューベン(病棟主治医)をやりながら論文を書くのはなかなか大変なのです。これを読んでくれている卒業生には、義務年限中になんでもいいので1本論文を書くことを強く勧めます。論文は最初から1人では書けないので、教えてくれる先生を見つけることも大事なことです。CRSTがどうにかしてくれる(と思います)。
そもそも自治医大は臨床医の育成→へき地医療の実践が目的なんじゃないの、論文って必要なの?って思う方も多いでしょう。義務年限中の卒業生に知っていてほしいことは、医師になる直前の卒試・国試で得た知識はその時は正しいですが、5年10年で医療現場の常識は変わってくる、ということです。その変わってくることを知らないと患者さんにその時点で最も適切な治療はできないし、ガイドラインも5年もたたずに変わることがしばしばあります。変わってくることの多くは新しい研究に基づく新しい知見から生じることであり、臨床医であれば日常診療をしながら、日々の疑問にアンテナを張って自分で新しい知見を生み出すことも面白いんじゃないかな、と思います。ガイドラインが変わる前に、患者さんにより良い治療ができるかもしれません。
論文を書くには、新しい知見であることと面白いことが必要です。新しい知見だから面白いのですが、注意しなければいけないのは自分が新しくて面白いと思っていても実はすでに報告されているとか、実は専門家の間では常識だとか、そういうことがよくあります。なので、論文を書くネタができたと思ったら早めに目上の先生に相談することをお薦めします(もちろん、自分で勉強したり過去の論文検索は必要です。症例報告でも新規性、何が新しいのかが必要とされます)。私の研究テーマの1つに心電図のP波があります。僧房P波という単語はご存知の先生も多いと思いますが、僧帽弁狭窄でなくても左房拡大する病態は多く、調べてみると意外と論文で明らかにされていないので最近はP波にまつわるいろいろなことを調べて論文にしています。皆さんも日ごろ疑問に思っていて解決したい、ほかの人にも教えてあげたい、そんなことを論文にしていったら楽しく論文が書けるのではないでしょうか。卒後3年目でも早すぎるということはありません。論文を書きたいテーマがあったら早めにCRSTに、循環器関連でしたら私まで(kabu@jichi.ac.jp)ぜひご連絡ください。後期研修生も随時募集中です。待ってます!