自治医科大学医学部同窓会報「研究・論文こぼれ話」その54 同窓会報第109号(2024年10月15日発行)
「膵臓の中に見つけた”星”と病理学研究のこれから」
自治医科大学医学部病理学講座 包括病態病理学部門 福嶋敬宜
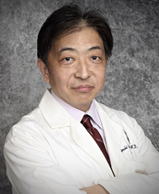
最近の人工知能(AI)の精度には驚愕するものがあるが,病理AIの開発も花盛りである。すでに,一般的な病変の病理診断(多くは良悪性判別であるが)に関しては,そのスクリーニングや病理医の見落としチェックなどに十分な威力を発揮しそうなレベルまで来ている。一枚の病理プレパラートの上には,非常に多くの情報が載っているが,人の目では捉えられなかったり素通りしているものも少なくないと想像される。そのようなものを固定観念のない“目”でスクリーニングしてくれるAIの実用化が待たれる。また、病理学は,組織・細胞の“形”や見た目を相手にした学問でもあり,それらの変化の理由を解明したり,人に伝えるためには,“形”を言葉にするというプロセスも重要になる。このような “形”を言葉にする生成病理AIもまた割と近い内にその日が来るのではという気もしているが、その時の病理医・病理学者が、どのように組織・細胞と対峙しているかは、まだ想像がつかない部分もある。
さて,ここでもっと足元の研究にまつわる話に話題を移そう。私は国立がんセンター(現 国立がん研究センター)中央病院に在籍した30年弱前から膵腫瘍の病理を専門としてきた。そのきっかけの一つになった病変が現在、膵管内乳頭粘液性腫瘍(IPMN)と膵粘液性嚢胞腫瘍(MCN)と呼ばれている腫瘍である。当時は,予後の良い膵癌として見つかってきたIPMNとMCNの両者が別物なのか同じものなのかというのがこの分野の外科,内科,放射線科,病理を跨いで喧喧諤諤と盛り上がった時期であった。IPMNは高齢男性に多く,膵管の中に粘液産生豊富な腫瘍が増生している。MCNは,その患者のほとんどが女性の膵体尾部に発生する嚢胞状腫瘍で,その腫瘍上皮下の間質には特徴的な組織像が見られる、とその特徴の違いは今では医学部の学生も知っているくらいのものだ。しかし,この特徴的な間質組織像を,世界保健機関(WHO)が,「“卵巣型“間質」と表現し,MCNの組織分類の定義に加えたことに、当時の私はかなりのショックを受けたのだ。1996年のことである。実は,このMCNのみに見られる独特の間質の存在に我々も注目しており,海外の雑誌に投稿する直前のことだったのだ。論文執筆のため,多くの関連論文を読んだが,それを指摘したものは当時は皆無だったはずだ。ところが,雑誌論文どころか,腫瘍分類の国際的権威とも言える国際がん研究機関(International
Agency for Research on Cancer, IARC)が発行するWHOの組織分類にいきなり掲載されてしまったのだから。。。
さて,インパクトはだいぶ減じられてしまったものの、その後,投稿した論文は受理されたので一件落着ではあったのだが,そもそもこの間質組織は何ものなのか?そんな疑問はその後,米国に留学してからも私の頭を離れずにいた。そこで,主研究の傍,このMCNの”卵巣型“間質からRNAを抽出し,当時流行りの遺伝子チップで解析してみた。その結果,この間質の遺伝子発現パターンは,組織の見かけだけではなく閉経後の卵巣間質のそれに類似していることがわかった。膵臓の腫瘍であるにもかかわらずだ。そして特に高発現していたのは,ミトコンドリア内でステロイドホルモンの産生に関わるSTAR(steroid acute regulatory protein)という蛋白の遺伝子だった。
それから時は流れ2010年に改訂されるWHO分類では、自分が編集委員の一人という立場になっていた。その時にはすでにIPMNとMCNとは別の腫瘍として広く知られるようになっていたが,MCNの解説文の中にMCNの間質におけるSTAR(星)の存在も刻むことができた。ご存知の方もおられるだろうが,膵臓には”星細胞”(stellate cell)という膵線維化の元になる細胞があり、癌の浸潤周辺では癌関連線維芽細胞(CAF)に変化することから,世界中で多くの研究者が注目し昼夜研究しているといってよい、まさに“スター細胞”と言ってもよい細胞なのである。そんな“星細胞”に比べるとスケールは小さいが,自分にとってはMCN間質における“STAR”は,もう一つの”星”を膵臓内に見つけた思いだった。
先に,「病理学は,“形”や見た目を相手にした学問である」と書いたが,その相手の仕方にはいろいろある。MCNの“卵巣型”間質の様に、形の見た目から研究がスタートする場合もあれば,形に戻ってきて,しっくりと病態が理解できる場合もある。そんな組織・細胞形態⇄分子異常⇄病態と,それぞれの言語化を病理生成AIとやりとりしながら病気の理解を詰めていくのが,今の私にも見えている病理学の将来像の一つである。AIに飲み込まれてしまうか,味方につけて一緒にやっていけるかが,病理学分野だけでのことではない医学・医療の未来像でありカギであろう。
(次号は、自治医科大学附属さいたま医療センター 一般・消化器外科 学内教授 野田 弘志先生の予定です)