自治医科大学医学部同窓会報「研究・論文こぼれ話」その55 同窓会報第110号(2024年10月15日発行)
「“こぼれ出てくる疑問”を臨床研究につなげる」
自治医科大学附属さいたま医療センター 一般・消化器外科 野田弘志
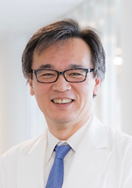
外科の分野に限らず、最もエビデンスレベルが高いと評価される臨床研究は、ランダム化比較試験(Randomized
Controlled Trial; RCT)であることは疑う余地がありません。消化器外科の分野でもたくさんの診療ガイドラインが発表されていますが、ガイドラインの作成においてもRCTの結果が指針の決定に重要な役割を果たします。私たち、自治医科大学附属さいたま医療センター一般・消化器外科ではこれまでに1000人規模のRCTを2つ実施し、CRSTにサポートいただき、結果を英文誌に発表することができました。このRCTを通じて、データを解析し、論文を書いている段階で“こぼれ出てきた疑問”が、次の研究につながっていった私たちの経験を紹介させていただきます。
当科で行った最初のRCTは『抗菌縫合糸の使用による手術部位感染(surgical site infection; SSI) 発生率低減の研究』(UMIN000013054)で、研究の目的は外科の手術後に発生する創感染の予防に抗菌縫合糸が有効か否か?を調べるものでした。外科の先生方はご存じと思いますが、WHOやCDCなどの組織からSSI予防のガイドラインが出されていますが、この中に抗菌縫合糸で創を閉鎖するということが推奨されています。ただ、そのエビデンスレベルは低く、いずれのガイドラインでも弱い推奨に留まっていました。そこで我々は“抗菌縫合糸はSSI予防に本当に有効なのか?”ということをClinical QuestionにしてRCTを計画し、2014年3月から2017年3月の間に1,023症例を集積し、解析を行いました。結果は、抗菌縫合糸を使用しても非抗菌縫合糸を使用してもSSIの発生率に差はなく、抗菌縫合糸の優越性は否定されました。Effect of
triclosan-coated sutures on the incidence of surgical site infection after
abdominal wall closure in gastroenterological surgery: a double-blind,
randomized controlled trial in a single center. SURGERY 2018;164 :91–95. PMID: 29402448 DOI:
10.1016/j.surg.2017.12.020.
新たな疑問が“こぼれ出てきた”のはその結果を論文化している時でした。消化器外科手術で腹腔内操作が終わり、創閉鎖を行う時、日本ではSSI予防のために生理食塩水で皮下を洗浄します。私が研修医だった頃は、皮下を“消毒薬”で“消毒”していましたが、私が佐賀県で9年間の義務年限を終了し、自治医科大学附属さいたま医療センターに赴任した2001年には、“イソジン液には組織障害性があり、創傷治癒遅延を起こすため、イソジンで創を消毒してはいけない”、ということが日本の常識になっていて、全く疑問を持たず、RCT中も生理食塩水で創洗浄を行いました。ところが、文献を調べているとCDCやWHOから出ているSSI予防のガイドラインでは、なんと!ヨードホール水溶液(イソジン)による創洗浄が推奨されていました。論文では正直に創洗浄は生理食塩水で行った旨を記載し、CRST(担当:大口昭英先生)に統計のご指導もいただき、無事に希望する英文誌に掲載されましたが、そこを指摘されたらどうしよう?と内心ハラハラして査読結果を待ったのを記憶しています。その時に、一緒に論文を書いていた当科の市田晃佑先生とともに“こぼれ出てきた疑問”=『欧米で推奨されているイソジンによる創洗浄、日本で行われている生理食塩水による創洗浄、本当はどっちがSSI予防に有効なの?』という素朴な疑問が次のRCTのClinical Questionとなりました。
RCTを行う前に調べてみると、CDCやWHOのガイドラインで推奨されているヨードホール水溶液(イソジン)による創洗浄のエビデンスとなっていた論文は何と!1970~1980年代に実施されていたRCTでエビデンスレベルは低く、その結果を現代の消化器外科に当てはめるのは非常に疑問を感じました。当科で手掛けた2本目のRCT『手術切開による創傷に対するヨードホール水溶液洗浄のSurgical Site
Infection低減効果の検証』(UMIN000036889)は、市田先生が派遣で不在であったため、義務年限終了後の研修に来ていた島根32期卒業の前本遼先生がバトンを受け継いで主導して実施し、2019年5月から2022年3月の間に950例を集積し、解析を行ないました。結果は、イソジン液で皮下洗浄を行った群と生理食塩水で皮下洗浄を行った群のSSI発生率に差はなく、イソジン液を用いた創洗浄の優越性は否定される結果となりました。この結果は、CRST(担当:三重野牧子先生)に統計解析をご指導いただき、無事に希望する外科の英文誌に掲載されました。論文では、現在のCDCやWHOの推奨の再考を主張しており、次のガイドラインの改訂に本論文が影響を与えると期待しています。 Aqueous
Povidone-Iodine Versus Normal Saline For Intraoperative Wound Irrigation on The
Incidence of Surgical Site Infection in Clean-Contaminated Wounds After
Gastroenterological Surgery: A Single-Institute, Prospective, Blinded-Endpoint,
Randomized Controlled Trial. Annals of Surgery. 2023; 277:727-733. PMID:
36538622. doi: 10.1097/SLA.0000000000005786.
このRCTを通じて、前本先生が“SSIって夏に多くないですか?”と何回か私に言っていました。また、RCTが論文化された後、前述の市田先生を交えてSSIについて話していた時に、前本先生がまた“SSIって夏に多くないですか?”と疑問をこぼしたのです。文献を調べてみると整形外科領域では夏にSSIが多いという論文が、本邦も含め複数出ていましたが、消化器外科をターゲットにした論文はなく検討することに興味を覚えました。その時点で前本先生は当科での研修を終了し、地元の島根県立中央病院に戻っていました。この前本先生から“こぼれ出た疑問”=『消化器外科でもSSIは夏に多いのか?』をClinical Questionとして、長年、当科のSSIに関する膨大なデータベースを作成していた市田先生が再度バトンを受け継ぎ、答えを出すべく後方視的研究を行いました。この研究では、スタートからCRSTの三重野牧子先生に統計解析に関する指導をいただき、当院で手術を行った8,463症例について検討を行いました。解析は消化器外科手術と一般外科手術(甲状腺・乳腺・ヘルニアなど)に分けて行ったのですが、一般外科では予想通り夏にSSIが有意に高頻度に発生していたのですが、消化器外科手術では当初の予想を覆して!冬にSSIが有意に高頻度に発生しており、対照的な結果となり、最近、希望する英文誌に無事に掲載されました。(一般外科と消化器外科のSSIの季節性がなぜ異なるのか?原因についてはっきりとしたことは言えないのですが、考察に興味があれば、論文を是非、ご一読ください。)Contrasting seasonality
of the incidence of incisional surgical site infection after general and
gastroenterological surgery: An analysis of 8,436 patients in a single
institute. Journal of Hospital Infection. 2024. PMID: 38950864. doi:
10.1016/j.jhin.2024.06.003. Online ahead of print.
基礎研究でも臨床研究でも、1つのことに結果を見出すと、必ず次の疑問が生まれてきます。この次々に“こぼれ出てくる疑問”に答えを出し続けていくことで、研究が大きくなっていくと思います。どんな研究でも最初の一歩を踏み出すのが大変ですが、私たちはCRSTのサポートのおかげで臨床研究を継続してくることができました。今後も、少しでも臨床に役立つエビデンスを作り、世に発信していきたいと考えていて、現在も2つのRCTを進捗させています。この結果も、是非、将来、報告できるように頑張っていきたいと考えています。卒業生の皆さんも、自分の中で芽生えた疑問に対して、是非CRSTにサポートいただいて、最初の一歩をスタートさせてみてください。
(次号は、自治医科大学 医学部外科学講座 消化器一般移植外科学部門 教授 佐田 尚宏先生の予定です)