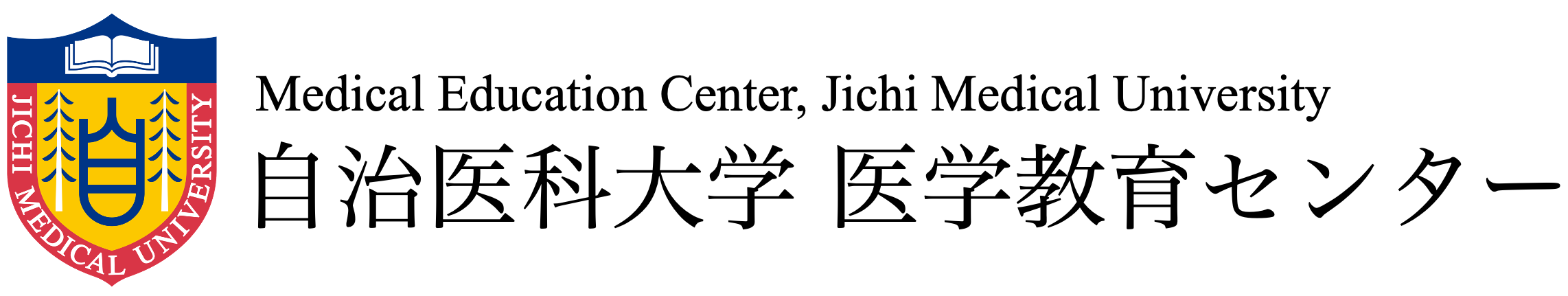担当科目
| M1 | 医療における「学習」と「教育」 | 科目責任者:淺田 義和 | |||
| 1学年 総合教育選択科目 | 10コマ | ||||
| 教育目標 | |||||
| 1) | 生涯にわたって共に学ぶ姿勢を学ぶ。 | ||||
| 2) | 医学・医療・科学技術と社会の変化に応じてキャリアを継続させる能力を身につける。 | ||||
| M1 | ICT時代の情報活用力 | 科目責任者:淺田 義和 | |||
| 1学年 総合教育選択科目 | 10コマ | ||||
| 教育目標 | |||||
| 1) | 生涯にわたって共に学ぶ姿勢を学ぶ。 | ||||
| 2) | 医学・医療・科学技術と社会の変化に応じてキャリアを継続させる能力を身につける。 | ||||
| M2 | 臨床英語 | 科目責任者:松山 泰 |
| 2学年 必修科目 | 5コマ | |
| 教育目標 | ||
| To develop communicative competency for a diversity of patients and their family members in consideration of their culture, nationality, ethnicity, language, and gender identity issues To understand the influence of culture and customs on individuals and groups in medical communication To read medical articles in English for a general understanding of content |
||
| M2 | 総合診断学1 | 科目責任者:松山 泰 | |||
| 2学年 必修科目 | 5コマ | ||||
| 教育目標 | |||||
| 1) | 基礎臨床系統講義で学習する前の臨床的基礎事項を学ぶ。 | ||||
| 2) | 診療録の記載とプレゼンテーションの基礎事項とを学ぶ。 | ||||
| M3 | 地域医療学各論2 | 科目責任者:岡崎 仁昭 | |||
| 3学年 必修科目 | 19コマ | ||||
| 教育目標 | |||||
| 1) | 臨床各科のBSLで学習する前の社会的常識、必須の準備事項を理解し、身につける。 | ||||
| 2) | 医の倫理と患者の権利について理解する。 | ||||
| 3) | コミュニケーションの基礎を身につける。 | ||||
| 4) | 医療安全の基礎事項を学ぶ。 | ||||
| 5) | ハラスメントの基礎事項を学ぶ。 | ||||
| 6) | 緩和ケアの基本を身につける。 | ||||
| ァ) | 緩和ケアの歴史、定義、概念を知る。 | ||||
| ィ) | 緩和ケアに必要な症状コントロールとは何かを学ぶ。 | ||||
| ゥ) | 緩和ケアに必要な態度を身につける。 | ||||
| 7) | 緩和ケアに必要なコミュニケーションの基礎を身につける。 | ||||
| 8) | 緩和ケアに必要な職種間の連携を学ぶ。 | ||||
| 9) | 緩和ケアに必要な地域連携を学ぶ。 | ||||
| 10) | 臨床疫学の基礎を身につける。 | ||||
| ァ) | 臨床疫学とEBMの基本概念を理解する。 | ||||
| ィ) | 疾病の頻度、診断、治療、予後についてEBMを適用する技術を身につける。 | ||||
| ゥ) | 日常的なEBMの利用方法を理解する。 | ||||
| 11) | 臓器移植の種類と適応を理解する。 | ||||
| M3 | 総合診断学2(症候学) | 科目責任者:岡崎 仁昭 | |||
| 3学年 必修科目 | 13コマ | ||||
| 教育目標 | |||||
| 1) | 医学教育モデル・コア・カリキュラムに含まれる37症候の鑑別診断の基礎事項を学ぶ。 | ||||
| M3 | 総合診断学2(臨床推論) | 科目責任者:松村 正巳 | |||
| 3学年 必修科目 | 10コマ | ||||
| 教育目標 | |||||
| 1) | 実際の症例を通して臨床推論を論理的に行う過程を学ぶ。 | ||||
| 2) | 症状・徴候から可能性ある疾患(鑑別診断)を想起する。 | ||||
| 3) | 病歴を時間経過に沿って解釈する。 | ||||
| 4) | 身体診察の重要性を理解し、所見を解釈する。 | ||||
| 5) | 基本的な検査所見を解釈する。 | ||||
| 6) | 病歴、身体診察および検査所見から診断の鍵となる問題を抽出する。 | ||||
| 7) | 観察される症状・徴候、病態、診断となる疾患を因果から捉える。 | ||||
| M3 | 総合診断学2(テュートリアル) | 科目責任者:笹原 鉄平 | |||
| 3学年 必修科目 |
オリエンテーション 2コマ |
||||
| 教育目標 | |||||
| 1) | 学生が自ら問題点を理解し、調べ、解決する能力を養う。(BSL/生涯学習の入り口) | ||||
| 2) | 学生グループが討議し、コミュニケーション能力・チーム力を養う。 | ||||
| 3) | 基礎医学・臨床系統講義の知識を総動員し、患者の病態を推測する力を養う。 | ||||
| 4) | 鑑別疾患を挙げ、論理的に診断を行っていくプロセスを学ぶ。 | ||||
| 5) | 日常的な主訴に関する症候学を学ぶ。 | ||||
| 6) | 医療情報・エビデンスを活用し、医療情報リテラシーを養う。 | ||||
| 7) | 医学英語を活用する能力を養う。 | ||||
| テュートリアルは比較的新しい学習法である。ここでは教員は教えない。学生が自ら学習し問題を解決していかなければならない。 まずpaper patient<仮想患者>の主訴が示される。それを基に6-8名ほどのグループで討論し、鑑別診断や診療方針をうちだしていく。これまで学んできた基礎医学・臨床系統講義の知識を総動員し、仮想患者の病態を推測する。議論が熟したところで病歴、身体所見、検査データが与えられ、さらに議論を深めていく。その仮定で、自分達の知識では解決できない問題点が挙がれば、それが学習課題となり、議論の後に自ら勉強し解答を探し出す。自分たちが「何がわからないか」がわかることが重要で、知識を求める動機付けになる。これがPBLである。最後に講義があり、実際の診断名やその後の治療方針などが示される。 主訴は「頭痛」「腹痛」「呼吸困難」「むくみ」「胸痛」「しびれ」「めまい」などの日常診療で頻度の高い症状である。鑑別診断が多岐にわたるものとなっており、症候学を学ぶことができる。臓器別の基礎臨床系統講義を縦糸とすると、横糸のような内容で、知識の整理に寄与するようなシナリオが用意されている。 |
|||||
| M4 | 総合判定試験 | 科目責任者:松山 泰 | |||
| M5・6 | 総合判定試験 | 科目責任者:松山 泰 | |||
| M4・5 | 臨床講義 | 科目責任者:岡崎 仁昭 | |||
| 4・5学年 必修科目 |
4学年:22コマ |
||||
| 教育目標 | |||||
| 1) | 各分野の疾患の理解の上に、実際の症例にあった際に、病態をどのように考え、評価し、診断し、治療方針を立てるかの、思考過程の築きかたを学習する。 | ||||
| 2) | 主訴から治療までの過程で、疾患別に学習した知識を有機的かつ総合的に利用するかを学習する。 | ||||
| 3) | M4はBSLでローテーションしている学生が症例提示するのを原則とする。プレゼンテーション法を学習する。 | ||||
| 4) | 実際の画像や検査のポイントと鑑別診断について学習する。 | ||||
| 5) | 基礎臨床統合講義では、臨床に必要な基礎医学を復習する。 | ||||
| M6 | 老年医学 | 科目責任者:松山 泰 | |||
| 6学年 必修科目 | 4コマ | ||||
| 教育目標 | |||||
| 高齢化社会の到来を鑑み、高齢者医療の重要性と成人医療とは大きく異なるアプローチが必要であることを学習する。 | |||||
| 1) | 高齢者の心理・精神の変化を説明できる。 | ||||
| 2) | 加齢に伴う臓器の構造と機能との変化を説明できる。 | ||||
| 3) | 高齢者における病態・症候・治療の特異性を説明できる。 | ||||
| 4) | 高齢者における治療上の留意点を説明できる。 | ||||
| 5) | 高齢者の栄養摂取の特殊性を理解し栄養管理を説明できる。 | ||||
| 6) | 老年症候群(誤嚥、転倒、失禁、褥瘡)の病態、治療および予防を説明できる。 | ||||
| 7) | サルコペニア<加齢性筋肉減弱症>の病態、治療および予防を説明できる。 | ||||
| 8) | 高齢者総合機能評価法<CGA>を説明できる。 | ||||
| 9) | 高齢者の生活支援の要点を説明できる。 | ||||