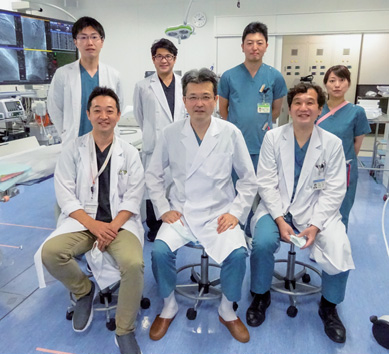不整脈
不整脈治療の背景となる器質的心疾患の有無についての評価および存在する場合の治療介入、血栓リスク管理を含めた適切な薬物療法を行った上で、非薬物療法:カテーテルアブレーション、植込み型デバイス(ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)、心室再同期療法(CRT)手術を実施しており本邦で許可された不整脈手技はほぼ全てを網羅して実施しており、地域の患者さんに最善かつ最適な診療を提供出来る体制を確保しております。
若手医師についても最近では病棟を担当する折に不整脈チームに一定期間配属され、病棟診療のみならずカテーテルアブレーション、デバイス植え込み手技に加わってもらい、次世代の不整脈医養成に努めています。
現在では日本不整脈心電学会認定不整脈専門医を8名擁し非常に充実した陣営であり、当院のみならず、新小山市民病院、佐野厚生総合病院におけるカテーテルアブレーションにも積極的に参画しております。今後さらに地域診療のニーズに応えるべくチーム一丸となって取り組んで参る所存でおりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
臨床アクティビティ 2023年度~2024年度
●心臓電気生理検査・カテーテルアブレーション
年間 291例(内訳)
心房細動 191例
心房粗動・心房頻拍 38例
上室性頻拍 36例
流出路起源期外収縮・心室頻拍 24例
AVBRT・WPW症候群 34例
心室頻拍(器質的心疾患に伴うもの) 6例
Covid19感染下で2023年夏頃までは病棟の入室制限、普及の侵襲的手技の制限などが行われ大きな制約となっておりましたが、2023年度後半以降は1ヶ月あたり25~30件のカテーテルアブレーションを実施できております。
●植込み型電子デバイス植込み・管理
ペースメーカー 年間 116例 (新規 65例、交換 51例)
ICD/ CRT手術 年間583例 (新規 30例、交換 28例)
リード抜去 年間 5例
デバイス植え込み患者は年1~2回程度外来で対面でのデバイス点検を実施しますが、ICD/CRT/ペースメーカーの機種によらず積極的に遠隔監視(機械の情報を専用の小型通信機を用いてWeb上に情報送信)を導入し担当スタッフと臨床工学技士CEとが協力し管理業務を行っております。
研究アクティビティ2023年度~2024年度
COVID19感染拡大の影響で学会が中止・延期あるいはweb開催になるなど大きな制約がありましたが、日本循環器学会、日本不整脈心電学会および関連学会(アブレーション、デバイス)等で不整脈疾患・手技に関する症例報告・臨床研究、不整脈と血圧・血行動態に関する臨床研究について学術発表を行っており、植込み型電子デバイスに関する疫学的研究、カテーテルアブレーション手技にかかる臨床研究・症例報告、血圧計の開発にリンクした形での心房細動検出アルゴリズム開発など多岐に渡る研究成果が論文化されております。
日本循環器学会、日本不整脈心電学会および関連学会、AHA、ESC、EHRA等で不整脈疾患・手技に関する症例報告・臨床研究、不整脈と血圧・血行動態に関する臨床研究について学術発表を行っており、カテーテルアブレーション手技にかかる臨床研究・症例報告、心房細動発症あるいはカテーテルアブレーション後の再発と高血圧との関係性についての検討、植え込み型電子デバイスに関する疫学的研究など多岐に渡る研究成果が論文化されております。
毎週不整脈カンファランスを開催し症例検討会を行い、不定期ですが研究ミーティングも実施しております。後進の指導については、ペースメーカー植え込みが独立して実施出来ること、植え込み型ICDの原理・設定について熟知していること、発作性心房細動を含めた上室性不整脈に対するカテーテルアブレーションが実施できることを到達目標として指導体制を敷いています。
今後の目標
新館南棟の新しいカテーテル室に移り6年が経過し、2023年11月にはヘリポートも完成して救急応需体制が充実しました。また、2025年4月には大きく一つに統合されたICU/CCUの運用が開始予定です。今後この環境を有効活用し、カテーテルアブレーション、植込みデバイスの両面において更なる安全性と治療成績を向上しつつ症例数増加を図りたいと考えております。また全国で活躍される本学卒業生や外部医療機関からの見学・研修の受け入れも積極的に進めたいと考えております。