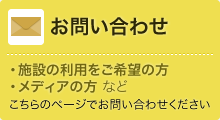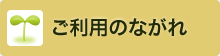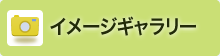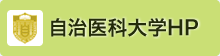令和7年度 第2回 自治医科大学・先端医療技術開発センター
共同利用・共同研究の公募について
当センターは実験用のブタ(ピッグ;注1)を用いた医学橋渡し研究や医学トレーニングを専門に行う施設です。一般的にピッグを用いた医学研究やトレーニングを行うためには、専門の施設、設備、人員、ピッグの飼育が必要なだけでなく、それを維持するためのコストがかかります。当センターは文科省より共同利用・共同研究拠点として認定を受けており、学外の方でも
- 1.リーゾナブルなお値段で(注2)
- 2.私達ピッグの専門家との共同研究として
- 3.ピッグセンターの全ての施設を活用しながら
皆さまのご研究を発展させることが可能です。ピッグを扱った経験のない方でも心配ご無用。実際、ご利用されたほとんどの方は最初ピッグ利用経験がありませんでしたが、ご利用後、論文発表、特許出願、医療機器の上市、治験に繋がる多くの成果を挙げました。日本外科学会または日本先進医工学ブタ研究からの推薦を受けて申請していただくと、公募期間外でも申請を受け付けます。
毎年、共同研究・共同利用の公募を行っており、本年度も以下のように課題を募集します。
提案書はたったのA4用紙1~2枚です(注3)。皆さまからいただいた提案書を学内外の専門スタッフが検討し、必要に応じて実施内容を修正し、おおよその実施期間や予算をご提示した上で、実施するかどうかを決めます。双方納得の上、実施すると決まれば、提案者と当センタースタッフ(注4)が一緒に実施計画を立て実行するという流れになります。ぜひお気軽にご応募ください。
注1 : ブタは食肉を主目的とする産業動物ですが、実験動物としても重要です。当センターでは、実験動物としてのブタをピッグと呼んでいます。当センターはピッグ利用に特化した施設ですが、利用目的・内容によっては他の動物を扱う場合があります。ピッグ以外の動物を扱いたい場合は、ご提案前に「公募要領3.提出先」にご相談ください。
注2 : 「公募要領1.申請資格」を参照。この共同利用・共同研究性は大学等非営利組織を対象としています。しかし、企業等営利組織の方のご利用も歓迎します。費用は多少高くなります。見積り等は当センター共同利用コーディネート部門担当にお問い合わせください(pig-center@jichi.ac.jp )。
注3 : 「先端医療技術開発センター共同利用提案書」は、当センターホームページからダウンロード又はメールでpig-center@jichi.ac.jpまでご請求ください。http://www.jichi.ac.jp/cdamt/riyou/gakugai.html#riyou
注4 : 提案毎に当センタースタッフを割り当て、提案者のご利用のサポートに努めます。
本センターの特徴
- ピッグに対応した設備・機材をご利用いただけます
- ・手術室(クラス10,000)、集中治療室、セルプロセッシングルーム
- ・MRI(1.5テスラ)、CT(128列)、C-arm
- ・鏡視下手術システム、循環動態モニタリングシステム、慢性実験テレメトリーシステム
- ・特殊飼育ケージ(体重200kgまで。新生仔、分娩に対応)
- 以下のようなピッグでの研究・トレーニング事例があります
- ・ピッグをヒトに見立てた医療機器開発(内視鏡、ステントなど)
- ・ヒトと等量の投与量によるウイルスベクターの遺伝子治療効果検討
- ・ヒトiPS細胞由来の組織をピッグに移植する再生医療研究
- ・重症複合免疫不全症ピッグのゲノム編集治療研究
- ・無菌ピッグやヒト腸内細菌定着ピッグを用いた腸内細菌研究
- ・ゲノム編集による疾患モデルピッグ作製支援
- ・麻酔下での外傷手術チームトレーニング法の検討
- ・ピッグの精子/卵子/初期胚を用いた生殖医療研究
- ・ピッグの精子/卵子/初期胚を用いた生殖工学トレーニング
公募要領
企業等営利団体の方々は別途、ご相談に応じます。
自治医科大学 先端医療技術開発センター 共同利用コーディネート部門
E-mail:pig-center@jichi.ac.jp
次年度の研究計画について、チェックボックスにご記入ください。実験内容を大幅に変更する場合は、変更版の提案書をご提出いただく必要があります。変更が無い場合は、次年度における年度更新のための研究提案書の提出は必要ありません。
E-mail:pig-center@jichi.ac.jp
TEL:0285-58-7456(ダイヤルイン)
FAX:0285-44-8629
先端医療技術開発センター共同利用提案書
2.令和7年度 第2回 研究提案書_研究提案例 (Word 292KB)