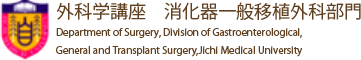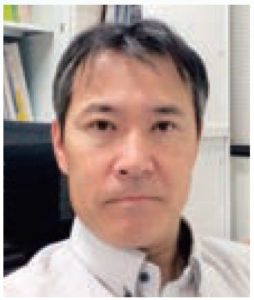移植・再生医療センター 教授
秋田大学 1992年卒業
移植外科は、2001年4月から小児外科・移植外科としてスタートしましたが、2019年3月からは消化器一般外科の仲間となり現在消化器一般移植の中の一診療科として活動しています。2024年4月現在の院内スタッフは、佐久間、大西、眞田、脇屋、平田で、大豆生田がレジデントとして在籍しています。岡田は、腹腔鏡やロボット手術を勉強しに埼玉医大総合医療センターへ、堀内は消化器外科手術のさらなる研鑽のためにJCHOうつのみや病院へ派遣にでています。また昨年入局してくれた高寺は、現在新小山市民病院にて多くの手術を執刀させてもらっており活躍中です。
当科は肝移植を中心とした診療を行っており、2023年12月までに404例を施行しました。この間、2008年10月には、日齢17、体重2.6㎏の新生児劇症肝不全症例に対し肝S2 亜区域を用いた生体肝移植を施行し救命させることができました。本症例は当時の生体肝移植成功例の中では、 本邦最年少・最軽量で、世界でも2番目に低体重の症例であり、このニュースは読売新聞の1面にも掲載されました。このS2 グラフトを用いた低体重例への生体肝移植は、国内外で多大な評価を受けています。現在は小児末期肝疾患に対する肝移植だけではなく、成人も含め年間20例前後のペースで肝移植を行っており、国内でも有数の肝移植施設として成長してきました。
また、移植後10年生存率は約95%と全国トップの成績で、これもひとえに団結したチーム医療の賜物と考えています。2010年には脳死肝移植実施施設(小児)となり、その実施と普及に取り組んでおり、2022年には成人の脳死肝移植実施施設にも認定されました。今年はすでに5名の患者さんの脳死ドナーからの肝移植を行い、北関東初となる肝腎同時移植も行いました。
これまでドナー手術は腹腔鏡補助下や小切開で肝切除を行ってきましたが、保険改正に伴い(完全)腹腔鏡下で行うことができるようになりました。当院も保険運用できるよう施設認定を受け、昨年末には佐久間がプロクターを取得しました。肝離断までは腹腔鏡で行い、摘出時に7cmの皮膚切開をおく自治医大独自の方式で開始しております。
肝移植以外では、2011年に脳死小腸移植実施施設に認定されております。これまで移植の実績はありませんが、腸管リハビリテーションに関する勉強会を開始し、残された消化管の機能を有効に使えるよう目指しています。中でも、食事性ポリアミンによる短腸症候群における消化・吸収能の改善をこれまでの研究で明らかにしており、実臨床でも使用を開始し、良好な結果が得られています。
2019年から、膵臓移植の脳死実施施設を目指して他院への手術参加や、豚を用いた臓器摘出トレーニングを行ってきましたが、2022年膵臓移植実施認定施設になる事が来ました。これまで、内分泌内科や腎臓外科の先生と連携し、10名近い患者さんが膵・腎同時移植の登録準備中であります。

若手むけ臓器摘出トレーニング
様々な分野において、学内、学外施設と積極的に臨床、研究の交流を行っています。海外ではカルフォルニアのアーバイン校と交流を行っていますが、コロナ禍という事もありwebカンファレンスを行うにとどまっています。現在行っている研究は、小児生体肝移植後のテロメア長によるグラフト肝年齢の解明、肝移植における常温酸素化灌流のグラフト肝保存効果、エクソソームによる前転移ニッチ形成における好中球細胞外トラップの意義、胆汁中miRNAによる早期拒絶反応の診断、胆汁酸分析と質量分析イメージング法による小児肝疾患の早期診断ならびに病態解明などがありますが、最近では東京大学工学部と連携して移植後早期血流障害の診断などを目的としたWearableデバイスの開発に取り組んでいます。これらは科研費をはじめとした研究費を獲得して行っていますが、今年も2件の科研費を取得することができました。(・肝切除後フェンタニル血中濃度と網羅的メタボローム解析によるPONVリスク因子の検討・小児肝移植における移植肝の予後マーカー解析)
臨床研究では、AMED案件である心停止後臓器提供時のECMOによる臓器(肝臓・膵臓・腎臓)機能温存やヘモクロマトーシス予防のための経胎盤的大量γグロブリン投与、肝胆膵疾患を対象としたヒトiPS細胞を用いた病態解明などにも積極的に参加しています。
少ない人数ながらいろんな事にチャレンジして、日々頑張っていますので興味のある方はいつでも連絡して下さい!
移植外科部門のホームページがあります。 是非ご参照ください。
http://www.jichi.ac.jp/transplant/