
医学部
School of Medicine



教員VOICE
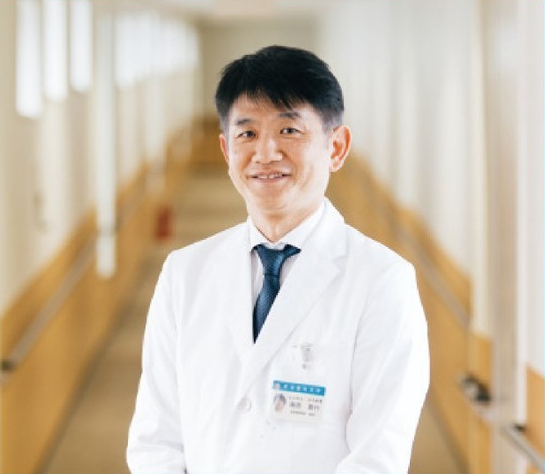
産科婦人科学講座 婦人科学部門
教授
藤原 寛行

感染・免疫学講座 医動物学部門
教授
加藤 大智

附属さいたま医療センター
総合医学第1講座(腎臓内科)
教授
森下 義幸

小児科学講座
准教授
小島 華林

脳神経外科 教授
附属病院長
川合 謙介

病理学講座 教授
附属病院病理診断部・病理診断科 部長・診療科長
福嶋 敬宜

腫瘍センター 臨床腫瘍部 准教授
附属病院臨床腫瘍科
大澤 英之

附属さいたま医療センター
消化器内科 准教授
松本 吏弘
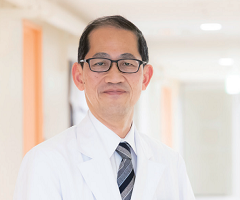
整形外科学講座 教授
附属病院整形外科
竹下 克志

総合教育部門
文化人類学研究室 教授
田中 大介

さいたま医療センター
総合医学第2講座 教授
(一般・消化器外科)
野田 弘志

附属病院救命救急センター 副センター長
救急医学講座 教授
米川 力
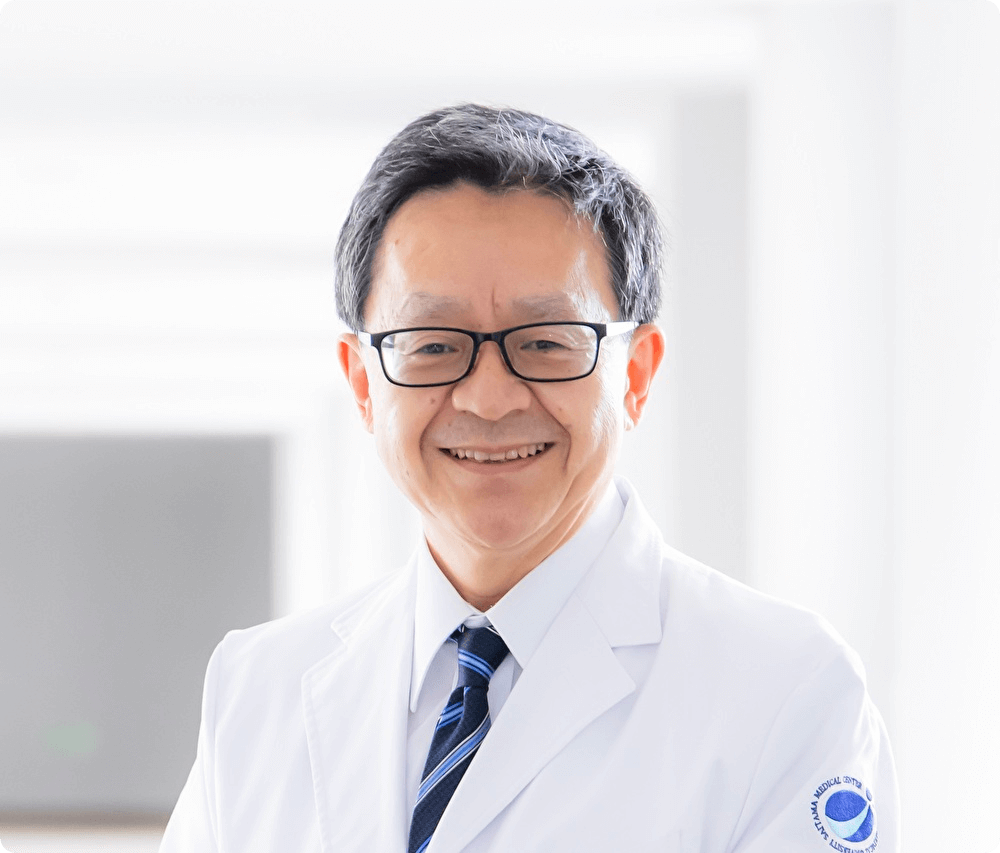
さいたま医療センター センター長
総合医学第2講座 呼吸器外科
教授
遠藤 俊輔
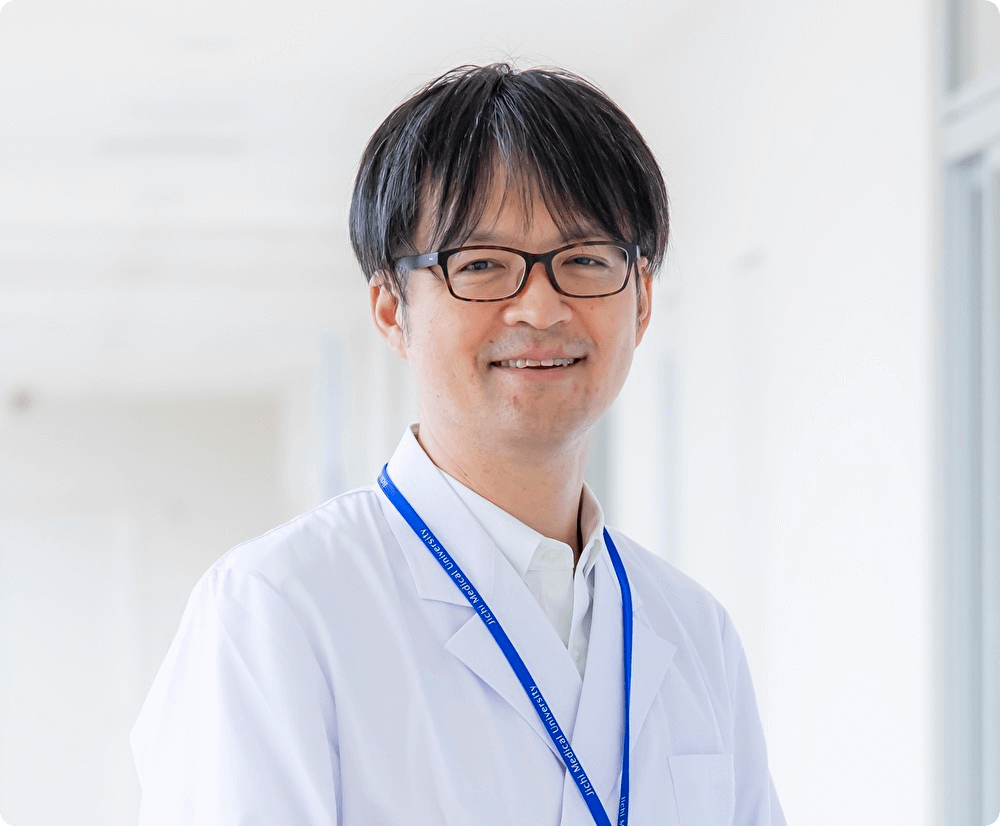
分子病態治療研究センター
循環病態・代謝学研究部 教授
附属病院循環器センター内科部門
武田 憲彦
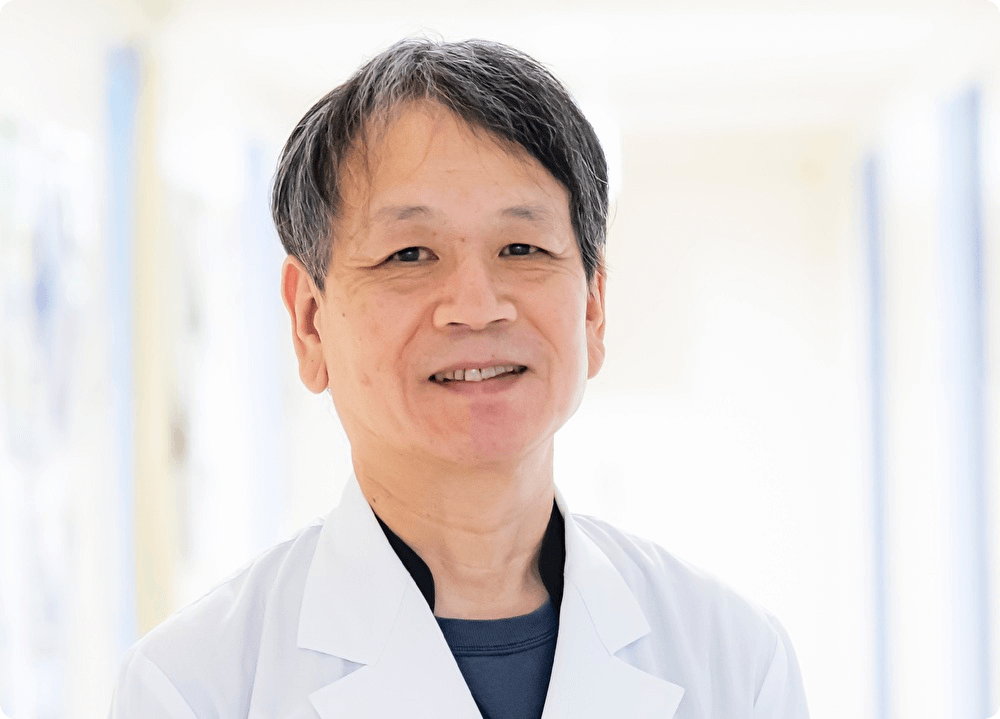
脳神経外科学講座 教授
附属病院脳神経センター外科部門
益子 敏弘
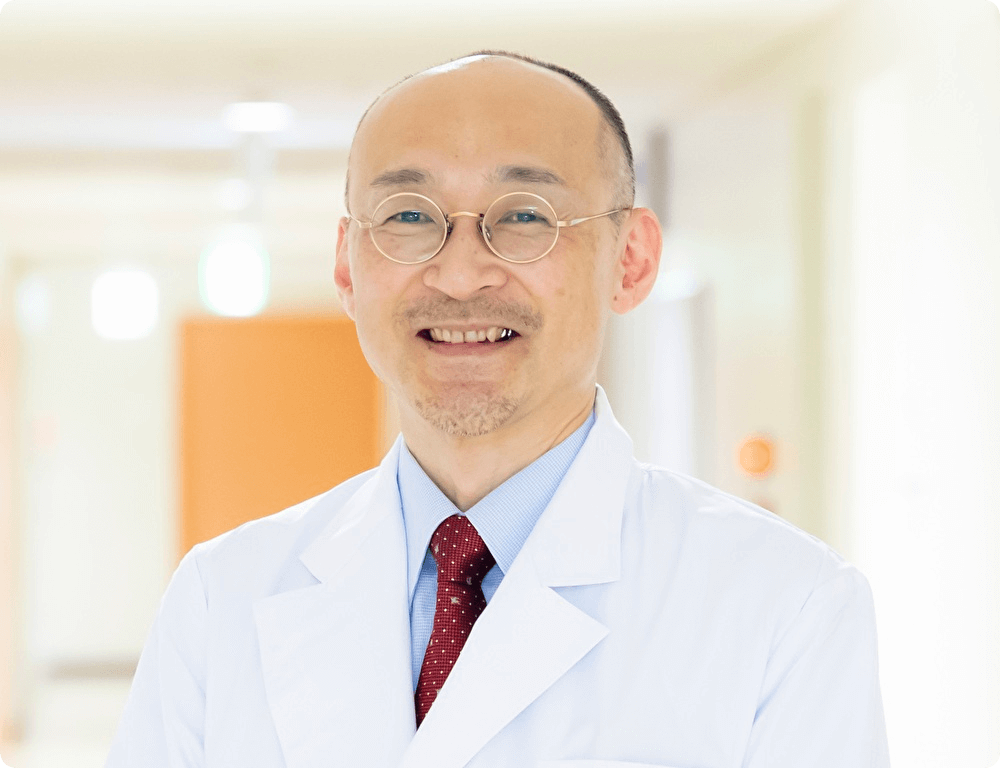
小児科学講座 小児医学部門 教授
とちぎ子ども医療センター 小児科
熊谷 秀規
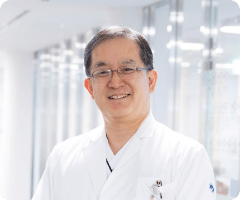
さいたま医療センター副センター長
総合医学第1講座
主任教授(循環器内科)
藤田 英雄
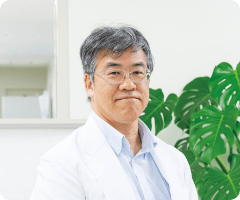
救命救急センター センター長
救急医学講座
教授
間藤 卓
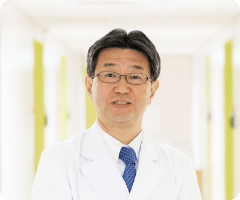
臨床研究支援センター
内科学講座(呼吸器内科学部門)
教授
坂東 政司
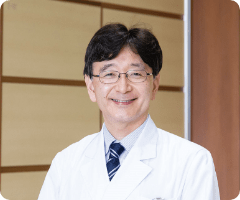
医療の質向上・安全推進センター
センター長
内科学講座(循環器内科学部門)
教授
新保 昌久
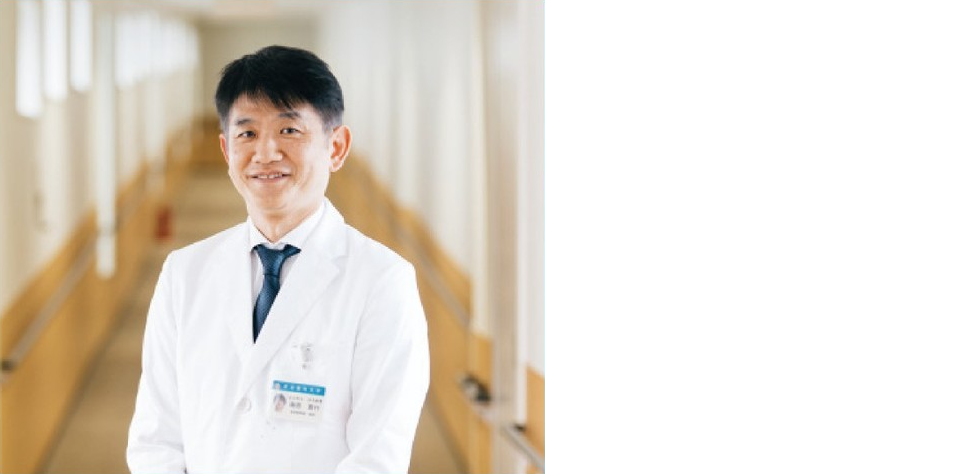
産科婦人科学講座 婦人科学部門
教授藤原 寛行
1990年山口大学医学部卒業。日本医科大学救命救急センターレジデント、沖縄米海軍病院インターンを経て、国立小児病院(現国立成育医療センター)麻酔・集中治療科勤務。1995年より自治医科大学産科婦人科学講座に入局、1999年同大学院修了、同助手を務め2003年講師、2004年婦人科病棟医長、2008年准教授、2015年教授を経て、2020年より主任教授。
ライフステージに応じた診療で
女性の一生に寄り添い支える。
産婦人科の診療は大きく「産科」「婦人科」「不妊内分泌」「女性医学」という4つに分けられ、女性の一生を支える幅広い医療を提供しています。私は卵巣がん、子宮頸がん、子宮体がんなどの悪性腫瘍を専門としており、手術、化学療法、放射線療法などを用いた集学的治療のほか、自治体と連携した検診に関する研究や多施設共同で行う臨床研究なども行っています。
がん医療において大切なことに、「早期発見」と「予防」があります。例えば、婦人科の扱う子宮頸がんは検診の効果が認められていますが、日本では受診率が低いという問題があります。またワクチンによってある程度予防することが出来ますが、このワクチン接種率も諸外国と比べると低率です。早期発見やワクチンによる予防などは、自治体と連携しながらより良い方策を探る必要があり、多方面との調整が必要になってきます。ここで求められるのが総合的な力だと思います。
自治医科大学では、地域に出て活躍する人材を育成することに力を注いでいます。ただ単に医学的知識を身に付けるだけでなく、地域社会を守るという観点から地域との連携や調整力も大事です。私たちは日々患者さんに寄り添いながら「診療」を行い、また将来の患者さんのために「研究」を行います。そしてこれらを引き継いでくれる新しい医師を育てるために「教育」を行っています。自治医科大学に集い、総合的な力を持った医師に是非ともなって欲しいと思います。
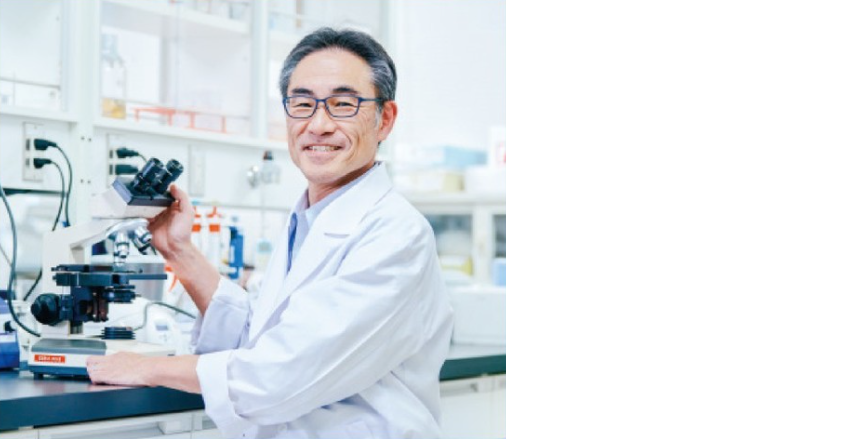
感染・免疫学講座 医動物学部門
教授加藤 大智
1999年東京大学大学院農学生命科学研究科獣医学専攻博士課程修了。米国アラバマ大学バーミンガム校免疫ワクチンセンター博士研究員、東京医科歯科大学医歯学総合研究科免疫治療学教室博士研究員、山口大学農学部獣医学科獣医衛生学教室准教授、米国国立衛生研究所客員研究員、北海道大学大学院獣医学研究科寄生虫学教室准教授を経て、2016年より現職。
熱帯・亜熱帯地域を中心に蔓延する
寄生虫を研究し感染症対策につなげる。
「リーシュマニア症」は、熱帯・亜熱帯地域を中心に蔓延する寄生虫感染症で、顧みられない熱帯病の1つです。日本では馴染みがありませんが、ヨーロッパの地中海沿岸地域を含む世界98カ国で流行し、総患者数は1200万人以上。年間2~3万人の死者も発生しています。その病気を媒介するのが体長2~3mmという極小の吸血昆虫サシチョウバエです。一部のサシチョウバエの体内では「リーシュマニア原虫」という寄生虫が増殖し、吸血行動によってこの寄生虫が人や動物に感染します。約20種いるリーシュマニア原虫がどの地域で流行し、どのような種が病気の原因となるのか、また、1,000種以上ものサシチョウバエの中でどの種がリーシュマニア原虫を媒介するか、どのような動物が人への感染源になるのか。現在でも分かっていないことが多く、効果的な感染対策、治療・予防法の開発が進んでいないのが現状です。そこで、世界各地のフィールドを飛び回り、捕獲したサシチョウバエや感染者から採取したリーシュマニア原虫を現地で調べ、またラボにも持ち帰り、流行把握や疾病対策、さらに遺伝子解析などを進めています。
私たち人類は生物と関わりながら生活を営んでおり、人体に害を与える生物も数多く存在します。国内においてもアニサキス、トコジラミ、マダニなどによる被害も少なくありません。地域医療に従事する医師には総合的な判断が求められることから、「医動物学」の知識を頭に入れておくことも重要です。
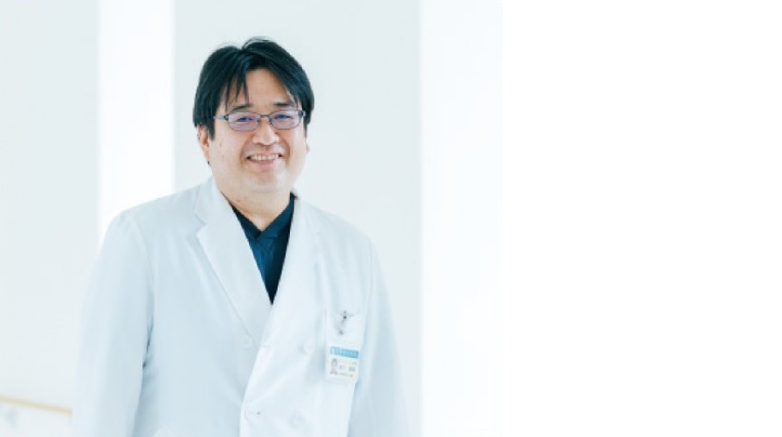
附属さいたま医療センター
総合医学第1講座(腎臓内科)
教授森下 義幸
1996年自治医科大学卒業。岡山赤十字病院と附属病院腎臓内科での研修、岡山県の地域医療を経て、2007年米国ハーバード大学ImmuneDiseaseInstituteポストドクター、2008年岡山大学大学院医歯学総合研究科免疫学分野博士課程修了。2010年自治医科大学腎臓内科助教、2013年同講師を経て、2015年より附属さいたま医療センターにて教授、2020年同センター長補佐兼務。
地域連携による重症化予防と
新遺伝子治療法の開発を推進。
腎臓は老廃物を体内から排出する機能を持っており、人体を正常な状態に保つために欠かせない臓器です。しかし、腎臓の働きが低下する慢性腎臓病(CKD)の国内患者数は2023年時点で1,480万人(成人の約7人に1人)、腎不全に伴う透析患者数は34万人を超えると推計され、新たな国民病として患者さんの生活や国の医療経済面に大きな影響を及ぼしています。
CKDは早期発見・早期予防による重症化予防が極めて肝心であることから、当センターが主軸となり2020年に運用を開始したのが「さいたま市CKD診療連携プログラム」です。腎機能低下を示す数値など紹介基準を明確にすることで、かかりつけ医が私たち腎臓専門医と連携しやすい仕組みを整えようと二人主治医制を導入しました。薬物療法や食事療法などの情報を共有し、専門看護師や管理栄養士、臨床工学技士と連携しながら、患者さん一人ひとりの状態に応じた適切な診療を行うことで重症化予防とQOL維持・向上に努めています。
また、CKDは「慢性糸球体腎炎」や「糖尿病性腎症」など数十種類に分類され、それぞれに治療法も異なるため各治療法と診断法の開発も必要です。私は、臨床に加えて人体の細胞内におけるタンパク質の合成量を調整する「マイクロRNA」を用いた開発研究も行っており、これまでに複数の新遺伝子治療法と早期診断マーカーの開発に従事してきました。今後も臨床で得られた知見を研究に活かし、さいたま市から全国に向けて最先端の腎臓医療を広げていきます。

小児科学講座
准教授小島 華林
2001年自治医科大学医学部卒業。青森県立中央病院で初期研修後、大間病院、佐井診療所を経て、附属病院小児科学で後期研修を行う。その後再び長崎県対馬いづはら病院で地域医療に従事し、自治医科大学大学院入学。博士課程修了後、自治医科大学小児科学入局。大学附属病院、新小山市民病院、栃木県立リハビリテーションセンターでの研鑽、米国ベイラー医科大学遺伝子細胞治療センター留学を経て、2022年より現職。
目の前にいる一人の子どもから
世界中の子どもたちの未来のために。
「小児神経疾患」とは、遺伝的あるいは環境的な影響で、発達期の子どもの脳の構造や機能が変化し発症する病気です。幼くして発作症状や機能障害を患い、生涯にわたって寝たきり状態を余儀なくされることもあり、ご本人・ご家族の一生に影響します。これまで、ほとんどの疾患は根本的な治療法がありませんでした。
しかし、近年、人の遺伝子の解析技術が飛躍的な進歩を遂げ、遺伝的影響と疾患の関連がわかるようになり、その常識は覆りつつあります。欠損している遺伝子の補充や新たな機能を細胞に付加する「遺伝子治療」が小児神経疾患に有効で、世界中で治療の期待が高まっているのです。その一つが、私が研究している「AADC欠損症」です。これは世界で約350人、日本では11人という希少難病です。AADC欠損症に有効な遺伝子治療が開発され、これまで国内外の子ども10人に治療を行いました。その結果、治療したすべての子どもの症状が著しく改善しています。寝たきり状態の12歳の少女は、治療後6年で支持歩行ができるようになり、首が据わらなかった7歳の少女は、治療後3年で泳げるようになりました。現在は、遺伝子治療を他の小児神経疾患に応用する研究を進めているほか、保険適用にすることで病気の子どもたちがすぐに治療を受けられる環境づくりに努めています。目の前の子どもから世界中の子どもたち、そして子どもを支えるご家族を笑顔にするために、研究はこれからも続きます。
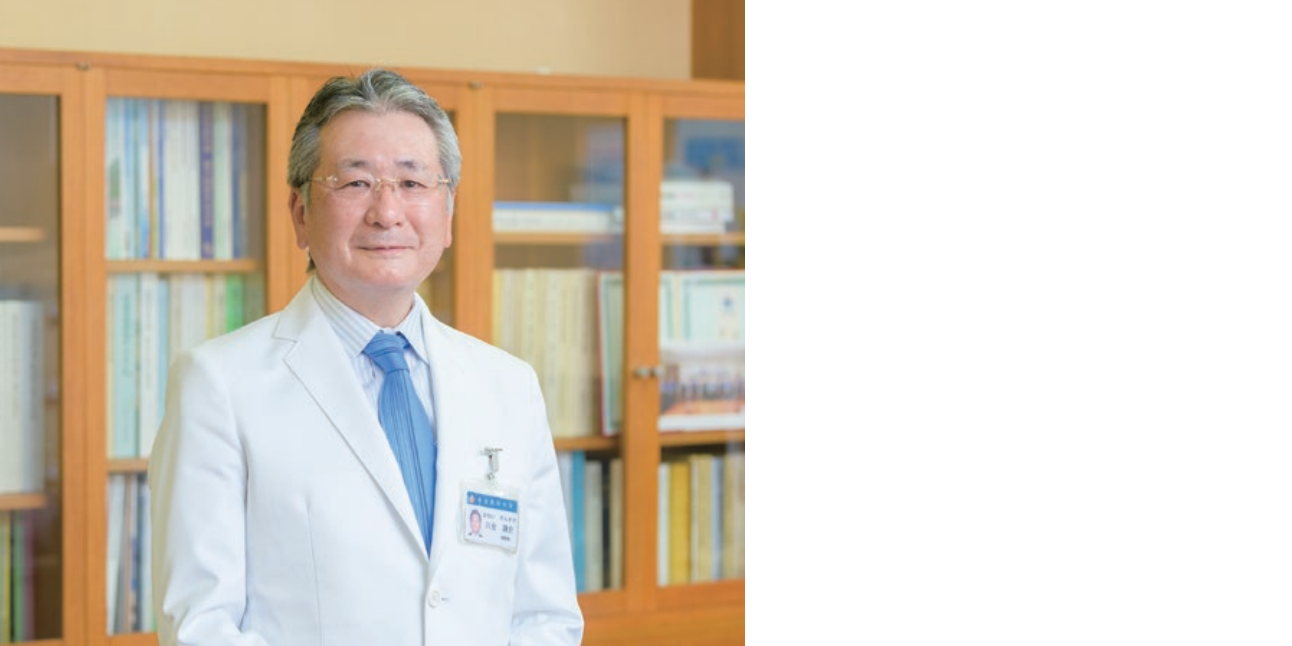
脳神経外科
附属病院長
教授川合 謙介
1987年東京大学医学部卒業。東京大学、総合会津中央病院、米国国立衛生研究所、寺岡記念病院、帝京大学、東京都立神経病院などで脳神経外科臨床および脳神経科学研究の研鑽と実績を積み、東京大学医学部・大学院脳神経外科准教授、NTT東日本関東病院脳神経外科部長を経て、2016年より附属病院脳神経外科教授、2022年より附属病院長。
脳外科治療で患者さんに、
脳機能研究で人類に貢献する。
脳神経疾患を主に手術で治療するのが脳神経外科です。対象は、脳腫瘍、脳血管障害、脳機能的疾患などで、開頭手術で顕微鏡下に脳腫瘍を摘出したり、くも膜下出血を起こす動脈瘤にクリップをかけたりします。私が特に力を入れて取り組んできた脳機能的疾患にはてんかんやパーキンソン病などがあり、大脳そのものの機能変調に対して原因部位を切除したり、体内植込型電気剌激装置で脳機能を調節したりして治療します。治療で症状がなくなると生活の質が大きく改善するので患者さん達から大変感謝されますし、とてもやり甲斐のある領域です。
さらに、これらの治療を安全確実に行うために治療前や手術中に脳に電極を入れて、人の脳機能を直接個別に調べることがあります。脳神経科学の手法には培養神経細胞や動物モデル実験から最先端の脳画像検査などさまざまなものがありますが、脳神経外科はヒトの脳に直接アプローチできるので、他の手法では得られないきわめて貴重な情報をもたらしてくれます。歴史的にも脳神経外科が脳神経科学の発展へもたらした貢献はとても大きいですし、自分たちの研究が脳機能の解明を通じて人類に貢献していると実感しています。
自治医科大学で学ぶ医学生の皆さんには、罹患率の高い脳神経疾患、特に脳卒中とてんかんについて、基本を押さえてもらえるように心がけています。しっかりと知識と技術を修得して地域のプライマリケアに貢献されることを願っています。
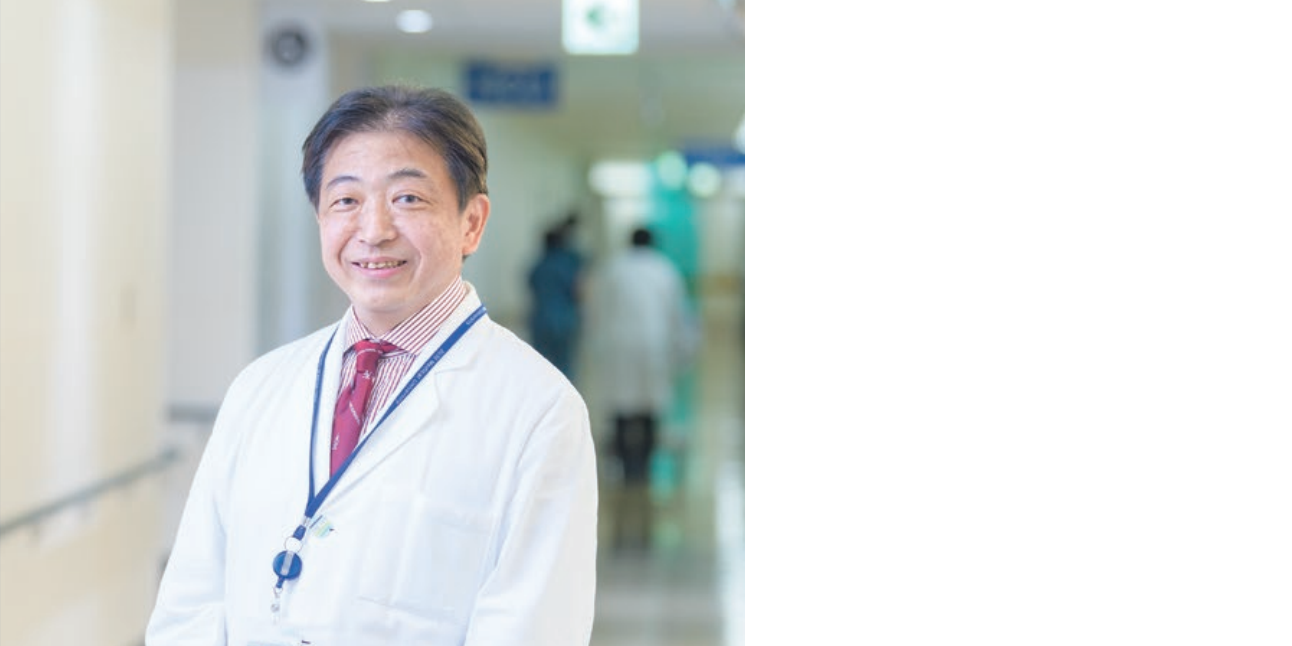
病理学講座 准教授
附属病院病理診断部・病理診断科 部長・診療科長
教授福嶋 敬宜
1990年宮崎医科大学医学部卒業。NTT関東逓信病院、国立がんセンターを経て、2001年に米国ジョンズ・ホプキンス大学病理部門研究員となる。2004年に帰国後、東京医科大学や東京大学大学院にて病理学講座の講師・准教授、東京大学病院病理部副部長を経て2009年より現職。
病理医の視点を持つことで
臨床の精度をより高められる。
「病理学」は病気の成り立ちやメカニズムを組織・細胞レベルで研究します。そして、これらの基礎研究によって蓄積された知見を患者さんの病気の診断に活かすこと、それが「病理診断学」です。がんの場合、採取した組織を調べると非常に高い確率でその種類まで判定できます。 つまり、がんの最終判断をするのが病理診断であり、病理医が提供する情報をもとに臨床医が患者さんの治療方針を決めていきます。
私が専門とする膵臓がんは診断から5年後の生存率が7~8%とがんの中でも特に予後が悪く、体の深部に位置するためがんの早期発見が非常に困難です。そこで、がんが臓器の中でどのように変化するのかなど病理学的な研究が進められており、近年では、まだ浸潤していない「上皮内癌」が見つかり始めています。さらに研究が進んで早期発見できるようになれば、やがて生存率を高めることができると期待されています。
病理医は、臨床医と異なる視点で患者さんを診ています。そのため、病理医の視点を持つことで多角的な観点から病態を読み解けるようになり、臨床の精度も高まります。学生たちには 表面をなぞるのではなく、「なぜ症状が出ているのか?」「体の中では何が起きているのか?」 など、常に疑問を持ちながら疾患の本質を探り、そして、自治医科大学の強みであるジェネラルな力にプラスして自分にしかない強みを身につけていってほしいと願っています。

腫瘍センター 臨床腫瘍部 准教授
附属病院臨床腫瘍科
准教授大澤 英之
1998年自治医科大学医学部卒業。愛媛県立中央病院で初期研修後、国保中島中央病院、四国中央市国保新宮診療所で地域医療に従事。愛媛県での勤務終了後、附属病院消化器センター外科、乳腺総合外科を経て、自治医科大学大学院入学。博士課程修了後、2015年より附属病院臨床腫瘍科、臨床研究センターを経て現職。
治療することも医師の仕事であり
最期を見守ることも医師の仕事。
がんの薬物療法を専門とするのが臨床腫瘍科です。以前は各診療科で薬物治療を行っていましたが、治療の多様化・複雑化に伴い臓器横断的に治療を行う腫瘍内科が注目されるようになり、附属病院では臨床腫瘍科として2006年に設置されました。
薬物療法には、がん細胞を直接攻撃する「抗がん剤」、がん細胞などに特有の分子を標的にした「分子標的治療薬」、免疫細胞の働きを活発にしてがん細胞を攻撃できるようにする「免疫チェックポイント阻害剤」など様々なジャンルの薬物が存在し、その組み合わせも多数あります。日本の標準治療であるガイドラインを参考にしながら、患者さんの病状や体調、また、どんな生活を望まれているか、どこで最期を迎えたいか、などご本人やご家族の希望、医療スタッフの意見なども含めて全人的観点から検討し、薬物療法によって得られる利益と副作用のバランスを取りながら、患者さんとともに治療方針を考えていきます。
臨床腫瘍科での仕事は、地域医療に従事する自治医科大学卒業生の働き方に 近いものがあります。へき地や離島では一人の医師があらゆる疾患の患者さんを診ますし、最期を見守ることもあります。どうしたら患者さんのためになるかを考え、最期を迎えるまでやるべきことをやり切ることは共通しています。私自身も、自治医科大学生としての経験はとても大きいものでした。私たちは、患者さんの人生を診る医師でもあるのです。

附属さいたま医療センター
消化器内科 准教授
准教授松本 吏弘
1999年自治医科大学医学部卒業。国立病院機構長崎医療センター、長崎県立上対馬病院を経て2002年に附属さいたま医療センター消化器内科で後期研修を行う。その後、長崎県上五島病院で再び地域医療に従事し、2008年より附属さいたま医療センターにて助教、講師となり、2018年より現職。
国の難病と対峙するために
重要となるのが医師による見極め。
炎症性腸疾患は、私が生まれた当時は数百人ほどでしたが、現代では若い世代を中心に右肩上がりに増えており、2016年の段階で患者さんの数は約22万人に上ります。自分の免疫細胞が腸の細胞を攻撃してしまうことで炎症が起きる病気で、ひどくなると腸に穴が空き大腸を全摘出しなければならなくなります。原因は分かっておらず、食事の欧米化、化学物質の服用、ストレスなど様々な要因が複合的に重なって発症すると言われています。
メインは薬物治療となります。炎症が軽ければ基礎的な飲み薬ですみますが、炎症が重くなると注射などによる薬物投与が必要になります。これらの薬物はとても高額ですが、国の難病に指定されていることから患者さんの負担も少なくてすみます。しかし、誰もが高額な薬を使うと医療経済を保てません。そのため、どの薬物を使うか、いつまで使い続けるかなど医師による見極めがとても重要となります。
炎症性腸疾患に対して現在のところ完全に治癒させる治療方法がなく、課題は山積しています。国内の医療機関において一つずつ症例を積み重ねることでエビデンスをまとめることが急務であり、 標準治療のガイドラインを明確化することに貢献できればと考えています。
出身の都道府県によっては希望する専門医になれないことがあるかもしれません。しかし、自治医科大学の学生だからこそ歩める道もあります。その一つが地域医療であり、住民や患者さんとの深い関わりです。医師として一番大事なことを若くして経験できるのは、とても貴重なことなのです。
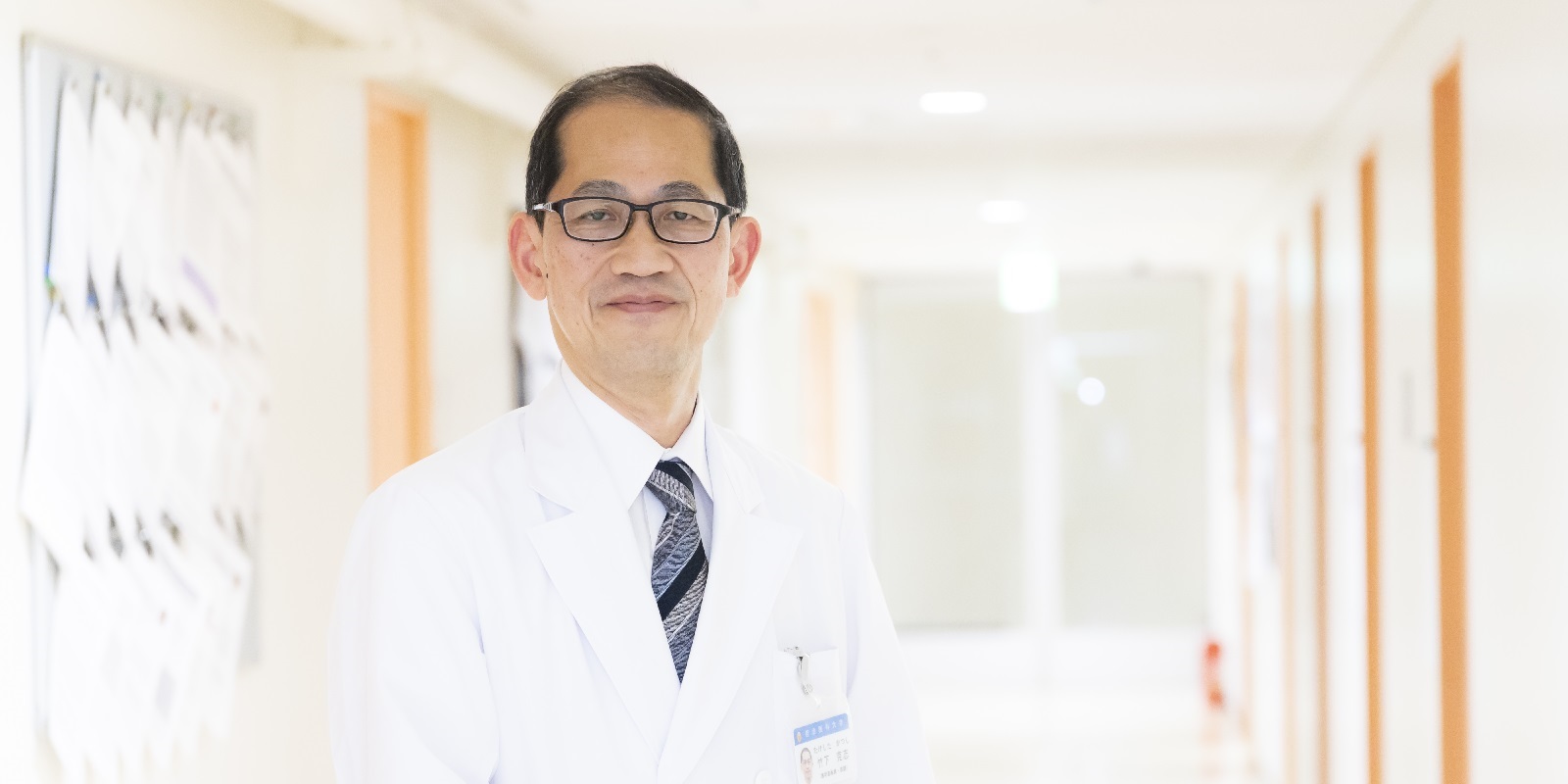
整形外科学講座
附属病院整形外科
教授竹下 克志
1987年、東京大学医学部卒業。同学部附属病院に入局し各地の関連病院で勤務。1999年以降、米国シンシナティ大学小児病院整形外科やワシントン大学整形外科のリサーチフェロー、東京大学医学部整形外科教授などを経て、2014年より現職。
研究内容
脊椎・脊髄の疾患(特に側湾症)や痛みに関する研究に長年取り組む。近年は予防の観点から、生活習慣病やロコモ(運動器症候群)についての啓発活動に力を注ぐ。
人間の姿勢や運動に関わる
すべてを研究と診療の対象とする
整形外科には、団体競技のチームに似た気質があります。外科系の全般にいえることではあるのですが、スポーツ整形を専門にする医師がいたり運動で故障した患者さんが多かったりする整形外科は特にその傾向が強く、集団で何かを成し遂げようという意識を共有していて雰囲気が明るいのです。BSLで来た5年生に得意なことや趣味について自己紹介してもらっているのも、短期間の実習とはいえ人となりを知ったうえでチームの一員として迎えたいからです。
整形外科は、運動器科ともいわれます。人間が姿勢を保ち体を動かすために必要な骨、筋肉、関節、靱帯、神経などの運動器官すべてを研究の対象とし、その疾病や外傷を年齢を問わず治療するからです。首や肩が痛い、背中に張りがある、腰が重いといった症状は、多くの人が経験しているのではないでしょうか。その際、鍼灸やマッサージへの通院、市販薬の使用で済ませてしまう人もいます。しかし背中や腰で感じる痛みの背後に病気が隠れていることもあり、実際に整形外科の診療でがんなどの重篤な疾患を見つけることも多々あります。
そのように痛みの原因となる病気を明らかにできるケースがある一方、原因を特定できない痛みも少なくありません。痛みを訴える患者さんは、医師に「どこも悪くない」と言われたところで納得も安心もできないのが現実。感覚と診断結果との差に、患者さんと医師とのギャップが生じます。そうした臨床現場で感じた溝を埋められればと考え、痛みに関する研究を脊椎・脊髄の臨床研究と並行させてきました。この研究の難しい点は、検査技術が進歩した現代でも、神経回路で伝わる痛み自体を探すことや痛みを客観データとして定量化できないこと。そのため、せめて患者さんが訴える痛みに医師が共感できるように開発した、主観的な痛さを評価する手法が今も臨床の現場で活用されています。痛みの研究はまだ途上なのです。高齢化に伴い整形外科の患者さんは増える半面、整形外科医の数は常に不足状態。自治医科大学の附属病院に限らず、全国の整形外科が若手医師の“チーム参加”を待ち望んでいます。

総合教育部門
文化人類学研究室
教授田中 大介
1995年、金沢大学経済学部卒業。三菱商事株式会社に6年間勤務した後、2001年に東京大学大学院総合文化研究科超域文化科学専攻に入学し、博士課程を修了。その後、早稲田大学や東京大学での教育研究を経て、2020年より現職。
研究内容
専門は文化人類学。主に国内のフィールドワークから各地の弔いやそれに関わる産業、看取り、ケアなどのあり方を通して、現代の死生観を文化という視点で探る。
地域医療は冒険と発見に満ちた
フィールドワーク
自治医科大学の総合教育部門は、医師を目指す学生が現代の医療に求められる倫理観や教養を高い水準で身につけることを目的としています。人文・社会科学や自然科学の知識を単に羅列するのではなく、医療の背景となる社会や文化のあり方、人間という存在の考え方や価値観について深くかつ多面的に考える力を養えるように、学際的な分野を含む多彩な科目を系統立てて構成しています。
文化人類学には医療人類学という分野もありますが、とりわけ私が専門とする「死」の問題は医療と不可分です。かつての医学は病気と戦うための学問という見方も強く、1分1秒でも患者さんを生き長らえさせることが「勝利」とする考え方もありました。それを全て否定できるわけではありませんが、一方でホスピスや緩和ケアが認知されてきた現代では、死と折り合いを付けることも医療の一側面となっています。克服が叶わない病気をいかに受け容れて死を迎えるか、生命を脅かす疾患でなくとも完治するまでは続く肉体的・精神的苦痛とどう付き合うか、その課題に直面する本人はもちろん、患者さんの家族や地域社会に、どのように寄り添えるかを現代の医師は問われます。地域に根ざした医療をミッションとして担う自治医科大学生には、臨床医学の知識や技術と同じくらい、地域の社会や文化を深く理解するための素養が求められるのです。
学生の出身は全国各地の都道府県にまたがっていますが、同じ県内であっても山一つ川一本を越えれば驚くほどの違いをみせる多様な文化が根付いています。そこに半ば“よそ者”として赴任しながら人びとの信頼を得ていく地域医療の実践は、文化人類学におけるフィールドワークに他なりません。文化とは空気に似ていて、普段は無意識にしている呼吸を止めたときに気付くようなもの。初めて訪れた地で空気の違いを感じるように、衝撃を受けることもあるでしょう。しかし、未知の文化に出会うことは、大きな喜びでもあります。それまで当たり前としてきた自らの文化的背景を深く見つめ、その土地ごとの多様な文化と人びとに出会う「地域医療の冒険」が、あなたの人生を変える驚きと発見にきっとつながるはずです。
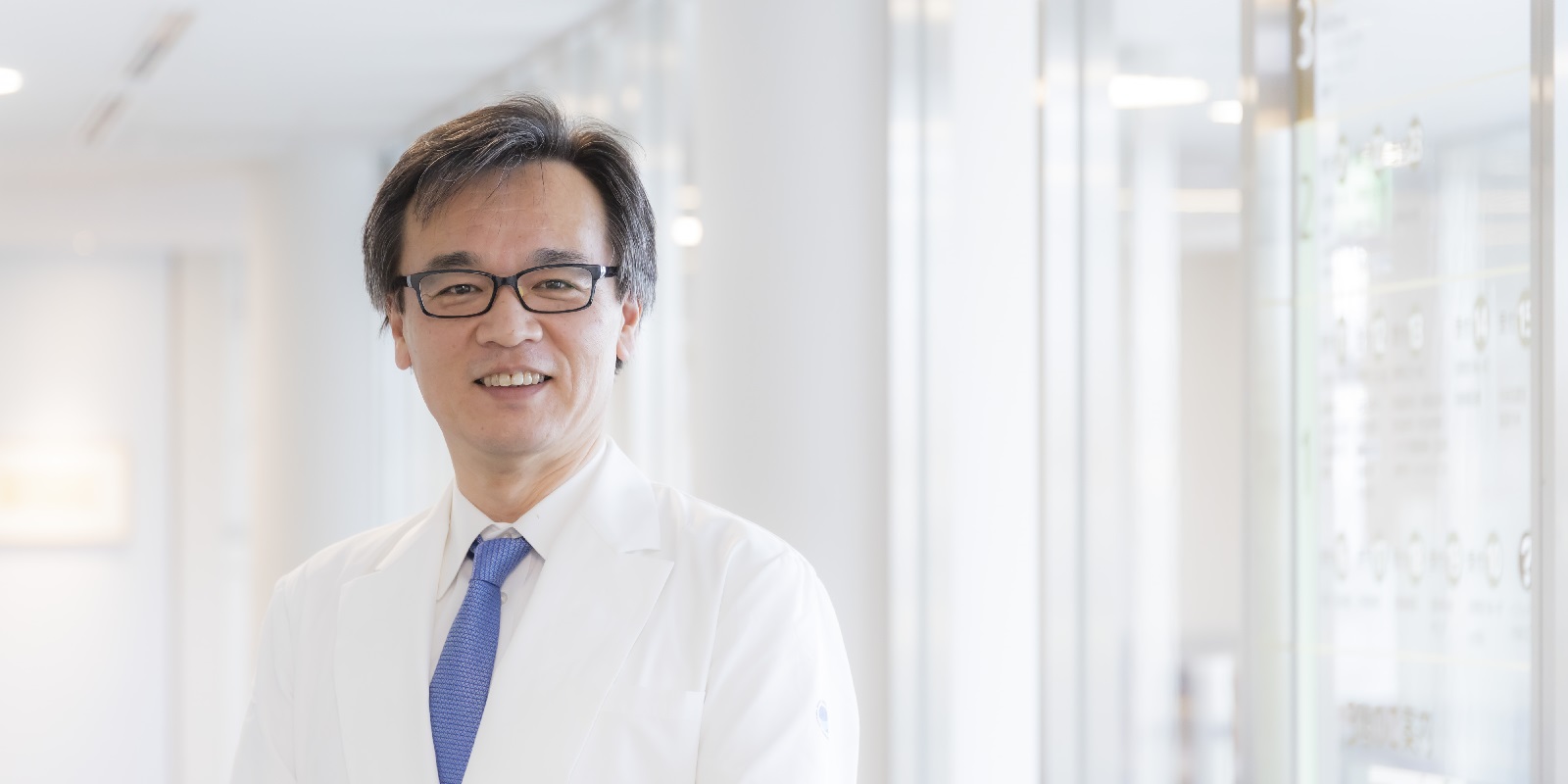
さいたま医療センター
総合医学第2講座
一般・消化器外科
教授野田 弘志
1992年、自治医科大学医学部卒業。佐賀県内で地域医療に従事した後、2001年から自治医科大学大学院で消化器癌の遺伝子発現異常を研究。2005年から同大学附属さいたま医療センターで消化器外科、肝胆膵外科を担当し、2022年より現職。
研究内容
消化器癌に対する手術成績の向上のため、術後に起こる合併症の予防に関する大規模前向き臨床試験の推進に取り組み、国際基準の作成を目指している。
目の前の診療に全力を注いだ先に
専門性を高める時期が訪れる
私は義務年限中に佐賀県内の地域医療に従事する傍ら、九州大学で胃癌の発生と進展の原因となる遺伝子異常の研究を行なう機会をいただきました。また、義務年限を終えて自治医科大学附属さいたま医療センターに戻ってからも、胃癌・大腸癌の手術と研究を行っていましたが、肝胆膵外科の前任者の異動に伴い、図らずも後任として診療を担当することになり、以来、消化器外科の中でも、特に肝臓、胆道、膵臓の外科を専門としています。
肝胆膵外科の手術は難易度が高く、手術時間も長い場合は10時間に及びます。しかも、いずれも生命維持に必要不可欠な臓器であるため、小さなミスが重大な結果につながりかねません。術後に合併症を起こすと予後が悪化し、患者さんはもちろん執刀した医師も大きなストレスを抱えます。手術自体は腹腔鏡手術の普及など技術革新が進んでいるにもかかわらず、術後の管理にはスタンダードが確立されていません。そこで、当科で行った術後創感染予防に関する1,000人規模の臨床試験のデータを提供し、欧州の施設と共同で研究を行っています。この研究結果が発表されれば、現在、世界で使用されているWHOやCDC(アメリカ疾病予防管理センター)の術後創感染予防ガイドラインを塗り替えることになると期待しています。そして今も、2本目の1,000人規模の術後創感染予防の臨床試験を進めています。
かつては肝胆膵外科の手術をすべて担当していた私も、今は若手の指導が中心となりました。BSLで来る自治医科大学の学生も、さいたま医療センターで研修中の若い医師も皆さん真面目で優秀です。私は肝胆膵外科学会の高度技能指導医など専門性の高い資格を持っていますが、先述の通り肝胆膵外科を専門にしたこと自体、偶然が重なったもので、資格取得はその結果に過ぎません。義務年限中の離島の一人診療所での経験は、医師としての成長の糧になり、思い出を超えた財産となりました。これからの医療を担う若い人にも、まず自分の足もとを見て目の前の患者さんの診療に集中してほしいと願っています。専門医や博士号などの取得は、日々の診療に全力を注いだ先に、必然的にその時期が訪れるものだと考えます。

附属病院救命救急センター 副センター長
救急医学講座
教授米川 力
1998年、自治医科大学医学部卒業。秋田県内で地域医療に従事し、義務年限終了後2007年に母校の救急医学に入局。医学博士、大規模災害の現場に駆けつけるDMAT隊員、救急医学の指導医などの学位・資格を取得し、2021年より現職。
研究内容
医療でのICT活用が研究テーマ。患者の様子と医師のアドバイスを画像や音声、文字でやり取りし、救急搬送時のほか、遠隔医療や災害地医療などへの応用も想定する。
地域医療での知識と経験を
救急医療に活かす
自治医科大学で学び地元に帰った卒業生の多くは、一般内科を主とする総合医として地域医療に従事します。学生時代は外科系の診療医や救急医に漠然と憧れを抱いていた私も、義務年限中は内科医として秋田県内の各地で勤務しました。そこでも急病への対応や、重症化する患者さんの集中管理は経験しました。へき地の診療所であれば、腹部や腰などが急に痛くなったという住民が、頻繁にやって来たり運び込まれたりします。そうした日常の医療を通して救急医療の知識や経験は自然と積み重なり、義務年限中に救急の専門医を取得できたことが、今に至る医師としての方向性を決めたといえます。
救急医療は、すべての医療の基本であると考えています。確かに薬物中毒や全身熱傷への対応などは、救命救急ならではの医療です。しかしその場合も、目的は目の前にいる患者さんの状態をより良くすること。そのための具体的処置には、気道を確保しての呼吸の管理や循環機能の管理などがあげられますが、それらはどの診療科でも同じです。みるみる状態が悪化していく患者さんを前にした医師に求められるのは、特定の臓器に限定した専門性ではありません。患者さんの全身を診ることであり、根底に求められるのは「人間が好き」というマインドです。その姿勢は地域医療に従事する総合診療医にも通じることを、救命救急センターにBSLで来た学生に繰り返し伝えています。
一人の患者さんにチームで対応するという点も、救急医療と地域医療で共通しています。どちらもチームの概念は広く、一つの医療機関の枠を越えています。救急医療では消防署に勤務する救急隊員はもちろん、消防署を管轄する行政、患者さんが帰宅できた場合は地域の病院や保健所、介護関係者などとの連携が欠かせません。多職種による安定した体制の構築と併せて、緊急時には患者さんの最も近くにいる人が医師のアドバイスに基づき即対応できるよう、迅速かつ的確な情報共有が必要です。そのため地域医療と救急医療での経験を踏まえ臨床と並行して、例えばスマートフォンのような身近なデバイスで画像や音声、文字情報をやり取りできるシステムやアプリケーションの開発に取り組んでいます。
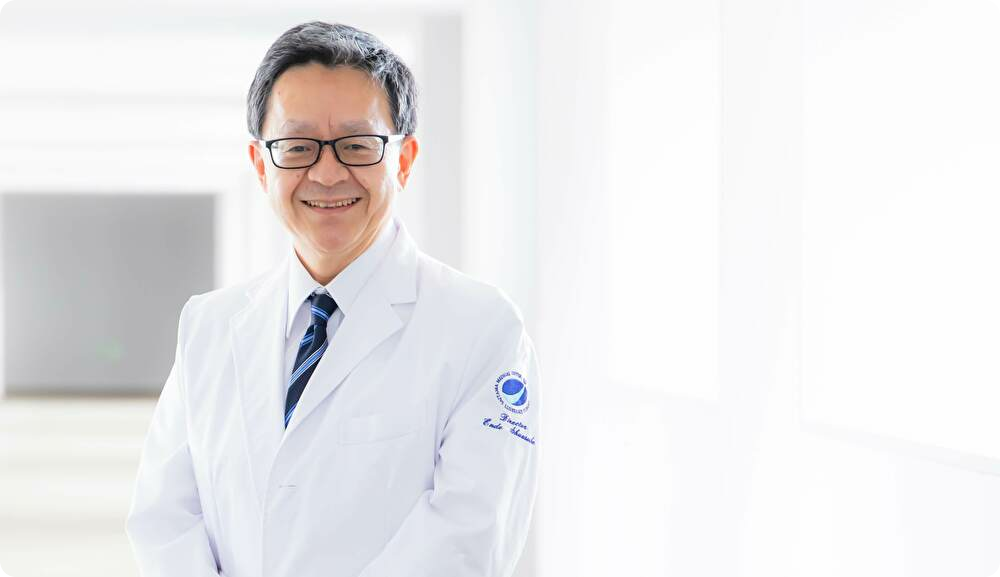
さいたま医療センター センター長
総合医学第2講座
教授(呼吸器外科)遠藤 俊輔
1984年、筑波大学医学部卒業。
筑波大学附属病院研修医、マギル大学(カナダ)実験医学研究部門研究員を経て、1992年に自治医科大学呼吸部外科学講座に。その後、同大学外科学講座主任教授・附属病院副院長などを経て、2020年より現職。
研究内容
早期に発見された肺がんに対する内視鏡を用いた手術で、全国有数の実績を持つ。
また、肺と心臓との血流に関する相互関係を研究テーマとする。
「専門の谷間」にも灯をともす
総合診療能力を身に付けてほしい
体中を巡り二酸化炭素を回収した血液は、各臓器の様子を写し取った状態で肺に集まります。そして二酸化炭素を放出し、生命活動のエネルギーとなる酸素を受け取って各臓器に運搬します。肺には全身の状態が現れ、肺の病気は全身に影響を与えます。「肺を制する者は全身を制する」といわれ、全身の疾患を知らなければ肺の病気を十分に治療できないこともあるのです。
私は呼吸器外科の医師として、がん患者の肺の切除や再建を行います。内視鏡や治療薬の進歩に伴い手術の成功率や患者さんの生存率は、かつてに比べて格段によくなりました。ただし、その背景には全身疾患を視野に肺の治療を考えることが重要です。もし肺だけを見て治療を進めた場合、肺の病気は治ったがその他の病気が悪化した、という事態を招くこともあり得ます。また、心臓の疾患や脳卒中、慢性関節リウマチなどの病気にかかると、それぞれの臓器だけでなく肺も傷むことがわかっています。肺が「全身を写す鏡」といわれるのは、そのためです。
現代の医学は診療科の分科が進み、しかもそれぞれが目覚ましい進歩を遂げています。その結果、医師は専門とする診療科のことで手一杯になりがちで、他の分野について関心を示すことができないこともあります。ところが現実には、専門診療科の領域を超えた病気が増えてきました。そうした患者さんを救うためには、いずれかの診療科に属しても総合的な見地で患者さんと向き合うことが必要です。診断においても検査部門から提供される画像だけに頼ることなく、例えば患者さんの顔色や息づかいをよく観察することで多くの情報を得られます。
複数の病気にかかっている患者さんの数は、高齢化により今後さらに増えることでしょう。自治医大の学生は卒業後、それぞれの出身地でそうした患者さんに医療を提供します。「地域医療の谷間に灯をともす」医師を育てることが本学における教育の目的ですが、それと併せて学生には「専門医療の谷間に灯をともす」知識と志をもって、地域医療に尽くすことができるような能力を身に付けてほしいと願っています。

分子病態治療研究センター
循環病態・代謝学研究部
附属病院循環器センター内科部門
教授武田 憲彦
1996年、東京大学医学部卒業。
2005年、東京大学大学院医学系研究科博士課程修了。カルフォルニア大学サンディエゴ校生命科学分子生物学分野リサーチフェロー、東京大学医学部附属病院特任講師などを経て、2020年より現職。
研究内容
体内の低酸素状態に適応する生命維持システムにおいて、これを司るHIFという遺伝子の働きと心血管病の関係を明らかにし、心血管病の治療を目指す。
低酸素で働く細胞に着目し
心血管病の原因を解明する
酸素は生命活動を維持するエネルギーとなり、生きていくために不可欠です。一方で体内には、酸素が欠乏した状態で働きが活性化する細胞やシステムも存在します。私たちの研究は、そうした低酸素の環境で活性化する細胞や生命システムと、その働きを導く遺伝子を対象としています。
生命の維持に必要な酸素は、血液によって全身に運ばれます。ところが心筋梗塞や心不全などの心血管病にかかると血流が阻害され、酸欠状態となった臓器や細胞は機能が低下します。このような心臓の病気に対して、これまでは心臓の主な働きをする心筋細胞の研究と治療に多くの目が向けられてきました。心筋細胞は心臓における、いわば中心プレーヤー。実際に心筋細胞に対する治療は一定の効果を上げています。ところが、同じ治療が効果を発揮しないケースもあります。実は心臓には心筋細胞のほかに、線維芽細胞や炎症細胞といったサブプレーヤーも働いています。これらが低酸素状態で活性化する細胞であり、心臓が機能する上で重要な役割を果たしていることがわかってきました。しかし、それらの細胞に着目した心血管病の研究は、ほとんど手が付けられていないのが現状です。そこで私たちは低酸素状態で活性化する細胞とその働きを導く遺伝子に焦点を当て、酸素を切り口とした心血管病の研究を進めるとともに、治療法の開発につなげる基礎研究に取り組んでいます。
私が自治医科大学に着任したのは、2020年4月です。着任して早々に驚いたことは、教員や職員が在学生や卒業生の個人名を挙げて、それぞれが取り組む学修の進度や出身地での医療活動について会話を交わしていることでした。それぞれが所属する診療科や部局にとらわれないやり取りに、学生や卒業生を最優先に考える自治医大のDNAを感じました。現代医学の基礎研究は生命科学や医療工学などの知見を積極的に取り組み、その成果を臨床の現場に提供します。私たちの研究も、それぞれの出身地で地域医療に従事しながら自身のアップデートを図る卒業生に役立ててもらいたく、また基礎研究に興味を持った在学生には、研究室の見学や研究活動の参加を呼びかけたいと考えています。
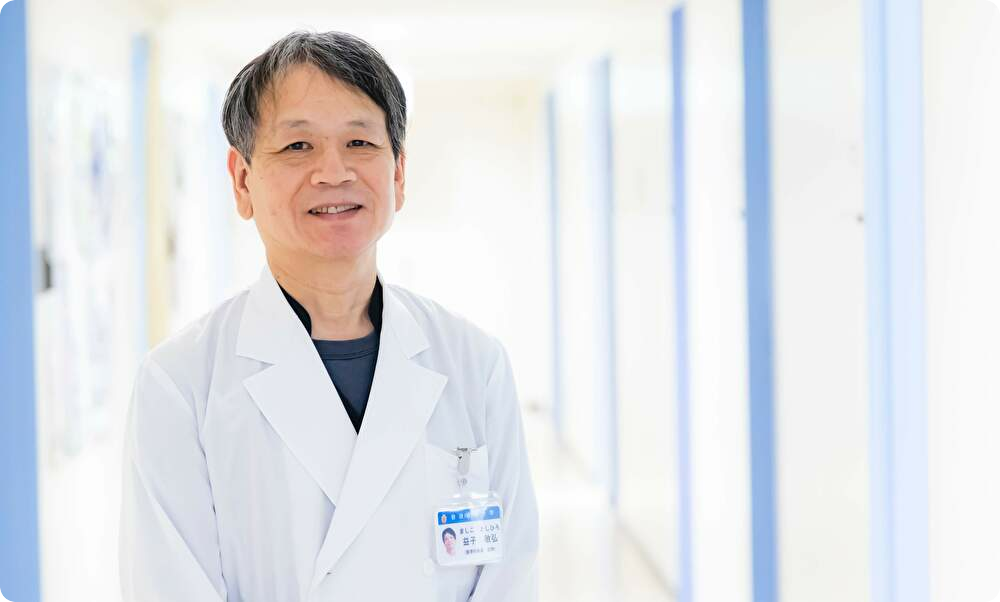
脳神経外科講座
附属病院脳神経センター外科部門
教授益子 敏弘
1985年、自治医科大学医学部卒業。
栃木県内で地域医療に従事し義務年限終了後、1995年に自治医科大学脳神経外科に入局。脳神経外科の専門医を取得し、2003年にアメリカのアルベルト・アインシュタイン医科大学に留学。2020年に現職。
研究内容
附属病院における脳神経外科の診療と併せて、脳神経外科の手術シミュレーションと教育を研究。
手術患者の3Dモデルの開発・製造で特許を取得している。
全国の臨床と教育現場で活用される
脳外科手術の3Dモデルを開発
本学附属病院の脳神経外科で、外来と病棟の患者さんを診ています。専門は脳血管障害としていますが、実際の診療からは脳神経外科の総合医といえると思います。本診療科では年間に約500件の手術を行います。内視鏡やカテーテルによる治療はこの分野でも進歩が著しく、かつてに比べれば患者さんの負担は軽減されました。それでも脳の病気は生命に直結するケースや緊急性を要する病状が多く、診療には確かな知識と技術、積み重ねた経験が求められます。そのため後進の指導も脳神経外科の重要な課題であり、私は脳神経外科手術のシミュレーションと研究を研究課題としています。手術患者の3Dモデルを開発・作製したのは十数年前のことでした。その後改良を重ね、今では若手医師の教育、手術前の検討と練習などに活用されています。また、患者さんや家族に対して事前に手術を説明する際にも用いられており、脳神経外科におけるインフォームドコンセントの推進にも貢献できています。もちろん、医師を目指す学生への指導にも用いられています。
私が自治医大を卒業してから、三十数年が経ちました。教育のための施設や設備はあの頃から格段に進歩し、学びの環境を充実させています。講義や実習を担当し、ハンドボール部の顧問でもあり、さらに2021年度からフリーコース・ステューデントドクター制度のメンターも務める私は、脳神経外科の中では最も学生と接する機会が多い医師だと思います。指導者として、あるいは本学の先輩として今の学生と交流すると、私が学生だった頃と比べて真面目であり勉強熱心であることがうかがえます。一方で「医療の谷間に灯をともす」という設立趣旨と教育理念が明確な自治医大に入学してきた若者の本質は、時代を経ても変わっていないと感じています。脳は未解明な点が多く、現代の医学では治すことができない病気があるのが現実です。しかし治療により助けられる患者さんと助けられない患者さんのどちらに対しても、自身が持つ知識と技術で最善を尽くせる医師になってほしいと、キャンパスでの交流を通じて学生に繰り返し伝えています。

小児科学講座 小児医学部門
とちぎ子ども医療センター 小児科
教授熊谷 秀規
1991年、自治医科大学医学部卒業。。
岩手県内で地域医療に従事し、義務年限終了後はもりおかこども病院(当時)、岩手医科大学を経て、常陸大宮済生会病院の小児科部長に就任。2012年に自治医科大学小児科学講座の講師となり、2019年から現職。
研究内容
小児科学の中でも小児消化器病学を専門とする。
研究テーマのひとつに、小児期の腸内細菌叢の形成、腸管粘膜免疫の発達、および消化管と脳機能の相関関係がある。
未開拓の領域が広く
探究心が刺激される小児科学
小児科は、子どもを対象とする総合診療科です。学生時代からこの分野に関心を持った私は、出身地・岩手県での義務年限履行中も、小児科での勤務を希望しました。幸い県の配慮があって配属された医療機関では大なり小なり子どもを診る機会を得られたので、教室では学ぶことが難しい子どもとのコミュニケーションや親との接し方、”子どもファースト”の医療について、貴重な経験と学びを得ることができました。小児科のない病院では内科に所属しましたが、そこで獲得した成人患者を対象としたスキルを子ども向けに応用し、小児科の診療に活用することもできました。消化管内視鏡検査もその一つ。今では広く行われるようになった子どもへの内視鏡検査に、全国でも早い段階で取り組めたことになります。実は「暗黒の臓器」といわれる小腸の内視鏡検査を可能にした技術は、自治医科大学の卒業生が開発しました。これを継承する後進の一人に加われたことに、私は誇りに思っています。
小児科学の基礎研究に取り組むようになったのも義務年限中のことです。無菌状態で生まれてきた赤ちゃんの腸内に細菌叢が形成される過程や、形成に伴う腸内粘膜免疫の発達は、当時から取り組み今も続く研究テーマとなりました。また、腸と脳との相関関係にも関心を持っています。強いストレスを感じるとお腹の具合が悪くなり、悪化させると潰瘍になるなど、多くの人が腸と脳の状態が影響し合うことを体験的に知っていると思います。腸の細菌叢と、自閉スペクトラム症や肥満との関係も研究が進んでおり、「脳腸相関」と呼ばれる分野の研究も継続したいと思います。
少子化が進む現代、小児科は、開業して儲けようと考えている人には勧められる診療科ではないかもしれません。しかし小児科学の領域には、治療法どころか発症のメカニズムさえ明らかにされていない病気が数多く残されており、医科学への探究心を刺激するテーマに満ちています。何より生まれてきた赤ちゃんが成人になるまでの成長過程に、医師として長期間寄り添えることは、他の診療科にはない喜びになると確信しています。
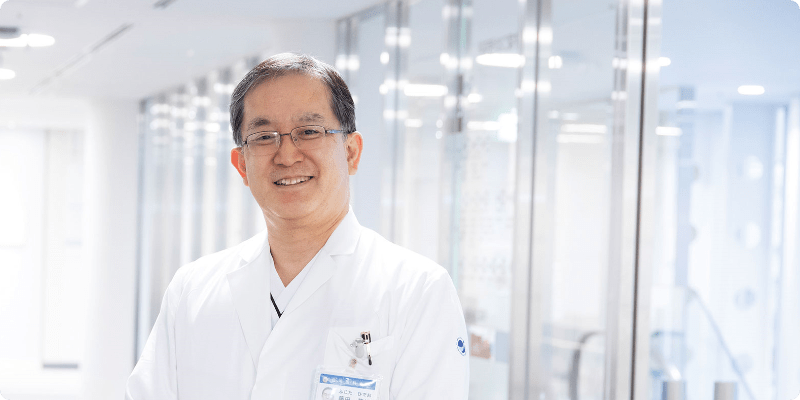
さいたま医療センター副センター長
総合医学第1講座
主任教授(循環器内科)藤田 英雄
1989年、東京大学医学部卒業。
1997年、同大学大学院医学系研究科を修了し医学博士に。2000年、北里大学医学部助手・救命救急センター診療講師などを経て、2014年に自治医科大学附属さいたま医療センター循環器内科教授に。2019年より現職。
研究内容
心臓カテーテル治療、および救命救急における心電図伝送システムの開発をはじめ、
臨床医療へのICTの活用、ビッグデータ
カテーテル治療とI C T 活用の
可能性を若い世代と広げたい
循環器内科に目覚めた時の、学生時代の衝撃は今も忘れていません。臨床実習の現場に運び込まれてきた心筋梗塞の患者さんは、顔面蒼白の状態。学生である私の目には、もう助からないと写りました。ところがカテーテル治療を施すと、その最中から顔色に赤みが差し、わずかな入院の後に自身の足で歩いて退院していったのです。生死の瀬戸際にあった患者さんを救った医学の力を目の当たりにし、以来、心臓カテーテルによる治療は、私にとって臨床における最大のテーマとなりました。
カテーテルは血管に挿入する導管。これを体内の患部まで導いた上で管内部にワイヤを通し、心筋梗塞や血栓に対しては、先端に付けたステントという金属製の網でふさがった血管を広げる、といった治療をします。開胸手術が不要なため患者さんの負担は軽減されますが、かつては職人技として捉えられていました。しかし今では材料を含めてデバイスとしてのカテーテルの進歩を含めて、治療法も確立され、予後も飛躍的に向上しました。しかも弁膜症の患者さんに人工弁を入れたり、かつては薬で抑えこむしかなかった不整脈の患部を焼いて治療したりと、カテーテル治療を適用できる疾患も増えています。
附属さいたま医療センターは、カテーテル治療で全国屈指の実績を誇ります。学生や若い医師には、この充実した環境で循環器を含めて総合医療を学んでほしいと考えています。循環器系の疾患は緊急を要し、生命に関わるケースが多く、医療設備が整わない地域で総合医療を提供する医師もカテーテル治療を理解していれば、診断後の治療に迷うことなく患者さんを中核病院に送ることを即決即断できるからです。
1分1秒を争う局面で威力を発揮する、臨床へのICT活用も私の研究テーマです。開発に携わった心電図の伝送システムは、搬送中の救急車内で取得したクラウドサーバーにアップした心電図を複数の医療人が同時に共有して、診断と搬送先の決定と病院前の治療を準備するもの。全国の救命救急の現場ですでに活用され始めていますが、ビッグデータ・AIとともにさらなる発展も必要であり、特にこうした分野では、ICTを当たり前として育ってきた若い世代に期待しています。
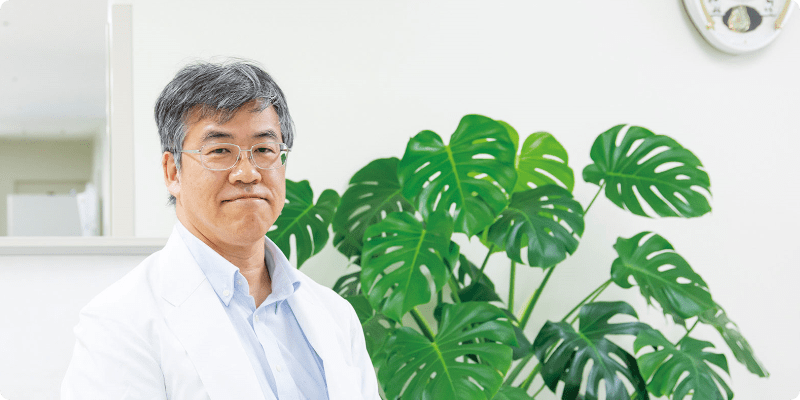
救命救急センター センター長
救急医学講座
教授間藤 卓
1987年、新潟大学医学部卒業。東京大学医学部附属病院での内科研修医、リウマチ・アレルギー内科医師、救急部助手などを経て、2009年、埼玉医科大学総合医療センター高度救命救急センター准教授に。2016年より現職。
研究内容
栄養チューブを安全に挿入するための医療機器や、地元の農産物や食品を使った医療用教育機器の開発
かんぴょうを医療に転用した問題意識と注意深い視点
救命救急センターは、医療ドラマの舞台として映画やテレビにも数多く登場します。次々に搬送されてくる重症の急患に私事を捨てて不眠不休で対応し、奇跡のような医術で命を救うスーパーマンのような主人公と、脇を固める個性派の医師たち…。センター長である私が目指すことの一つには、救命救急センターが超人集団であるという、医療界にも根強いイメージを払拭し定着させることにあります。名付けて「ゆる救」のすすめ。医師にも当然、人生や生活があります。それらの犠牲を常に強いられていたのでは、救急救命体制の維持・継続は叶いません。救命救急センターが“普通の医師”にとって働きがいのある職場であり、ドラマで見るような超人的な医師が不在であっても、安定した医療を提供できるチームにしたいと考えています。
一方で救急救命の現場には、臨床研究に直結する課題があふれています。出産や臨終、生死の境をさまようような状態の時、生き物は生命の本質をあらわし、日常の感覚では不思議や神秘と思える現象を起こすことがあります。もともとは基礎研究の道に進もうと考えていた私が、縁あって救命救急に関わったのを機に現在に至るのは、そこに研究の種となる出来事があふれているからです。とはいえ、当たり前と思える風景にも注意深く意識的な視線を向けなければ、せっかくの種を見過ごしてしまいます。解決したい課題を常に蓄えておくことも必要です。メディアで大きく取り上げられた、地元産のかんぴょうを用いた縫合シミュレーターの開発も、縫合の手技を習得するための安価なトレーニング機器がないという教育現場の課題をあらかじめ意識していたからにほかなりません。
患者さんから診断や治療法の選択につながる多くの情報を取得できるのは、臨床経験を積んだ医師だと思います。しかし、ベテラン医師が当たり前と見過ごしてしまうようなことに疑問をはさむ初々しい感覚は、若い人のほうが勝るはず。医療の発展に貢献できる種は、目の前にいくらでもあるのです。
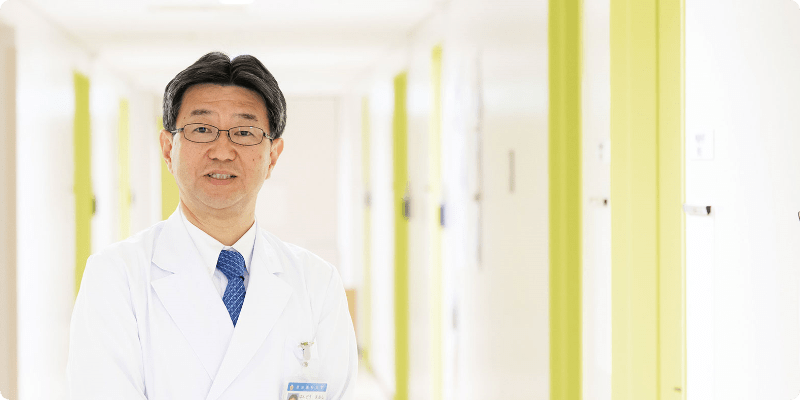
臨床研究支援センター
内科学講座(呼吸器内科学部門)
教授坂東 政司
1989年、自治医科大学医学部卒業。徳島県内で地域医療に従事した後、1995年米国イリノイ大学シカゴ校留学、2006年、自治医科大学呼吸器内科准教授、2009年、附属病院卒後臨床研修センター長、2016年、医薬品医療機器総合機構(PMDA)などを経て、2018年より現職。
研究内容
全国の卒業生や附属病院の医師・医療従事者に向けて臨床研究の支援と推進を担当。
自身は間質性肺炎などの呼吸器難病に関する臨床研究を継続
日本の未来を先取りするへき地・地域医療における
疑問・課題を臨床研究により解決する
今から20年も前、郷里の徳島県でへき地医療に従事していた頃の話です。当時すでに高齢化率が40%を超える山村の診療所に一人医師として勤務していた時でした。呼吸不全の患者さんに対し在宅酸素療法を施していた私は、在宅医療の原点といえるこの治療法が、へき地の現場で当時どれくらい行われているのかを知りたくなり、アンケート調査を実施しました。四国の山中から発した問いに、全国から回答が寄せられました。卒業生が全国各地で地域医療に取り組む自治医大ならではのネットワークがあってこその調査研究であり、その連携・支援体制は現在私が取り組む臨床研究支援システムの価値ある資源として広く活用されています。
臨床研究は、毎日の診療の中で生まれた疑問から発します。私にとってその第一歩は、症例報告の作成でした。医師が記す体験記録のようなもので、考察には先行する臨床研究のデータを用います。大学院在籍中に基礎研究に従事していたこともあり、その後私もデータを提供する側に立ちたいと思うようになりました。それが、臨床研究を意識して医療に取り組むようになったきっかけといえます。臨床研究は、一人の患者さんや一つの症例から発見した疑問や課題とその解決法に科学的根拠(エビデンス)を与えます。その点で私は、臨床研究には、真実を深く追究するサイエンス(医の科学)と人間を対象としたアート(医の心)が共存しているように感じています。
私は「ピンチと思うな、チャンスと思え」という言葉を好んで使います。これは知人であるプロ野球選手から教えられたフレーズで、地域医療にも当てはまります。専門性を高めたい医師にとって、へき地で医療に従事することは「ピンチ」と感じるかもしれません。しかし超少子超高齢化や人口減少が進むへき地は、未来の日本の姿。そこで取り組む医療とは、この国に求められる未来の医療を先取りする「チャンス」であり、地域医療から発信する臨床研究には、これからの医療を物語る価値があると考えています。
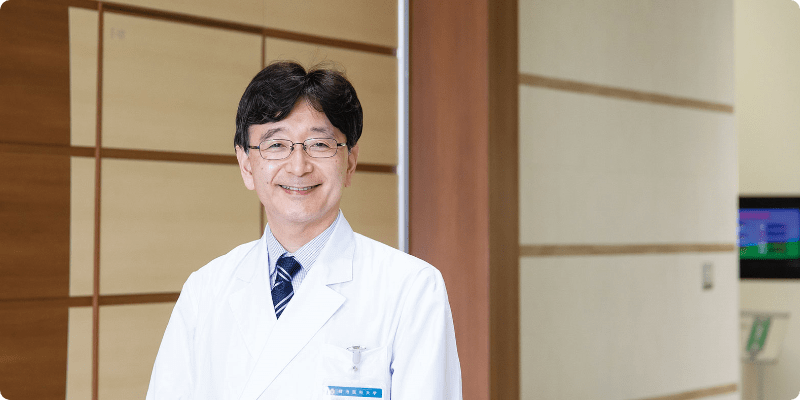
医療の質向上・安全推進センター センター長 内科学講座(循環器内科学部門)
教授新保 昌久
1991年、自治医科大学医学部卒業。栃木県内で地域医療に従事。義務年限を終了して以降は、自治医科大学救急医学講座助手、同大学内科学講座循環器内科学部門講師・准教授、同大学附属病院卒後臨床研修センター長などを経て、2017年より現職。
研究内容
臨床では動脈硬化症を中心に患者の予後に関する新規バイオマーカーなどの調査研究。
並行して医療の質的向上、安全性・信頼性の維持・改善に関する調査分析
基礎研究と臨床をつなげ新たな治療法に応用する
自治医大で学んだ大半の医師と同じく、私も義務年限中の関心は臨床に向いていました。へき地医療に従事する傍ら基礎研究に取り組んだのは、科学的・論理的思考への興味と、新たな視点も大切との先輩医師からのアドバイスによるものです。
とはいえ当時は、将来にわたり基礎研究を続けるつもりはありませんでした。自治医大の大学院で遺伝子を導入して血管を新生する研究に力を注いだのも、地域医療に取り組む中で多くの患者さんがいた心臓や血管の疾病に対する効果的な治療法を見いだしたかったため。その思いも、先輩医師が体現する「循環器の急変は、絶対に救わなければいけない」という厳しい診療姿勢に感化されたものです。しかしその後、留学先のハーバード大学で基礎研究と臨床を橋渡しするトランスレーショナル・リサーチを学び、研究と診療を両立させることの意義を理解しました。以後今日まで、臨床と研究の双方を大切にしています。循環器内科医としてキャリアを重ねた今は、後進の育成が最重要課題。学生や若手の医師に向けて強調していることは、エビデンスに基づき可能性と限界を十分に理解した医療を提供することと、その医療を患者さんと家族が納得し受け入れられるようコミュニケーションを徹底することの大切さです。これらは私自身が地域医療を通して得た実感であり、現在センター長を務める医療の質向上・安全推進センターのテーマでもあります。
同センターが追求する「医療の質と安全」は、医師を含めた医療チームが科学的根拠と十分な技能に基づく医療を提供することで、患者さんとその家族、さらにそれを取り巻く社会との間で信頼関係を築くことによって成り立ちます。特に自治医大生が卒業後に取り組む地域医療では、地域が持つ医療資源を最大限活用して安定した医療を提供するために、現場で接する全ての人と結ぶ信頼関係が前提となります。そうした意識を早い段階で養えるよう、同センターは3年生には医療安全に関する講義を、4年生にはBSL直前の実習を担当しています。将来、患者さんを第一に考えた安全な医療を提供するために、プロフェッショナルとして大切なことは何か、学生の間にぜひ理解してほしいと思います。
