
医学部
School of Medicine



学生VOICE
医学部1年

野尻 悠喜 さん
大分県
大分県立大分豊府高等学校
出身
全国47都道府県から集う仲間たちと
心強い先生や先輩方が大きな支えに。
医学部2年

久保田 夏央 さん
静岡県
静岡県立静岡高等学校
出身
友人と先輩方に日々支えてもらいながら
基礎医学の知識を段階的に深めています。
高校時代に甲状腺の病気を患い不安を抱いていた私に、親身に寄り添ってくれた地元医師に憧れたのをきっかけに、生まれ育った地元で多くの人に適切な医療と安心を届けたいと考え医師を志しました。自治医科大学では1年次から附属病院の患者さんに付き添う早期体験実習や、人体の構造と機能への理解を促進する解剖学などにより実践的な学びが得られるため、医学生としての自覚が高まることを実感しています。2年次からは基礎臨床系統講義が始まり、基礎医学の知識を段階的に深めることになるので楽しみにしています。学習は大変ですが、ラウンジで共に勉強する友人から日々励みをもらい、部活や学園祭実行委員会の先輩方に多くの教えをいただきながら充実した寮生活を送っています。
医学部3年

樫原 愛実 さん
徳島県
徳島県立城ノ内高等学校
出身
勉強と部活を両立させながら
新しいことに挑戦していきたい。
高3の受験期まで医学部を目指すか悩んでいましたが、周りに体調を崩している家族や友人がいても何の力にもなれないのが悔しく、そんな自分を変えたいと思ったのが医師を志したきっかけです。地域に寄り添うことができる総合医の育成に力を入れていることや、病棟実習が早期から始まるため実際の臨床現場で座学の学びを活かせること、さらに学費がなくて全寮制という点に魅力を感じて自治医科大学を志望しました。3年次は1年間で数多くの基礎臨床系統講義をこなす必要があり、さらに試験も多いのが特徴です。部活ではバドミントン部とフォークソング部(JFC)に所属していますので今後も勉強と部活の両立を目指していきたいです。
医学部4年

川上 紗和 さん
兵庫県
甲南女子高等学校
出身
実体験から得られる学びを大切にしながら
卒業後のキャリアを具体化していきます。
アフリカのへき地で医療活動に従事する日本人医師に憧れを抱いたことがきっかけで、国内においても医療が不足する地域があることを知り、地域医療におけるトップクラスの教育環境を備えた自治医科大学に入学しました。3年次までに培った医学知識を基盤に、4年次からは約2年間に渡るBSLがはじまり、2週間のローテートで各診療科の実務を経験します。教科書通りにはいかない難しさを体感しながらも、患者さん一人一人の人生に寄り添う姿勢を大切に、卒業後のキャリア設計を具体化することが当面の目標です。また現在私は柔道部の主将を務めており、大会で優勝するべく日々稽古に注力しています。部活も勉強も妥協せず、今後も自分らしく大学生活を楽しみます。
医学部5年
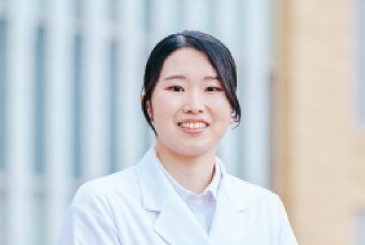
遠藤 奈々 さん
鳥取県
鳥取県立鳥取西高等学校
出身
臨床実習期間が長く充実していて、
全国に友人ができるのが魅力です。
自治医科大学を志望した理由は、将来的に地元で医師として貢献したいと考えたからです。地域医療教育に力を入れていることや臨床実習期間が長いこと、医師国家試験の合格率の高さ、各都道府県から学生が集まる寮生活にも魅力を感じました。また学費など経済的な負担が少ないのも理由の一つです。4年次のBSLでは内科系の各診療科をまわり、5年次では外科系や小児科、産科婦人科などの診療科をまわります。有意義な学びになるよう病棟実習に取り組んでいきたいです。医療の発展とともに治療法の選択肢は増えていますが、根治できない病気を抱えている方も多くいます。ご家族の思い、患者さんの希望する生活に配慮し、気持ちに寄り添える医師を目指しています。
医学部6年

早坂 健杜 さん
神奈川県
聖光学院高等学校
出身
多方面から地域医療への理解を深め
地域に根ざした総合医になりたい。
へき地診療所で医師として地域に溶け込み働く父の姿に憧れ、自然と自らも地域医療に携わりたいと考えるようになりました。これまでの学びは全て有意義なものでしたが、その中でも特に5年次のCBCLは自身の将来の姿を想像する上で大いに役立ちました。6年次の約半年間は自分で自由に実習を組み立てるFCSD制度を利用し、医療機関だけではなく行政や公衆衛生などの多方面から俯瞰的に地域医療への理解を深める予定です。また地域に疑問を見つけて研究に落とし込み、その成果を地域に還元する医師を目指すため、学生のうちに論文執筆を経験しておくことも目標の一つ。それらの経験を糧に医師国家試験に確実に合格し、地域に根ざした総合医を目指します。
