
医学部
School of Medicine




「第3回やぶ医者大賞」を受賞して
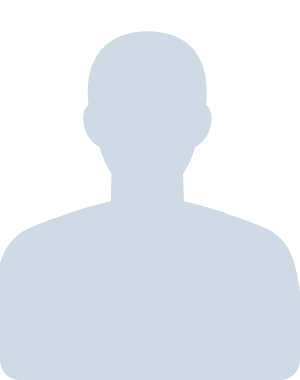
永源寺診療所(滋賀18期)
花戸貴司 滋賀県
この度、兵庫県養父市が3年前に創設された「やぶ医者大賞」に選出いただきました。同窓会事務局より受賞挨拶の原稿依頼がありましたので、表彰式当日のスピーチの内容をここに掲載させていただき、受賞挨拶とさせていただきます。
本日は、このような機会をいただき、養父市長さまをはじめ関係者の皆様には、感謝申し上げます。私が中学3年生のとき、父が亡くなりました。肝臓がんでした。それを機に医師を志すのですが、恥ずかしさもあり母には詳しいことは語らず「やりたいことがある」としか伝えていませんでした。そして、進んだ医学部で、一緒に勉強をしたのが、今日、同席している藤原先生です。
医師になり、永源寺診療所に赴任したのが、卒業して6年目のことでした。診療所に来てはじめて、往診をしていた患者さんことを今でも忘れることができません。紳悟さん、60歳の男性の方でした。脊髄小脳変性症という難病を患い、私が赴任する前から奥さんと家族の方が献身的に介護をされていました。病状は徐々に進行していましたが、私が主治医になった一か月後、とうとうご飯が食べられなくなりました。当時、永源寺という田舎にも最高の医療を届けよう、そう思っていた私は、毎日点滴をし、血液検査の結果をみては薬を追加していました。往診でも、しっかりと病気を診よう、そんなことばかり考えていたように思います。
そして、私が患者さんのもとで点滴をしようとしていたとき、後ろから、奥さんがポツリとつぶやかれたのです。「先生、もうあかんな」 自分が一生懸命治療をしようとしているのに、「もうあかんな」とは何を言うか!と半ば怒り気味に、後ろにいる奥さんの方を振り返りました。すると、奥さん、家族、親戚、近所の人たちがとりかこんで、患者さんをじっと見ておられたのです。このとき、自分はこの場にふさわしくない人間なのではないか、と感じたのです。患者さんの「病気」しか見ていなかったのです。目の前の患者さんが最期の時を迎えようとしている、周りの皆さんは、人生の幕を閉じようとしている「その人」を見ていたにもかかわらず、私は「病気」しか見ていなかった。その2日後、紳悟さんは家で息をひきとられました。奥さんから「ありがとうございました」と頭を下げられる一方で、自分自身の医師としての無力感だけが残りました。「このままではいけない、自分が変わらなければならない」心の中で、そう繰り返しました。
医学部で勉強している頃、いろんな科に興味を持ちました。手術ができる「外科」、スポーツドクターもできる「整形外科」、知識が豊富な「内科」など。そして大学を卒業する前に、私が最終的に選んだのは、「小児科」でした。病気に苦しむ子どもたちのために働きたい、そう思いました。医師になり、大学病院での研修は忙しかったのですが、やりがいもあり、とても充実し、子ども達との時間も楽しかったことを覚えています。この頃は、難しい病気を診断し治療することこそが、医師の仕事と信じて疑いませんでした。もちろん、自分の周りにもそんな立派な医師ばかりでした。
そして、3年目からは、滋賀県の北部にある総合病院に赴任しました。そこに小児科医は、定年間近の副院長先生と私の二人しかおらず、夜間や休日の呼び出しも私が全て対応していました。「24時間365日ここの小児科は俺に任せろ」そんな気概をもって働いていました。重症の患者さんが入院すれば病院に泊まり込み、家に帰らないこともしばしば。家族にも迷惑をかけたと思います。今から思うと、まさに肩で風を切るような医者でした。このときは、たくさんの病気を診ることがとても楽しく、また、それを治療することに充実感を覚えた時期でもありました。
そして今から17年前、診療所に赴任することになります。診療所に赴任して時間の流れが変わりました。子どもだけでなく、お年寄りを診る機会も増え、病院勤務時代には少なかった病気以外の話をすることも多くなりました。話を聴いてもらえるだけで、満足して帰ってくお年寄りたちの後ろ姿を見ながら最初は戸惑いました。「この人たちは、何のために診療所に来ているのか? 治療するために来ているのではないのか?」と。やはり「病気」しか診ていなかったのです。しかし、病気だけではなく、「その人の人生を最期までみとどけよう」、地域の人たちの思いを叶えるために「自分自身が変わろう」、そう思うようになると、たくさんの話を聴くようになりました。
最近では、患者さんと病気の話以外にも、生活のこと、仕事のこと、家族のこと、そして、これからの人生のことなどを話すようになりました。これからの人生のこととは、ご飯が食べられなくなった時のこと、自分の人生の最終章をどのように迎えたいか、そんなことを話すことができるようになりました。外来に受診したおばあちゃんに、「ご飯が食べられへんようになったら、どうする?」と私が尋ねると、おばあちゃんは笑いながら、「やっぱ最期まで、先生に診てもらいたいわ」と返されます。私は、「お迎えが来そうになったら教えてあげるから、それまでは畑をがんばりや」…と、そして「もし、本当にご飯が食べられなくなったら、私が往診して、最期まで診させていただきます」そう約束することができるようになりました。今流行りのエンディングノートを書けなくても、ご自身の人生の最終章をどのように迎えたいか、こちらから尋ねると、皆さん、真剣に、そして思慮深く語ってくれます。死を語り合うことは決してタブーではない。本人の希望を叶えるため、いざというときに家族が迷うことがないように必要な対話である、そう確信を持ちました。
診療所に赴任してしばらく経った頃、医師官舎の裏庭に、朝、畑で採れたばかりの野菜が置いてありました。患者さんからの届け物らしいのですが、誰が置いたのかわからない。名を名乗らぬ贈りものに、感謝の気持ちが伝わってきたことを覚えています。地域の人に、自分の存在を認めてもらえた、という嬉しさがこみあげてきました。永源寺に来て、いろんなことを地域の皆さんに教えてもらいました。地域のつながりや互いをおもいやる気持ち、そして何より私自身が地域の人たちに支えられていると、感じることがたくさんあります。ですので、私自身がやるべきことは、物をもらった人に何かを返すということではなく、自分がこの地域のために何ができるかということを、自ずと考えるようになりました。
自分が、この地域でできることは何かと考えた時、地域で医療を行なうということだけではない、医療を通じた「まちづくり」ではないかと思います。せっかくその地域に住むなら、自分にできることをその地域に還元したい、地域の人たちの笑顔をもっと見てみたいと思います。結果として、障がいを持った人も認知症の高齢者も子どもも、皆が互いにおもいやり、支えあい安心して生活できる地域になればと思います。
医師を志し、まもなく30年が経ちます。私が抱いていた「やりたいこと」というのは、間違っていなかった。今、母に伝えます。大病院ではできないことも、地域ならできることがある、そう信じています。このたび、このような名誉ある賞をいただけたのも、永源寺地域の皆さまのおかげと感謝しております。これからも、地域のため、そして地域の人々のために、頑張っていきたいと思います。本日は、ありがとうございました。
 ご飯が食べられなくなったら、どうしますか
ご飯が食べられなくなったら、どうしますか
永源寺の地域まるごとケア
文 花戸貴司、写真 國森康弘 2015.03
一般社団法人 農山漁村文化協会
いのちつぐ「みとりびと」
第1集(全4巻)、第2集(全4巻)
文・写真 國森康弘 一般社団法人 農山漁村文化協会
