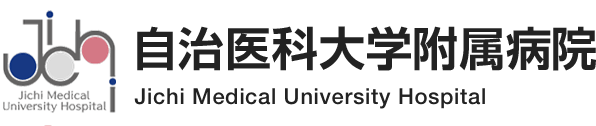脳神経センター外科部門(脳神経外科)【アニュアルレポート】
1.スタッフ(2024年4月1日現在)
| 科長 | (教授) | 國井 尚人 |
|---|---|---|
| 医局長 | (講師) | 大谷 啓介 |
| 外来医長 | (講師) | 石下 洋平 |
| 病棟医長 | (臨床助教) | 小熊 啓文 |
| 医員 | (教授) | 川合 謙介 |
| 五味 玲 (小児脳神経外科・兼) |
||
| 難波 克成 (血管内治療部・兼) |
||
| (准教授) | 中嶋 剛 | |
| (講師) | 中嶋 剛 | |
| 井林 賢志 | ||
| 大貫 良幸 | ||
| 病院助教 | 金子 直樹 (米国UCLAに留学中) |
|
| 檜垣 鮎帆 (血管内治療部・兼) |
||
| 黒田林太郎 | ||
| 佐藤 信 (芳賀赤十字病院に派遣中) |
||
| 下井 章寛 | ||
| 小河原 昇 (芳賀赤十字病院に派遣中) |
||
| シニアレジデント | 4名 (上記1名除く、1名は佐野厚生総合病院へ派遣中) |
|
| 大学院生 | 1名 | |
| 非常勤講師 | 4名 |
2.診療科の特徴
脳・脊髄脊椎疾患に対する最先端の外科的治療を成人および小児症例を対象に行っている(2022年手術件数 391件)。脳腫瘍(悪性腫瘍、良性腫瘍)、機能的疾患(てんかん、ーキンソン病なの不随意運動疾患、難治性疼痛、痙性麻痺、三叉神経痛や顔面痙攣)、小児脳脊髄疾患(腫瘍や先天奇形な)、脳血管障害、頭部外傷な外科的治療を要するあらゆる神経疾患を対象としている。
脳血管障害、頭部外傷な救急疾患には24時間体制対応しており、栃木県の脳卒中専門医療機関として認定を受けている。
また、厚生労働省のてんかん地域診療連携体制整備事業として、全国21か所の地域連携拠点機関の1つに指定されており、栃木県内のみならず北関東エリアを包括した広域てんかん診療拠点として機能している。
脳腫瘍に関しては、複数の手術支援技術を用いた低侵襲の手術治療を実践し、治療成績の向上に貢献している。また、術後の補助療法として放射線治療、化学治療を他診療科の専任スタッフと症例毎に検討し集学的治療を行っている。放射線治療では従来の放射線治療に加え、IMRT(強度変調治療)、VMAT(回転型強度変調治療)等の高精度治療も行っている。
てんかん外科では、各種モニタリング・手術等において国内有数の症例数と治療成績となっている。パーキンソン病・不随意運動・難治性疼痛・痙性麻痺などに対する機能的神経外科(刺激・凝固・持続髄注治療・遺伝子治療)も有数の治療実績数と成績を有する。
世界に先駆けて導入した自施設内3Dプリンターによる正常解剖・病変部3Dモデリングを術前シミュレーション・インフォームドコンセント・手術トレーニングなどに活用し、安全かつ効果の高い手術治療を実践している。
認定施設
- 日本脳神経外科学会専門医研修プログラム基幹施設
- 日本脳神経血管内治療学会認定研修施設
- 日本てんかん学会専門医認定訓練施設
- 日本てんかん学会包括的てんかん専門医療施設
- 日本定位・機能神経外科学会技術認定施設
専門医
| 脳神経外科学会専門医 | 川合 謙介 他 15名 |
|---|---|
| 日本てんかん学会指導医 | 川合 謙介 |
| 國井 尚人 | |
| 井林 賢志 | |
| 石下 洋平 | |
| 日本てんかん学会専門医 | 川合 謙介 |
| 國井 尚人 | |
| 石下 洋平 | |
| 井林 賢志 | |
| 中嶋 剛 | |
| 大谷 啓介 | |
| 佐藤 信 | |
| 日本脳神経血管内治療学会指導医 | 難波 克成 |
| 日本脳神経血管内治療学会専門医 | 難波 克成 |
| 檜垣 鮎帆 | |
| 金子 直樹 | |
| 日本神経内視鏡学会技術認定医 | 五味 玲 |
| 中嶋 剛 | |
| 大谷 啓介 | |
| 日本定位・機能神経外科学会技術認定医 | 中嶋 剛 |
| 大谷 啓介 | |
| 佐藤 信 | |
| 日本脳卒中学会指導医 | 國井 尚人 |
| 日本脳卒中学会専門医 | 國井 尚人 |
| 中嶋 剛 | |
| 石下 洋平 | |
| 紺野 武彦 | |
| 金子 直樹 | |
| 日本がん治療認定医機構がん治療認定医 | 五味 玲 |
| 日本リハビリテーション医学会認定臨床医 | 中嶋 剛 |
| 日本外科学会認定医 | 五味 玲 |
3.診療実績・クリニカルインディケーター
1)新来患者数・再来患者数・紹介割合
| 新来患者数 | 474人 |
|---|---|
| 再来患者数 | 8,744人 |
| 紹介割合 | 119.7% |
2)入院患者数 740(病名別)
| 病名 | 人数 |
|---|---|
| 脳腫瘍 | 141 |
| くも膜下出血、脳動脈瘤 | 160 |
| その他の脳血管障害 | 69 |
| 機能的脳神経外科 | 133 |
| 慢性硬膜下血腫 | 26 |
| その他の頭部外傷 | 27 |
| その他 | 184 |
| 計 | 740 |
3-1)手術症例病名別件数 469件
| 病名 | 人数 |
|---|---|
| 脳腫瘍(腫瘍摘出術+生検術) | 98 |
| 機能的手術(てんかん・パーキンソン病などの不随意運動症・顔面痙攣) | 67 |
| 脳動脈瘤 | 19 |
| 脳出血、その他脳血管障害 | 30 |
| 脊椎脊髄疾患 | 3 |
| 先天奇形 | 16 |
| 水頭症 | 33 |
| 頭部外傷(慢性硬膜下血腫以外) | 12 |
| 慢性硬膜下血腫 | 26 |
| 血管内手術 | 135 |
| 定位放射線治療(宇都宮セントラルクリニックへ紹介) | 0 |
| 上記に当てはまらないもの | 30 |
3-2)手術術式別件数・術後合併症
| 症例数 | 合併症 | 再手術例数 | |
|---|---|---|---|
| 脳腫瘍(腫瘍摘出術+生検術) | 98 | 5 | 1 |
| 脳血管障害 | 49 | 2 | 0 |
| 機能的手術(てんかん・不随意運動症・顔面痙攣) | 67 | 1 | 0 |
| 脊椎脊髄疾患 | 3 | 0 | 0 |
| 奇形 | 16 | 0 | 0 |
| 水頭症 | 33 | 1 | 2 |
| 頭部外傷(慢性硬膜下血腫以外) | 12 | 0 | 0 |
| 慢性硬膜下血腫 | 26 | 0 | 2 |
| 血管内手術 | 135 | 0 | 0 |
| 上記に当てはまらないもの | 30 | 1 | 0 |
4)化学療法症例:37例
大量MTX療法(メソトレキセート) 2例
PAV療法(プロカルバジン、ACNU、ビンクリスチン) 0例
IFN療法(インターフェロン) 0例
CARE療法(カルボプラチン、エトポシド) 2例
テモゾロミド療法 17例
ベバシズマブ療法 10例
カルムスチン脳内留置療法 8例
5)放射線療法症例・数
放射線療法:28例
6)悪性腫瘍の疾患別治療成績
手術死亡:1例(肺塞栓)
主要疾患の長期予後
| 退形成性星細胞腫 | 5年生存率 | 47% |
|---|---|---|
| 膠芽腫 | 5年生存率 | 14% |
| 1年生存率 | 79% |
7)死亡症例・死因・剖検数・剖検率
死亡者数:25人
剖検数:0人
剖検率:0%
死因
| 脳腫瘍 | 3人 | |
|---|---|---|
| 脳血管障害 | 20人 | |
| くも膜下出血 | 8人 | |
| 脳出血 | 12人 | |
| 外傷性頭蓋内出血 | 2人 | |
8)主な処置・検査
頭部MRI、頭部CT、頭部3DCT、SPECT、PET、光トポグラフィー、脳血管造影検査
9)カンファレンス
a)脳神経外科内
| 月曜・水曜・金曜日 | 7時45分-9時 | 入院症例検討カンファレンス |
|---|---|---|
| 火曜 | 14時-17時 | 教授回診、術前術後症例検討、研究報告、抄読会 |
| 脳神経外科学会研修プログラム連携施設・関連施設 合同カンファレンス |
(Web開催) | |
b)他部門との合同カンファレンス
| 脳卒中センターカンファレンス | 毎週火曜日 7時45分~8時45分 |
|---|---|
| てんかんセンターカンファレンス | 毎月1回 |
| 放射線治療カンファレンス | 毎週火曜日17時~18時 |
c)その他
栃木県脳神経外科研究会 3回/年
エピネット栃木プラス 2回/年
栃木県脳腫瘍懇話会 2回/年
栃木県てんかん研究会 1回/年
薬師寺脳卒中セミナー 2回/年
d)カンファレンス症例数 約1,900例/年
10)キャンサーボード
グループ名 なし
実績 1年間 0回 カンファレンス
4.2024年の目標・事業計画等
本院は厚生労働省のてんかん地域診療連携体制整備事業として全国21か所の地域連携拠点機関の1つに指定されている。栃木県内のみなら北関東エリアを包括した広域てんかん診療拠点として、より一層の診療の拡充と質の向上を図るとともに、既設のエピネット栃木プラスなどを引き続き最大限活用し圏内医療施設、行政との有機的な連携を強化していく計画である。
脳卒中センターカンファレンスを実施し脳血管疾患症例(主に入院症例)の検討を複数診療科の医師らにより行っている。血行再建手術の適応症例など、単科診療のみでは診断と治療が困難な症例に対する学際的な検討を推進することで診療レベルの一層の向上を図っていく。
国立研究開発法人日本医療研究開発機構「成育疾患克服等総合研究事業」(研究開発課題名:AADC欠損症に対する遺伝子治療の臨床研究)の受託研究機関として、本講座は脳神経外科的手法による遺伝子治療薬の導入に関与し、国内外の患者を治療対象とし良好な結果を得てきた。さらに同機構の「再生医療等実用化研究事業」(評価課題名:グルコーストランスポーター1欠損症に対する遺伝子治療開発)においても遺伝子治療薬の導入に携わり、指定難病であるグルコーストランスポーター1欠損症の患者に対して遺伝子治療を実施する計画である。
悪性神経膠腫において染色体1番短腕/19番長腕欠失、MGMT(O6-methylguanine-DNA methyltransferase)発現、IDH(Isocitrate dehydrogenase)遺伝子変異などを対象とした分子遺伝子学的診断法を行っており、オーダーメイド型治療戦略による一層の治療成績の向上を目指す。
これまでに本学先端医療技術開発センター脳機能研究部門およリハビリテーションセンターとの共同研究により、脳疾患症例における効率的な機能回復を目指した神経リハビリテーション治療を開発してきた。引き続き社会寄与度の高い治療方法を開発し臨床への還元を図っていく。
子ども医療センターの開設以来、二分脊椎や小児脳腫瘍、てんかん、不随意運動症など小児脳神経外科治療の対象となる症例が全国から紹介されている。小児脳神経外科が独立して存在し、かつ、センター内で他診療科と有機的に連結した国内有数の治療施設である。その利点を最大限に活用した高水準の医療を引き続き実践していく。