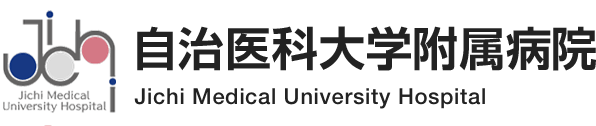皮膚科【アニュアルレポート】
1.スタッフ(2024年4月1日現在)
| 科長 |
(教授) |
小宮根真弓 |
| 外来医長 |
(助教) |
中野 尚美 |
| 病棟医長 |
(准教授) |
佐藤 篤子 |
| 医員 |
(教授) |
大槻マミ太郎 |
| (准教授) |
神谷 浩二 |
| (講師) |
角 総一郎 |
| (助教) |
杉原 夏子 |
| (病院助教) |
岡田 寛文 |
| シニアレジデント |
|
5名 |
2.診療科の特徴
当科では皮膚に症状のある疾患すべてを扱うが、大学病院および地域の特性として、皮膚がんや悪性黒色腫を中心とする悪性腫瘍、水疱症、膠原病、乾癬、重症アトピー性皮膚炎、遺伝性皮膚疾患などが多いのが特徴である。
入院では、皮膚悪性腫瘍が約7割を占め、手術、化学療法、放射線療法、分子標的薬、免疫チェックポイント阻害薬による治療を行っている。副作用の発現も高い治療であるが、他科との連携をとりつつ適切に対処している。
外来は午前に初診と一般再診、午後は専門外来を設けている。専門外来は、より専門性の高い診療を必要とする疾患、すなわちアトピー性皮膚炎、乾癬、水疱症、膠原病、脱毛症、皮膚悪性腫瘍、皮膚レーザー、遺伝カウンセリングなどに対するもので、県内だけでなく他県からの紹介患者も数多く来院している。外来ではレーザー治療、紫外線療法、簡単な植皮を含めた手術を行っている。診断や治療方針に苦慮する症例について、教授以下全員で診察する機会(外来クリニカルカンファレンス)を設けているほか、皮膚生検を行った症例では病理カンファレンスで検討し、個々の症例に即した最善の治療を皮膚科全体として追求するシステムを構築している。
乾癬については、2008年の栃木県患者会(とちぎ乾癬友の会)の立ち上げ以来、専門外来メンバーを中心に啓発活動を精力的に行ってきた。現在、生物学的製剤が多数承認されており、導入前の検査入院、外来での導入はスムーズに実施されている。導入後コントロールが付いた時点で、近医紹介元への逆紹介を推進している。逆紹介率の向上により、地域全体での診療のレベルアップと当科の過度の負荷を減らすことを目標としている。
2022年度にアレルギー・リウマチ科の協力のもとに開設した乾癬性関節炎外来では順調に患者数が増えている。臨床データも蓄積しつつあり乾癬学会やリウマチ学会で発表している。蕁麻疹やアトピー性皮膚炎においても保険適応のある生物学的製剤が増え、また悪性黒色腫への免疫チェックポイント阻害剤や分子標的薬の投与など、皮膚科外来医が扱う治療薬の範囲が拡大している。脱毛症専門外来においてJAK阻害剤による円形脱毛症の治療症例も増えている。
新規開発臨床試験(治験)は、これまで乾癬、アトピー性皮膚炎、掌蹠膿疱症を対象とするものが中心であったが、2024年度は天疱瘡の治験が予定されている。
施設認定
- 日本皮膚科学会認定専門医指定施設
- 日本専門医機構認定皮膚科専門研修プログラム基幹施設
専門医
| 日本皮膚科学会専門医 |
大槻マミ太郎 |
| 小宮根真弓 |
| 神谷 浩二 |
| 佐藤 篤子 |
| 杉原 夏子 |
| 中野 尚美 |
| 岡田 寛文 |
| 日本医師会認定産業医 |
小宮根真弓 |
3.診療実績・クリニカルインディケーター
1)新来患者数・再来患者数・紹介割合
| 新来患者数 |
1,489人 |
| 再来患者数 |
22,087人 |
| 紹介割合 |
93.4% |
2)入院患者数
| 入院患者数 |
486人 |
| 一日平均患者数 |
14人 |
| 平均在院日数 |
10.6日 |
| 疾患分類 |
患者数 |
| 湿疹・皮膚炎・蕁麻疹・痒疹 |
19 |
| 角化症・炎症性角化症・膿疱症 |
16 |
| 膠原病・類症・血管炎 |
2 |
| 水疱症 |
16 |
| 薬疹・中毒疹・ウイルス性発疹症 |
12 |
| 感染症 |
26 |
| 皮膚潰瘍・褥瘡・熱傷 |
33 |
| 皮膚悪性腫瘍 |
276 |
| 皮膚良性腫瘍 |
70 |
| 母斑 |
7 |
| 下肢静脈瘤 |
2 |
| 発汗障害 |
4 |
| 合計(人) |
483 |
| 平均年齢(歳) |
64.3 |
| 男:女 |
270:216 |
| |
入院 |
外来 |
| 皮膚悪性腫瘍切除術 |
131 |
26 |
| 皮膚悪性腫瘍切除術 |
104 |
31 |
| 皮膚腫瘍・血管腫切除術 |
63 |
115 |
| 創傷処理・皮膚切開術 |
3 |
24 |
| デブリドマン |
12 |
0 |
| 母斑レーザー(全麻下) |
11 |
0 |
| 静脈瘤手術(含:血管内レーザー) |
2 |
0 |
| センチネルリンパ節生検 |
24 |
0 |
| リンパ節郭清術 |
5 |
0 |
| 植皮術 |
82 |
1 |
| 皮弁・筋皮弁術 |
8 |
0 |
| その他(リンパ節生検含む) |
12 |
671 |
| エキスパンダー |
0 |
0 |
| 合計(件) |
326 |
842 |
麻酔別手術統計
|
病棟 |
外来 |
| 局所麻酔 |
114 |
841 |
| 腰麻・全麻 |
94 |
0 |
3)カンファレンス症例数
| |
症例数 |
カンファレンス率* |
| 外来カンファレンス |
271 |
18.20% |
| 病理カンファレンス |
162 |
12.96% |
*外来カンファレンス率 = カンファレンス症例数(271)/新来患者数(1,489)X100
*病理カンファレンス率 = カンファレンス症例数(162)/病理提出件数(1,250)X100
4.2024年の目標・事業計画等
- 一般再診と専門外来について
午前中には該当する専門外来のない患者を主に診察する一般再診及びレーザー外来、午後にはアトピー性皮膚炎、乾癬、水疱症、膠原病、脱毛症、悪性腫瘍に関する専門外来を開設しており、難治で長期間のフォローアップが必要な患者の診療を担っている。特別な検査や注意が必要な症例に関しては、クリニカルカンファレンスで検討することで、医局員全員で診察し、病理カンファレンスクリニカルカンファレンスレビューにおいてその経過を医局員全員で共有することで、若手の医師も数多くの皮膚科診療の経験を共有することができるようにしており、2024年度も継続的に行う予定である。
近年、乾癬、アトピー性皮膚炎、掌蹠膿疱症、円形脱毛症、蕁麻疹では生物学的製剤やJAK阻害剤をはじめとする分子標的薬の登場に伴い、治療選択肢が多岐にわたり、紹介患者数も増数している。副作用の発現には充分に注意して診療を行う。コントロールが付いた症例については、紹介元への逆紹介を推進することで当科の負担軽減と地域全体での診療のレベルアップを目指し多くの講演会や小規模のオンライン及び対面ミーティングを行った。2024年度も引き続き継続する予定である。
- 悪性腫瘍について
原発巣広範囲切除および再建、センチネルリンパ節生検、所属リンパ節覚醒等の侵襲の大きな外科的手術は、県内では獨協医科大学と当院の2施設で主に行っているため、2024年度においても自治医科大学は皮膚外科診療においては近隣地域や県内外における中心的存在であることが予想される。2023年度には手術治療を縮小したが、2024年度は術者が充実し再び拡大を目指している。安全で確実な外科治療を遂行するため、技術のレベルアップ、他科との連携や多職種間の良好なコミュニケーション、QSセンターとの協力に努める。切除不能な悪性腫瘍に対する免疫チェックポイント阻害剤や種々の分子標的薬が使用可能であり、最新のがん治療ガイドラインに沿ったシステマティックな治療を目指す。
オンコパネルを用いた最新のがん診療については、早めの検体提出を目指しており、2024年度も引き続き適切な症例選択と早めの検体提出を行い、必要な患者に最新治療を適切に届けられるよう努力したい。
- 下腿潰瘍の診療は、診断・治療を含め難しい点が多い。診断については、感染症、血管炎、静脈うっ滞、壊疽性膿皮症など種々の疾患が含まれるため、必要な検査を行い適切に診断できるよう努力しており、2024年度も引き続き継続する。壊疽性膿皮症については生物学的製剤が使用可能となったため、診断確定した症例については積極的に使用したい。潰瘍面積がある程度以上の場合には外科的治療が必要になるため、保存的治療、外科的治療を含めた長期的フォローアップの充実を目指す。一方で、難治性潰瘍の病変からPCRで抗酸菌やヘルペスウイルスが証明されることがあるため、2024年度は潰瘍部からの培養が陰性でもPCR検査あるいはマイコアシッド培地による培養にて確認したい。
- 重症薬疹、自己免疫性水疱性疾患、壊疽性膿皮症の入院患者については、早期の確実な診断と適切な治療を目指す。治療には高容量の副腎皮質ホルモンや免疫抑制剤、リツキシマブ、IVIGの全身投与が必要であるため、副作用の発現に注意しつつ他科との連携のもと、安全で最適な治療を目指す。
- パッチテストはこれまで通り積極的に行う。藤田医科大学との共同研究に参加して全国調査の結果を得ることで、日常診療の向上に努める
- 糖尿病性足壊疽、末梢動脈循環不全による足壊疽による下肢切断回避のため、足・爪のケアの充実、皮膚潰瘍の適切な診断と治療に努める。特に内分泌代謝内科、循環器内科、整形外科との連携を充実させることにより適時に適切な治療が導入できるよう努力を継続する。
- 遺伝性疾患については、保険診療の範囲が拡大し診断可能な疾患が増えた。遺伝カウンセリング外来を開設し、適切なカウンセリングのもと遺伝学的検査を施行している。可能な限りかずさDNA研究所をはじめとする認定施設での検査を施行する。対象遺伝子の探索が必要な場合には、免疫染色、電子顕微鏡検査も含めた総合的診断を行う。