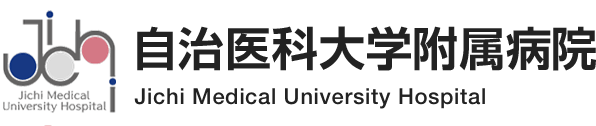麻酔科【アニュアルレポート】
1.スタッフ(2024年4月1日現在)
| 科長 | (教授) | 竹内 護 (子ども医療センター兼任) |
|---|---|---|
| 鈴木 昭広(周術期部門) | ||
| 五十嵐 孝(ペイン・周産期部門) | ||
| 医員 | (准教授) | 多賀 直行 (子ども医療センター兼任) |
| 堀田 訓久 | ||
| 佐藤 正章 | ||
| 末盛 智彦 (子ども医療センター兼任) |
||
| (学内講師) | 関 厚一郎 | |
| (講師) | 永野 達也 (子ども医療センター兼任) |
|
| (助教) | 大塚 洋司(留学中) | |
| 吉永 晃一 | ||
| 須藤 智幸 | ||
| 栁沼 和史 (子ども医療センター兼任) |
||
| 病院助教 | 篠原 貴子 (子ども医療センター兼任) |
|
| 方山 加奈 | ||
| 原 鉄人 | ||
| 原村 陽子 (子ども医療センター兼任) |
||
| 山本 令子 | ||
| 藤田 裕壮 | ||
| 山田 衣璃 | ||
| 山田 希生 | ||
| 村田 英崇 | ||
| 山田 高嗣 | ||
| 田中 諒子 | ||
| 中田 翔 | ||
| 小川 薫 | ||
| シニアレジデント | 4名 |
2.診療科の特徴
麻酔科の主な業務は、大学附属病院とそれに併設されたとちぎ子ども医療センターの手術室での麻酔管理である。2023年の総手術件数は10124件で、COVID-19感染患者増加による手術数削減の影響を受けた時期があるものの、当科麻酔管理症例は2022年より増加し、6949件だった。緊急手術の麻酔管理も多く行っており、栃木県のみならず北関東一円からの急患に24時間対応している。手術室外でも血管内治療部でのカテーテル治療や、小児のMRI検査など様々な要請に応じて、出張麻酔・鎮静を行っている。
安全で患者満足度の高い周術期管理を目指して、周術期センターが発足した。すでに術後疼痛管理チームが活動していたが、2023年は一部の診療科で多職種による術前評価を開始し2024年の本格稼働に備えている。
疼痛治療としては、術後疼痛管理チーム(J-TAPS)の活動に加え、ペインクリニック外来や緩和ケアチームでの活動を通して、入院患者、地域住民の生活の質の向上に貢献している。
施設認定
- 日本麻酔科学会麻酔科研修認定病院
- 日本ペインクリニック学会指定研修施設
- 日本心臓血管麻酔学会専門医認定施設
認定医・専門医
| 厚生労働省麻酔標榜医 | 竹内 護 他28名 |
|---|---|
| 機構専門医麻酔科専門医(含麻酔科学会専門医) | 竹内 護 他24名 |
| 日本麻酔科学会指導医 | 竹内 護 他10名 |
| 日本ペインクリニック学会専門医 | 鈴木 昭広 他4名 |
| 日本集中治療医学会専門医 | 竹内 護 他8名 |
| 日本心臓血管麻酔学会専門医 | 竹内 護 他4名 |
| 日本区域麻酔学会指導医 | 堀田 訓久 他1名 |
| 日本区域麻酔学会認定医 | 篠原 貴子 |
| 日本小児麻酔学会認定医 | 竹内 護 他3名 |
| 日本蘇生学会蘇生法指導医 | 鈴木 昭広 他1名 |
| 日本周術期経食道心エコー認定医 | 鈴木 昭広 他6名 |
| 日本臨床麻酔学会インストラクター(神経ブロック) | 堀田 訓久 |
| 日本救急医学会専門医 | 鈴木 昭広 他1名 |
| 日本小児科学会専門医 | 柳沼 和史 |
| 日本小児科学会指導医 | 柳沼 和史 |
| 日本プライマリ・ケア連合学会認定指導医 | 佐藤 正章 |
| 日本航空医療学会フライトドクター認定医 | 鈴木 昭広 |
3.診療実績・クリニカルインディケーター
1)新来患者数・再来患者数・紹介割合
| 新来患者数 | 41人 |
|---|---|
| 再来患者数 | 2,779人 |
| 紹介率 | 54.1% |
| 手術患者外来術前診察 | 5,734人 |
2)入院患者数
脊髄刺激装置埋め込み術ほか 7人
3)手術症例病名別件数
| 脊髄刺激装置埋め込み術 | |
|---|---|
| 複合性局所疼痛症候群 | 4件 |
| 硬膜外腔癒着剥離術 | |
| 難治性腰下肢痛 | 14件 |
| くも膜下フェノールブロック | |
| がん性痛 | 3件 |
| 腹腔神経叢ブロック | |
| がん性痛 | 1件 |
| 腰部交感神経節ブロック | |
| 複合性局所疼痛症候群 | 1件 |
4)手術症例病名別治療成績
| 複合性局所疼痛症候群 | 軽快 4件 |
|---|---|
| がん性痛 | 軽快 3件 |
5)死亡症例・死因・剖検数・剖検率
なし
6)主な検査・処置・治療件数
| 手術麻酔(2023年) | |
|---|---|
| 全身麻酔(硬膜外・伝達麻酔併用を含む) | 6,949件 |
| 脊髄くも膜下麻酔(硬膜外麻酔併用を含む) | 712件 |
| 硬膜外麻酔・伝達麻酔 | 42件 |
| 麻酔科依頼静脈麻酔・その他 | 21件 |
| 麻酔科外来処置 | |
| 星状神経節ブロック | 23回 |
| 三叉神経ブロック | 47回 |
| 硬膜外ブロック | 190回 |
| 腕神経叢ブロック | 53回 |
| 肋間神経ブロック | 29回 |
| 神経根ブロック | 30回 |
| その他の神経ブロック | 71回 |
| 鍼灸 | 554回 |
| 光線治療等 | 1,665回 |
7)カンファランス症例
| 手術患者術前カンファランス | 245回 |
|---|---|
| 手術患者術後カンファランス | 245回 |
| 症例検討カンファランス | 7回 |
8)キャンサーボード
なし
4.2024年の目標・事業計画等
麻酔業務
手術患者の高齢化や合併症保有率の上昇に伴う高難度の手術が増加しており、より厳密な麻酔管理を行うことが求められている。適切な麻酔管理のために日常臨床での指導のみでなく、カンファレンスでの症例検討や勉強会を充実させることで医局員の知識・技術の向上に勤めていく。一方で、定時延長手術の増加で時間外勤務が求められる人員が増加し、さらなる緊急手術への対応には人員の充足が必要である。中央手術部と連携し、適切な手術枠の設定、人員配置を進めて行く。
周術期センターの設立と多職種連携
周術期センターの業務としては、一部の診療科で多職種による術前評価が開始され、術後疼痛管理チームも対象患者を拡大している。2024年の本格的な運用に向けて、関連職種との連携を強化していく。
全身管理能力習得のための研修医教育
麻酔科は初期研修医が将来どの診療科を専門にしても必要となる、呼吸・循環管理をはじめとする全身管理のトレーニングの場として非常に適している。短い研修期間で医師として必要な全身管理の知識・技術を身につけるために、到達目標を明確に定め、新たにシミュレーション教育も取り入れていく。
学生教育
COVID-19の影響からほぼ脱し、例年通りの実習が再開されている。麻酔科実習は生命維持に直結したABCD(気道・呼吸・循環・意識)の変化と管理をもっとも間近に学べる場であり、学生が将来医師として働く上での基礎知識・技術として医局全体で指導に努めていく。