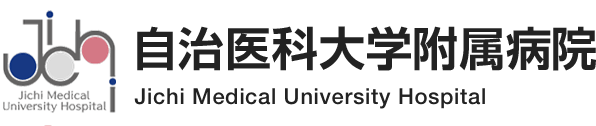看護部【アニュアルレポート】
1.スタッフ(2024年4月1日現在)
| 看護職員 | 1,462人 |
|---|---|
| 看護師 | 1,387人 |
| 助産師 | 71人 |
| 保健師 | 4人 |
2.看護部理念
安心感と温もりのある患者中心の看護を提供します
3.基本方針
- 患者さんの意思を尊重し、「いのち」と「暮らし」を守る看護を提供します。
- 患者さんと家族とともに、地域関係機関や院内の多職種と協働した質の高いチーム医療を行います。
- 地域医療における看護を牽引できる人材を育成し、社会に貢献します。
- 高度先進医療を推進する実践力と生活の視点をもち、最善の看護が想像できる専門職業人を目指して、自己研鑽に努めます。
4.2023年度看護部活動
看護部では年度内に取り組む課題を抽出するために、SWOT分析/クロスSWOT分析で現状の分析をし、業績評価指標であるBSC(Balanced Score Card)を用いて提示している。各部署でもSWOT分析/クロスSWOT分析をし、看護部BSCをもとに自部署のBSCを作成している。
看護部目標およびBSCの4視点について成果を記載する。
【看護部目標】
- 変化する医療情勢や患者のニーズに柔軟に対応し、患者満足度の向上を図る
- 安全で質の高い看護の提供を維持するために看護職員を育成する
- 心身ともに健康で働き続けられる職場環境を整備し、職員満足度の向上を図る
- 質の高い看護実践と経営を意識した看護活動により病院収益に貢献する
【BSCの4視点に関しての取り組み】
視点、重要成功要因を項目立てして、重要業績評価指標(KPI)、目標値、活動、成果を記載する。
1.顧客の視点
- 外部顧客
(1)患者満足の維持・向上
調査の結果「満足」「やや満足」の割合は、外来98.2%(△0.3)、入院98.8%(+0.5)だった。外来・入院ともに98%以上を目標としており、前年度に引き続き高い患者満足度を維持できた。 - 内部顧客
(1)職員満足の維持・向上
総合満足度2.8以上(4段階評価)、「やりがいを感じられる」「仕事を通じた成長」に関する項目の満足度2.8以上と目標を設定した。結果、総合満足度は2.78(+0.01)、「やりがいを感じられる」2.87(+0.03)、「仕事を通じた成長」2.85(+0.03)であり、総合満足度は前年度より上昇したものの目標を達成できなかった。COVID-19感染症に伴う自宅待機者の増加によって「休日休暇取得」、「人員数が適切」、「仕事量が適切」等衛生要因への満足度が低くなった。しかし、他大学(2.61)、他施設(2.5)の総合満足度より高く、「職場風土」「人間関係」に関する全項目は前年度より上昇し、当院の強みである。(2)働き方改革
①日勤での19時までの退勤割合を、病棟60%以上、中央部門80%以上として取り組んだ。看護業務委員会が中心となりJUNIORSを活用した部署内応援促進等の支援をした。目標を達成できた病棟は56.2%(32部署中12部署)、中央部門は79%(13部門中10部門)で、未達成であった。18部署がJUNIORSを導入・継続し、1年以上継続している部署の時間外勤務時間が低減しており、継続的な支援と評価が今後の課題である。
②病棟看護職員の年休と祝日取得数を合わせて21日以上、中央部門は年休取得数12日以上を目標とした。中央部門は年休13.05日(+0.28)で目標を達成したが、病棟は20.3日(+0.3)で達成できなかった。COVID-19による自宅待機総日数が大きく影響しており、総計3,422日(前年度比+2,028)で看護職員1人当たりに換算すると3.4日となる。(3)離職者減少
職場風土や人間関係を理由とした離職者数0を目指して取り組み、目標を達成した。
2.財務の視点
- 病院経営への貢献
(1)稼働率の維持
COVID-19による手術制限や病棟運営等の影響を受け、82%(前年比+1.7)で90%の目標に達成しなかった。(2)加算取得率(数)増加
①せん妄ハイリスク患者ケア加算算定率100%、②認知症ケア加算2算定数570件以上/月③がん患者指導管理料イ算定数103件以上/月、④入退院支援加算1.3算定率37%以上を目標とした。①は95.6%(前年度比+0.8%)と伸びたが、該当者11,447人に対して679件(5.9%)の算定漏れがあり目標達成できなかった。②は809件/月で目標達成。③体制を整備して対応したが、COVID-19による人員不足で対応できない症例があり、97件/月で目標を達成できなかった。④43.8%に伸びており、目標を達成した。(3)DPC係数の維持・向上
①一般病床7対1入院基本料施設基準(夜勤時間72時間以内/月)②看護職員夜間12対1配置加算③急性期看護補助体制加算25対1④急性期看護補助体制加算夜間100対1の4点をKPIとし、維持できることを目標とした。①に関しては月平均80.5%の短時間勤務者が夜勤協力をし、一人当たりの夜勤時間は67.15時間になった。②は勤務間インターバル11時間以上を意識した勤務表を作成し、NG数を5%以内にできた。③④は退職後の補充がタイムリーにできるよう委託業者との調整、ゴールデンウィークや年末年始の出勤協力等により維持できている。
3.内部プロセスの視点
- 患者の安全の確保
①インシデント3レベル報告件数低減の計画を全部署で立案し活動した。しかし、目標を達成できた部署は37部署中19部署にとどまった。分析が不十分であったことが要因と考える。ダブルチェック方法の統一後の評価が次年度の課題である。
②適正な身体拘束のための監査実施をKPIとし、全部署が実施し目標を達成した。拘束率低減の取り組みが今後の課題である。 - 感染防止
患者1,000人当たりの手指消毒剤使用料を20L/月以上と目標を設定した。平均して1部署あたり27L/月と目標を達成したが、目標を達成しない部署が30部署中7部署あった。今後さらに強化する必要がある。 - 質の高い看護の提供
(1)看護の質的評価の向上
①固定チームのチーム目標達成率80%以上
固定チーム検討会による部署支援、固定チームナーシングの質評価、チームリーダー・サブリーダー連絡会開催により、1年間で達成可能な目標設定ができ、36部署中35部署が目標を達成している。
②患者アウトカムの達成率、一般病棟94%、重症部門90%という目標に対して、一般病棟96.3%(前年度比+0.8)、重症部門91.4%(+1.2)で目標達成した。
③成果指標達成率90.1%以上という目標に対して、93.4%であった。
④看護記録監査の質評価項目点数が、1回目監査より2回目が上昇することを目標とした。1回目3.13点(5点満点)、2回目3.30で目標を達成した。1回目の監査点数も年々上昇している。(2)意思決定支援の強化
KPI・目標を「IC同席した件数」と同席できなかった際の「理解・納得状況の確認」記録件数を合わせた割合を80%以上とした。結果は69.9%で目標を達成できなかった。しかし、記録割合が、下半期に上昇した部署が34部署中15部署であった。ICタグ「該当有」入力に関する医師との情報共有等の課題が残った。(3)退院支援の充実
①医療的ケアがある患者への退院指導実施割合をKPIとして、入院60%以上、外来8%以上を目標にした。入院では59.6%と前年比7%増であったが目標を達成できなかった。しかし、下半期は71.1%に上昇した。外来は2.5%増の11.8%となり、下半期では12.4%となった。 - 人材の活用強化
(1)特定行為看護師の活動件数270件以上/月を目標とした。委員会が中心になり研修修了後速やかに活動に移行できるような支援を行い、2月までの実施件数は3,937件(358件/月)で12月以降は430件/月と伸びている。
(2)専門看護師・認定看護師の①相談件数②指導件数を各自で目標設定し、100%の達成率を目指した。総数では①1,459件(前年比+16)②268(+65)と増加したが、領域別、個人による活動件数の差が大きく(目標達成者63%)、今後の課題である。
- タスクシフト
(1)薬剤師の業務拡大
看護部と薬剤部で検討した結果、年度内の活動は困難であることを確認したため中止とした。
4.学習と成長の視点
- 人材の育成
(1)特定行為看護師増加
区分ごとの入講者数を決定したが、3名の入講にとどまり、目標数9人には至らなかった。(2)認定看護師増加
2024年度の受講希望者3名を目標にした。慢性呼吸不全看護、脳卒中看護、不妊看護、認知症看護など新たな領域への入講者を含め計6名となり、目標を達成した。(3)看護管理者の育成
「特定行為研修の組織定着化事業」への参画を機会ととらえ、ナーシングスキルスによる共通科目を2年目以上看護師20%以上が受講することを目標とした。対象職員1,238名、閲覧数3,818回、47部署中41部署が100%以上の閲覧率となり、目標を達成できた。 - 災害対策の強化
(1)災害対策能力の向上
災害訓練動画視聴と部署開催学習会(避難訓練または減災トレーニング)の100%参加を目標とした。委員会が中心となって部署支援をし、目標を達成した。
5.看護部の教育実績
1)看護職の院内教育の実績
看護職員の院内研修は看護部の教育方針のもと、J-ARISEキャリア・パスのキャリア・ラダー研修プログラムに沿って実施した。(看護職キャリア支援センターの項参照)
主任看護師研修会は年間テーマを「経営的な視点から看護の質の向上を図る」とし、隔月で6回開催した。(表3参照)自部署の現状を経営的な視点で分析し、課題を抽出して活動計画を立案・実施した。また、マネジメントラダーⅠの評価指標に照らして自己の課題を明確にし、取り組みを通した能力の向上を図った。
前半では看護の質と診療報酬、当院の経営戦略についての講義を受け、中盤以降ではGWにより自己の取り組みについて情報共有と意見交換を行った。最終会のGWでは、課題に取り組んだ背景、実践計画、実践内容、評価と課題の4つの題目にまとめ発表した。
看護師長研修会は年間テーマを「人材育成能力の向上」とし、隔月で6回開催した。(表4参照)人材マネジメントに必要な心理的安全性、および人生100年時代に求められるスキルとキャリア支援について講義を受け、自部署のスタッフのキャリア志向の現状と課題、マネジメントラダーⅡの評価指標に照らし人材育成における管理者としての課題について意見交換を行った。また、文献検索や情報交換を行い、取り組む課題を明確化し活動計画を立案・実施した。中盤では、効果的なキャリア面談についての講義を受け、取り組みの中間評価や活動計画の修正に活かした。最終会のGWでは、取り組んだ課題について現状分析、活動内容、結果、今後の課題の4つの題目にまとめ発表した。
看護部講演会は、国際医療福祉大学の中田光紀先生を講師として「いきいきと働くための睡眠・休息の在り方」をテーマに開催した。附属病院看護部227名の参加があった。
2)看護職の資格取得に関わる院外教育の実績
認定看護師の育成では2023年度は「感染管理」と「慢性心不全看護」の2領域の教育課程において2名が修了した。また、「感染管理」と「摂食・嚥下障害看護」の2領域で認定試験に合格し、認定看護師25名、専門看護師15名が活躍している。今後も先を見据えた育成計画を検討し、各領域の複数配置を目指す。
認定看護管理者の育成では2023年度はファーストレベル6名、セカンドレベル4名、サードレベル2名が受講した。現在、主任看護師84名中ファーストレベルの修了者は61名である。また看護師長以上50名中サードレベルまでの修了者は12名であり、認定看護管理者は10名となっている。
本学の看護師特定行為研修センターを活用した特定行為看護師の育成では、2023年度は4月期・10月期を合わせ新3名、科目追加2名が入構した。2023年4月現在在職している特定行為看護師は55名である。体制整備と周知活動により組織横断的活動が行えており、活動件数は月平均365件と前年度より増加している。今後は適正配置やニーズの高い行為を中心に育成計画に基づくさらなる受講者の確保を進めるとともに、安全な実施を継続するため院内全体での支援体制を整える。
3)学会および院外研修会の参加実績
学術集会がハイブリット開催で行われるようになっており、参加費補助の枠は変更していないが自分自身の都合に合わせて参加形態を選択できるようになっている。2023年度は62種類の学会に309名が参加し、22名が演題発表した。
院外研修への参加は、看護協会主催の研修受講者151名、その他(企業・財団・大学・学会等)主催の研修受講者111名で合計262名であった。
4)臨床実習の教育体制
新型コロナウイルス感染症が第5類となった以降も、マスクの着用や手指消毒、黙食、健康観察などが徹底されていることを確認し、本学看護学部の全学年のすべての実習を実施した。また、本学外の看護師養成機関の臨床実習についても依頼のあった4校も実施できた。(表5参照)
認定看護師教育課程の実習は「緩和ケア」1校2名、「がん放射線療法看護」1校2名、「摂食・嚥下障害看護」1校2名を受け入れた。(表6参照)実習指導者を計画的に育成し、基礎教育、継続教育の受け入れ体制を整えており、県内外の看護師教育に貢献している。
5)院外への講師派遣
栃木県看護協会や県内外の医療機関、行政機関、看護師養成機関3施設等からの依頼を受け、256名の看護部職員を講師・指導者として派遣し、多くの医療職の教育に貢献している。
表1 主任看護師研修会実施状況
| 日程 | 参加者 | テーマ | 目的 | 目標 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 5月12日(金) | 81名 | 経営的な視点から部署の看護を考える | 主任看護師として、経営的視点から自部署の看護実践をマネジメントできる | ①経営的視点での活動を主任看護師間で共有し、自己の課題を見いだすことができる ②さまざな加算を取得することが、看護の質の向上に結びつくことが理解できる |
| 第2回 | 7月14日(金) | 83名 | 加算取得のための方法を知る | 加算取得のための方法を知り、取得に向けた取り組みを明確にできる | ①看護の質の維持・向上を図るための加算取得の方法が理解できる ②マネジメントの視点から、自部署の加算取得に向けた取り組みを明確にできる |
| 第3回 | 9月8日(金) | 71名 | 経営の視点を踏まえてマネジメント能力を活用した取り組みを考える | 経営の視点を踏まえた主任看護師の活動を明確にする | ①病院経営と看護活動の経営的効果を理解する ②経営的効果につながる部署の看護活動を明確にする |
| 第4回 | 11月10日(金) | 80名 | 看護倫理研修【2】 レポート評価 |
ラダーⅡBトライ者研修看護倫理研修【2】のレポート評価をし、部署での看護倫理に関する教育や人材育成に活かすことができる | ①ラダーⅡBに求められる看護倫理力とその評価の視点を理解できる ②看護倫理研修【2】のレポート評価ができる |
| 第5回 | 令和6年 1月12日(金) |
82名 | 個人の取り組みに対するマネジメントリフレクション | マネジメントリフレクションを通し、主任看護師としての経営的視点をふまえた看護管理実践能力を高める | ①自己のマネジメント経験を内省し他者から示唆をもらうことで気づきや学びを得ることができる ②自己の取り組みの課題解決に向けた具体策を見出すことができる |
| 第6回 | 3月8日(金) | 83名 | 個人の取り組みに対する実践報告 | マネジメントの実践報告を通し、経営的視点を踏まえた看護管理能力を高める | マネジメントの実践と成果を共有し、次年度の課題を見出すことができる |
表2 看護師長研修会実施状況
| 日程 | 参加者 | テーマ | 目的 | 目標 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 5月18日(木) | 43名 | ・人材マネジメントに必要な心理的安全性 ・人生100年時代に求められるスキルとキャリア形成 |
スタッフのキャリア形成を支援する意義が理解できる | ①GWを通して自部署のキャリア形成支援の問題がわかる ②GWを通してキャリア形成支援における自己課題を見出す |
| 第2回 | 7月20日(木) | 38名 | ・課題取り組みシートの活用による現状分析 ・キャリア形成支援に関する知見や情報の共有 |
「スタッフのキャリア形成支援」について課題を明確にし、具体的な活動計画が立案できる | ①「キャリア形成支援に必要な知識・情報」をグループメンバーと共有する ②活動計画のゴール設定ができる |
| 第3回 | 9月21日(木) | 40名 | 効果的なキャリア面談について | 看護管理者に求められるスタッフのキャリア形成支援について学ぶ | 講義を通して効果的な面談方法を理解する |
| 第4回 | 11月16日(木) | 42名 | 人材育成能力の向上:「マネジメント研修【1】のレポート評価」 | 看護師長として人材育成能力を高めることができる | マネジメント研修【1】&実践教育研修【1】の研修レポートの評価ができる |
| 第5回 | 令和6年 1月18日(木) |
41名 | ・部署における心理的安全性チェックリストの活用 ・中間面接でのキャリア形成支援の振り返り |
心理的安全性の高い職場環境の視点から中間面談を振り返る | ①チームリーダー、サブリーダーからみた心理的安全性の高い職場であるかを知る ②キャリア形成(効果的なキャリア面談)への関わりを振り返る |
| 第6回 | 3月16日(土) | 43名 | 今年度の取り組みについて共有と意見交換 | キャリア形成支援への取り組みから人材育成能力を高めることができる | 自己のキャリア形成支援への取り組みを評価し人材育成能力を高めることができる |
表3 実習受け入れ実績(基礎教育)
| 学校名 | 日数 | 人数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 国際医療福祉大学看護学部(母性・急性) | 52 | 38 |
| 2 | 足利大学(小児) | 8 | 10 |
| 3 | 栃木県立衛生福祉大学校(小児・母性) | 30 | 42 |
| 4 | マロニエ医療福祉専門学校(助産科) | 5 | 14 |
| マロニエ医療福祉専門学校(通信) | 6 | 5 |
表4 実習受け入れ実績(継続教育)
| 学校名 | 日数 | 人数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 群馬パース大学摂食・嚥下障害認定看護師 | 19 | 2 |
| 2 | 静岡県立がんセンターがん放射線療法看護認定看護師 | 17 | 2 |
| 3 | 岩手県立医大附属病院緩和ケア認定看護師 | 15 | 2 |
| 4 | 順天堂大学小児看護専門看護師 | 1 | 3 |
| 5 | 国立看護大学校小児専門看護師 | 1 | 1 |
6.看護部委員会と検討会
看護部の目標達成に向け、委員会を中心に活動している。次の10の委員会と5つの検討会で以下の活動を行った。
【委員会の活動】
1)研修・看護職キャリア支援委員会
本委員会の目的は「質の高い看護を提供するために看護職員を育成する」であり、以下の3項目の目標を設定し活動を行った。
(1)マネジメント研修【1】【2】【3】の研修評価を行う
今年度はマネジメント研修【2】の企画に、マネジメント研修【3】で実践する管理プロセス(マネジメント・プロセス)の講義内容を追加し、学びが積み上げられるように変更した。マネジメント研修【2】の受講後アンケートから、管理プロセスについて概ね理解できていると評価できた。今年度の受講生がマネジメント【3】を受講するまでには数年かかるため、研修の積み上げの評価は数年かけてみていく必要がある。また、企画内容を変更した際は、指導する側の認識の統一を図ることも課題であると考える。
(2)「家族ケア」「心理ケア」評価の一貫性を確保しながら負担軽減を図るために、評価方法を変更する1事例を委員会全員で評価し、評価結果の意見交換を行い評価の妥当性の検討をしたことで、評価の視点をそろえレポートの評価ができた。この機会は、委員会全体のレポート評価の質向上にもつながると考える。しかし、「家族ケア」「心理ケア」を担当班の負担軽減は図ることができた一方で、他の研修の評価の時期が重なる担当班にとっては、負担増となってしまった。次年度は、各担当班のレポート評価時期を加味して評価の配分をし、委員会全員でのレポート評価を継続する。
(3)特定行為研修の組織定着化支援事業への参画に伴うe-ラーニングの活用の検討
今年度は、看護展開研修【1】フィジカルアセスメントの研修後の学習として7項目を活用した。受講項目は自由選択とし、平均6.9項目/人(最小1項目、最大15項目)の視聴結果であった。次年度は、スキルアップ研修「摂食ケア」4項目、「血糖管理ケア」8項目、看護倫理研修【3】6項目を活用する。
2)看護基準委員会
本委員会の目的は「看護の質を担保するための看護実践の基準を整備する」であり、以下の3項目の目標を設定し、活動を行った。
(1)基準に沿った「IC同席」または「理解納得状況の確認」のIC日の記録割合が80%に上がるように支援をする
「IC同席」の実施数は年々上昇しているが、今年度のIC同席記録率は71.1%から69.8%へと若干低下した。「IC同席」の促進と同時に、IC同席できなかった場合には「理解納得状況の確認」を行い、記録に残すよう働きかけた。しかし、医師との連携やICタグの使用方法なども影響し、IC同席率の課題は継続している。
そのような中、今年度は各部署での取り組みシートを取り入れた。取り組みシートは、各部署の現状把握に役立ち、部署の活動を間接的に働きかける効果はあったと考える。看護部で設定した目標値を達成した部署の割合は25.8%、自部署で設定した目標値を達成した部署の割合は29.0%であった。中間評価から最終評価での記録割合が向上した部署は15部署あり、そのうちの11部署は、取り組みシートの活用で自部署の課題が見え、具体的な取り組みへとつながり、後半のIC同席率の向上に成果が得られていた。
今年度データをみると、医療者側同席基準への該当有のICタグ数、記録件数なども増加しており、IC同席への意識は高まっているといえる。医師のICタグの記録と、看護師の「IC同席」記録が一致した記録として向上させていくためには、医師看護師間の連携が不可欠であり、「IC同席」記録について、看護師が取り決め通りに実施記録を残していくことが重要である。継続的に定期的な周知徹底を繰り返していくことが肝要であると考える。また、「IC同席」「理解納得状況の確認」以外に、意思決定支援に係わる3つの看護用語も「IC同席」実施記録に使用していることがわかった。今後、看護用語の使用の仕方を明確にすることで、IC同席率に反映していけると考える。
今年度、【意思決定支援】基準の見直し・修正を行い、意思決定支援に関する看護基準・手順の見直しがすべて終了した。次年度は改訂した看護基準・手順の周知を通して、更に質の高い「IC同席」が実施できるようにしていく。
(2)目標:看護実践に活用できる看護の手順を整備する
①看護業務基準・手順の改訂
2020年以前の改訂、昨年度改訂した差し戻し、新規作成の基準・手順の全96項目について、改訂作業を行った。このうち46項目の見直しが終了した。次年度は病院機能評価受審のタイミングの関係で145項目の見直しが必要となる。効率よく見直しができるような体制の検討が必要である。
②看護業務基準・手順の活用
活用しやすい看護業務基準・手順の整備として、ポータルサイトの「院内マニュアル」と連動させた。また、閲覧したい基準・手順を簡便に探し出せるように目次を作成し、目次と基準・手順を紐づけた。看護師が看護業務基準・手順を、より活用しやすい環境が整えられたと考える。更に、今回、院内で文書管理システムの閲覧件数を把握する方法があることがわかった。この機能を使って看護業務基準・手順においても閲覧状況の把握ができる可能性がある。閲覧回数から需要がある基準・手順を把握し、より実践に即した基準・手順の改定における優先度を考慮していく。
③中央部門の基準・手順
中央部門(画像診断部・放射線治療部、光学医療センター・内視鏡部)には、看護部と同標記の看護業務基準・手順がある。看護部の基準・手順は検査・治療の実施前と実施後の内容であり、画像診断部や内視鏡部での看護基準・手順は実施中の内容である。基準の目標や方針は異なるが、実施の前・中・後がつながった手順となるのが理想ではないかと考えている。そのためには、中央部門との調整・検討が必要である。文書管理システムの関連コンテンツの活用とともに、看護部の看護業務基準・手順として委員会がどう取りまとめるのか検討が必要である。
(3)看護の質を担保するためのクリニカルパスの作成、見直しを支援する。
4月~6月の看護パスを除いたクリニカルパスのバリアンス件数を出力した。バリアンスの中身を分析したい場合には、患者のIDを出すなど、医療情報部に依頼書を提出すればデータを出力することが可能であることを7月の看護部連絡会議で報告し、活用できるよう支援した。
3)看護研究委員会
本委員会の目的は「看護研究活動の促進を図り、看護研究の質向上のために支援する」であり、以下の2項目の目標を設定し活動を行った。
(1)看護研究相談会の参加者が研究課題の絞り込み・研究背景・テーマを記載できるように支援する。
参加者が臨床疑問から研究疑問を明らかにでき、今後の進め方がわかるように相談会を企画運営した。参加者の思考を整理するために前年度から使用している事前ワークシートを修正した。疑問に思った場面を詳しく記載するように変更し、そこから何が問題なのか、なぜ生じているのかを整理できるように相談会で支援した。
全6回コースで参加率93%であった。参加者12名の進捗に差はあるが、75%が目標達成できた。
(2)看護展開研修【2】において関連する文献を引用し整理・統合して記述できるよう企画・運営する。
昨年度の企画を基に各自のテーマに関連する文献を引用し、整理・統合して記述できるよう企画内容を修正し運営した。評価項目「看護上の疑問を生じた場面においての患者の4側面(身体・心理・社会・スピリチュアル)の情報から、患者をアセスメントし、個別性を捉えた全体像を要約して記述する」「関連する文献を引用し、整理・統合して記述する」について7/10点以上が77.5%であり目標を達成した。また、講義とグループワークを通して「研修の学びは今後に生かせる内容だった」と約90%が回答しており、目標に沿った学びができる企画・運営であった。
4)看護記録委員会
本委員会の目的は「看護の質を担保するために、看護記録の質の向上を図る」であり、以下の5項目の目標を設定し、活動を行った。
(1)看護記録についての理解を深め、看護過程がわかる記録ができる
①1回目の看護記録監査の意思決定支援を除く質評価項目(★印)の委員会評価平均が、3.15以上となり、2回目は1回目よりさらに上昇する。
1回目3.13、2回目3.30であり、0.18上昇した。1回目より2回目に上昇した部署は38部署中19部署であった。
②看護記録監査の意思決定支援項目の委員会評価平均が、1回目より2回目が上昇する。
1回目2.61、2回目2.75であり2回目は1回目より0.14上昇した。1回目より2回目に上昇した部署は30部署中10部署であった。意思決定支援項目の妥当性や、運用上の問題点については次年度の課題とする。
(2)患者アウトカム達成率が一般病棟94%以上、重 症 部 門(ICU、CCU、HCU、PICU、MFICU、NICU、EMC)90%以上となる。
患者アウトカム達成率は一般病棟96.3%、重症部門91.4%であり、目標達成とする。
(3)成果指標達成率が90.1%以上となる。
成果指標達成率は93.4%であり目標達成とする。
(4)標準看護計画の修正・作成等の相談件数が、担当グループごとに2件/年以上となる。
すべての部署において担当委員がフィードバック時に関わり、正しく患者アウトカムが設定できるように支援することができたため目標達成とする。活動内容としては、6部署(8S、7W、6E、ICU、CCU、中央手術部)で、テンプレートを含めた、標準看護計画の修正・作成の支援ができた。また、連絡員の記録に関わる様々な疑問や相談に対して回答を作成した。連絡員が看護記録について迷いなく部署のスタッフへの指導ができるように支援することができた。
(5)看護記録連絡員の活動目標達成率が90%以上となる。
看護記録連絡員の活動目標達成率は84.6%であり、目標未達成とする。活動目標の内容が行動レベルの表現ではなかった部署があり、評価のしにくさが活動目標達成率に差を生じたと考える。次年度は連絡員が目標を立案する時点で助言を行い、行動レベルでの目標設定ができるように支援する。
5)看護業務委員会
本委員会の目的は「効果的、効率的に業務を遂行するための業務改善、職場環境の整備を支援する。タスクシフティング、タスクシェアリングを推進するため、他職種との調整を図る。働き方改革を推進する。」であり、以下の2項目の目標を設定し、活動を行った。
(1)中央部門・外来・重症系部門を除く、全部署にJUNIORS活用に向けた支援ができる。
中央部門・外来・重症系部門を除く24部署が令和5年10月からJUNIORSの活用を開始できるよう、主任看護師研修会でのJUNIORSの説明と活用の紹介、JUNIORS活用に関するQ&Aの再周知、部署担当者による支援を行った。その結果、JUNIORSを活用している部署は18部署、中断した部署は5部署、活用していない部署は1部署となった。活用している18部署に活用の効果を調査した。「JUNIORSの活用がタイムマネジメントに効果的か」の問いに「そう思う」または「ややそう思う」と回答した割合は、活用継続期間が1年以上の部署で87.5%(8部署中7部署)、1年未満で70%(10部署中7部署)であり、長く活用している部署ではよりタイムマネジメントへの効果を感じていることが明らかになった。「JUNIORSの活用は業務調整に効果的か」の問いについて「そう思う」または「ややそう思う」と回答した割合は、活用継続期間が1年以上の部署では87.5%(8部署中7部署)だったが、1年未満の部署では50%(10部署中5部署)だった。残務量が可視化でき業務調整がしやすくなったという意見がある一方で、JUNIORSに反映されない業務の把握やリーダーの調整力の育成が課題となった。JUNIORSを1年以上活用している部署では、導入前(令和3年4月~令和4年6月)と導入後(令和4年7月~令和6年1月)の時間外勤務時間が月平均11時間54分減少した。JUNIORSを活用することはタイムマネジメントの意識づけに寄与したと考える。昨年度の19時までの退勤割合が院内平均より低かった15部署のうち、19時までの退勤割合が上昇した部署は11部署だった。そのうち看護部BSCの目標である60%以上となったのは1部署だった。昨年度と同様の部署が1部署、昨年度より低下した部署は3部署であった。15部署中11部署(73.3%)で目標を達成できた。目標値である「19時までの退勤割合が院内の平均より低かった部署の19時までの退勤割合が前年度よりも増加する」は達成できなかったが、JUNIORSの活用や委員会の働きかけが退勤時間短縮の一助となったと考える。
(2)効果的、効率的に業務を行うための業務改善の支援ができる。
①院内で使用されている氷枕、氷頸の種類の統一、新たなカバーの作成の検討
現在使用されている氷枕、氷頸カバーはサイズがあっておらず、手間を要する状況であった。
院内で使用している氷枕、氷頸の種類を調査し、それぞれ1種類を選定、新たなカバーの作成を行い導入した。
②19時までに退勤できている部署の業務改善や取り組みについて調査し他部署に紹介する
昨年度のBSCの結果から情報収集し、他部署でも活用できる業務改善や取り組みについて検討した。その中から、①入院時オリエンテーションテンプレートの作成と活用、②入院時チェックリストの活用、③業務改善プロセスの簡素化、④セル看護提供方法の試み、の4項目を抽出し、10月の看護部連絡会議で紹介した。①の入院時オリエンテーションテンプレートについては使用数を調査し、2月までに255件の使用があった。しかし、使用数は部署の偏りがあり、周知の方法に検討が必要である。
③診療報酬改定による加算を取得するための体制整備を行う
令和6年度の診療報酬に関する研修を受講した結果、早急に委員会で取り組む課題はなかった。今後も継続して注視していき、必要時に対応する。
④薬剤師へのタスクシフトについて取り組む
薬剤部との協議の結果、現状維持との回答がありタスクシフトについては見送りとなった。
⑤看護用品・医療機器一覧の作成について
看護用品と医療機器の部署間の貸し借りを行いやすくする目的で、有効活用するシステム作りについて検討した。「看護用品・医療機器一覧」「転倒転落予防用具保有一覧」としてJUMP3「エクスプローラー内」の「看護師」に掲載した。今後は記載内容の定期的な見直しが必要である。
⑥輸液ポンプ・シリンジポンプの使用基準作成について
部署により使用する基準は様々であり、ある程度の使用基準が必要であると考えた。他施設の基準を参考に、看護部としての基準を作成した。看護業務基準には記されていないため、今後、看護基準委員会と検討する必要がある。
6)看護情報システム委員会
本委員会の目的は「1.電子カルテ・看護支援システムの円滑な運用を支援する。2.ICT活用促進のための支援をする。3.施設基準に関連するデータを正確に評価できるよう支援する。」であり、以下の3項目の目標を設定し、活動を行った。
(1)現場と連携し、電子カルテ・看護支援システム更新に向けての構築・運用を支援する。
JUMP3構築ワーキンググループで情報共有・検討を行い、システム構築を進めた。現場の困りごとを解決できるように提案し、予定通りシステム更新ができた。
「JUMP2困りごと相談ファイル」を活用し、各部署の相談の対応を行った。1年間の相談件数は35件であった。次期システムへの要望5件にも対応できた。委員会の中で解決できる問題もあり、各部署の意見を吸い上げることができ有効であった。JUMP3に移行した際には、不具合をエクスプローラーの「JUMP3不具合報告」に入力する体制をとったことで、早期から現場の声を吸い上げ対応することができた。「JUMP2困りごと相談ファイル」の取り組みが活かされ、ICTの活用ができたといえる。引き続き、「JUMP3困りごと相談ファイル」で支援していく。
処置マスタについては、確実に効率よく処置オーダー・実施ができるようにマスタの更新を行った。
(2)安全で効率的な看護のために活用できるICTの提案と支援を行う。
目標を「ICT機器(フェリカ・Android)を使用した、体温・脈拍・血圧の測定値入力が50%以上となる」とし、データを正確に入力するためにICT機器を有効利用できるように支援した。フェリカの入力割合の平均は、4月25%、8月38.4%、12月42.7%であり、目標の50%以上は達成できなかったが、近い値まで上昇した。また、入力割合が50%以上の部署は、4月は5部署、8月は10部署、12月は11部署と増加した。50%以上を維持できた部署は5部署であり、50%以上の伸びがあった部署は2部署であった。部署訪問やデータの配付により、4月の段階で使用していなかった部署が使用するようになり、フェリカ使用の意識づけになった。一方で、10%以下の部署が2部署あり、ICT機器活用を推進する意義を理解してもらい、実施率が向上するように次年度も働きかけていく。
(3)重症度、医療・看護必要度の評価方法が理解でき、正確に評価・入力できるように支援する。
新人看護職員への重症度、医療・看護必要度研修を実施した。1回目のテストでは109名中64名が合格し、合格率58.7%であった。昨年度の合格率は46.7%であったため、昨年度と比較し合格率は上昇している。不合格者は2回目のテストで全員合格することができた。正しい評価の知識を得ることが重要であり、テキストを参考にしてテストを受けて良いことを十分に周知できていなかったため、次年度の課題とする。
全職員対象の重症度、医療・看護必要度の研修と連絡員による各部署での周知活動を行った。全職員対象の重症度、医療・看護必要度研修をtotaraで行い、全職員が満点を取得することができた。さらに精度を上げるために、totaraの研修で正答率が60%未満であった設問に対して、各部署で連絡員による勉強会を実施した。連絡員の報告書からスタッフの理解が不十分な点があることが分かり、次年度の研修課題といえる。
7)在宅移行支援委員会
本委員会の目的は「特定機能病院の役割を踏まえた、質の高い退院支援、在宅移行が実践できるよう支援する」であり、以下の3項目の目標を設定し、活動を行った。
(1)在宅移行支援連絡員の活動の支援を行い、退院支援が必要な患者に退院支援を提供する。
①入退院支援加算1と3の算定率37%以上
②退院時「退院支援要」の患者に対する退院支援計画書交付率95%以上
「入院時スクリーニングに関する事例紹介」を作成し、看護職員全員にtotaraの視聴を実施した。
入院時スクリーニングに対しては、Q&A形式の資料を作成し、退院支援の知識を深められるように支援をした。また、加算の算定の低い部署に支援を行った。結果、入退院支援加算1と3の算定率は43.8%、退院時「退院支援要」の患者に対する退院支援計画書交付率は96.4%であった。
(2)在宅療養指導料の理解を深め、算定に結び付く支援を行う
「在宅療養指導管理料に対する在宅療養指導料の割合:入院60%以上 外来8%以上」を目標に活動を行った。「在宅療養指導料について」の資料を作成し、看護職員全員にtotaraの視聴を実施した。また、文書管理システム内の資料の登載の周知をした。結果、在宅療養指導管理料に対する在宅療養指導料の割合は外来が11.8%、入院が59.6%であった。入院は下半期(2023年10月から2月)が71.1%(上半期は53.2%)と上昇した。
(3)在宅療養指導管理料に伴う衛生材料等の知識を深め、適正な材料が選定できるように支援する。
「在宅療養指導料について」のtotara視聴の実施と在宅療養指導管理料に伴う衛生材料等に関する現状把握を行い、「在宅療養管理料該当患者支援フロー」の作成と周知を行い支援した。
8)看護部患者サービス検討委員会
本委員会の目的は「患者満足度の向上を図るため、環境整備や部署支援を行う」であり、以下の3項目の目標を設定し、活動を行った。
(1)他部門と連携して患者の療養環境の改善を図る
今年度は、療養環境が改善されることを目的に「療養環境を整えよう」のポスターを作製し、2か月ごとに4回配付した。スタッフの意識づけになるよう、看護師長にスタッフの目に留まる場所への掲示をお願いした。ポスター掲示の評価は、各部署の主任看護師にアンケートを実施した。アンケートの結果では、【意識づけになった】75%【良い例を見本としたか】40%であった。意見では、収納スペースの少なさに困っていることや係活動として環境整備をしている、ポスターを部署で活用しやすいようにアレンジした、他の場所もポスターで取り上げてほしいなどの意見があり、関心があることは伺えた。ポスター掲示は今後も継続する必要がある。また、入院セットの活用状況について各部署にアンケート調査を行った。その結果をもとに要望をまとめ、改善案を提案し、明恵産業と調整ができた。
(2)患者から信頼の得られる対応ができる看護職員を育成する
「身だしなみチェック表」を他者評価で2回(8・10月)実施した。チェックは19項目あり、2回目が改善している場合を改善ありと判断し、改善率として評価した。改善率は80%あり、身だしなみをチェックすることで意識して改善されていたことが伺えた。しかし、改善率が80%以下の項目は、髪をまとめる・髪のカラーリング・髪が顔にかからない・ネックレスが見えない・ピアスは規定内であった。身だしなみをチェックすることは、看護職員の意識づけになるため、定期的に継続する必要がある。身だしなみチェックを実施した後に行われた患者満足度調査では、服装・身だしなみに関しての患者からの指摘意見はなかった。また、看護師の態度に関する満足度は98.8%であり、昨年度の98.3%から微増であった。高評価を維持できるよう活動は継続する。また、各部署で実施しているBSCの「患者満足の維持・向上」に向けた取り組み実施項目を一覧にまとめ、配付した。
(3)院内の患者サービス検討委員会に協力し、イベントを支援する
開催された院内コンサートは3回(七夕:7月8日 秋:10月19日 クリスマス:12月16日)であった。委員は前日の準備と当日の運営に協力した。4年ぶりの開催となったため、七夕は全員で参加し、秋・クリスマスは半数ずつ協力した。感染対策のためスペースを確保や誘導、見守り、トイレ介助などを行った。来場者のアンケート結果では、3回とも95%以上の満足度が得られた。
9)看護部安全推進委員会
本委員会の目的は「安全な看護業務の推進と、災害対策や感染予防対策が院内で統一して実践できるように支援する」ことであり、以下の3項目の目標を設定し、活動を行った。
(1)適正な身体拘束の実施ができるように支援する
行動制限における看護記録の整備として、テンプレート「行動制限開始」「行動制限カンファレンス」の修正を行った。各部署で実施されている身体拘束が、身体拘束の三原則に適応しているか、基準に沿った適正な身体拘束の実施となっているかを確認するために、監査を実施した。監査結果からは、昨年度より適正に実施されている項目の割合が上昇し、適正な身体拘束の実施の支援ができた。
(2)部署のレベル3以上のインシデント減少の取り組みを支援する
①確実な確認作業のためのダブルチェック方法を確立する
ダブルチェックを行う薬剤等と方法の整備を行った。薬剤等は、インスリン・輸血・麻薬・筋弛緩薬・KCLとした。インスリンは、2人連続型ダブルチェック、他は2人同時双方向型ダブルチェックとして、全部署に周知をした。
②インシデント0レベル報告の活動を支援する
インシデント0レベルの報告が部署でどのように活用されているか、部署訪問にて確認した。困っていることへの助言や他部署の取り組みなどを紹介し、連絡員が工夫して取り組めるよう支援ができた。
③PTPシート与薬方法の知識の習得を支援する
動画視聴と確認テストの実施を提示し、実施率100%であった。今年度のPTPシート誤飲の事故は0件であり、適切な与薬の実践の支援となった。
④リスク感性を高めるためにKYTを実施する
全部署が自部署の特徴に応じた内容で実施しており、日常業務に隠れた危険を予知でき事故を未然に防ぐための取り組みができた。
看護師のインシデントレベル3A以上の報告件数(4~2月)は301件で、昨年度の同時期(314件)と比較するとわずかだが減少している。看護職員の安全な看護実践の支援ができた。
(3)部署で効果的な災害訓練が実施できるよう支援する
①災害マニュアルの確認と災害訓練動画視聴と確認テストの実施を提示し、実施率100%であった。
②災害対策学習会の支援として、各部署で効果的な災害対策学習会が実施できるように、災害訓練シナリオとアクションカードを活用した災害訓練を推奨した。また、減災トレーニング「部署の防火・防災設備を確認しよう」の学習ツールを提供した。災害対策学習会に全看護職員が参加できた。
③「災害時の出勤可能職員名簿」については、電子媒体を使用した方法が実施できるよう、看護部で作成したマニュアルを確認し、運用に向けて取り組んだ。
10)特定行為看護師活動推進委員会
本委員会の目的は「特定行為看護師の育成と活動の推進を図る」であり、以下の2項目の目標を設定し、活動を行った。
(1)特定行為看護師が医療、看護の質の向上に向けた活動と実績が積めるよう支援する
特定行為別にグループ分けをし、委員会でグループ担当者を決めて支援した。今年度より活動シートを導入し、グループ毎に現状の共有や活動評価、活動上の問題点の抽出と対策を講じた。特定行為研修修了者の自立への支援をグループ毎で支援を行い、実践可能な特定行為は32行為となり、実施件数は、3,504件となった。
(2)特定行為看護師の育成を支援する
特定行為看護師研修受講要件を満たすラダーⅢトライ者のラダー研修受講時に広報活動を行った。病棟看護師には特定行為看護師通信を発行し啓発活動に行った。需要の増加している栄養に係るカテーテル管理関連に2名が研修受講した。
特定行為看護師の実績分析を行った結果、栄養に係るカテーテル管理関連、呼吸器(人工呼吸療法に係わるもの)関連、呼吸器(長期呼吸療法に係わるもの)関連、術中麻酔管理領域の育成を重点項目として研修受講者確保に取り組む。
【検討会の活動】
1)固定チームナーシング検討会
本検討会の目的は、「各部署が固定チームナーシング体制を維持し、継続できるよう支援する。」であり、以下の2項目の目標を設定し、活動を行った。
(1)1年間で実践可能な目標設定ができ、チーム目標達成の部署が80%以上になるよう支援する。
リーダー・サブリーダー連絡会を通して固定チームナーシング体制の知識と理解を深め、各部署のチーム目標達成に助力できるように関わった。また、連絡会に参加していない部署で、目標設定や活動方法に戸惑っている部署の相談を、検討会のメンバーが窓口となり支援を行った。
結果、リーダー・サブリーダー連絡会に参加者の自己課題達成度は、平均80.5%で前年度の79.8%を上回った。アンケートの「リーダー・サブリーダーの役割と業務が理解できたか」の問いに、96.4%の人が理解できたと答えた。また、連絡会に参加していない部署を含め、合計36件部署への相談対応や声かけ・助言など、目標設定や活動への支援を行った。その結果、チーム活動が計画的に進行し且つチーム目標を達成したチームは、全部署89チーム中84チーム(94.4%)であった。チーム活動が途中計画通りにいかないことがあったが、チーム目標を達成できた5チームを含めると、今年度は全チームがチーム目標を達成できた。
(2)固定チームナーシングチェックリストが適切に活用されるよう介入することで、固定チームナーシングの体制が維持され、質の高い看護につながるよう支援する。
①項目No.12(昨年同様)「受け持ち看護師の役割と業務を理解し実践している」にしぼり、△評価の理由などの詳細を確認し、介入することで、項目No.12 の2回目評価の結果が、1回目より×、△が減少する。
②項目No.8「部署の組織図を理解している」に関して、第1回固定チームナーシングリーダー・サブリーダー連絡会で参加者の持参したホームワークシートの組織図を確認する。
上記の2つに重点を置いて活動を行った。
結果は、1年間2回のチェックリストの評価のうち、No12の5項目の結果は「×」の割合が2.7%から5.4%へ悪化し、「△」は9.2%から4.3%に減少がみられた。「〇」の割合は1回目が80.0%で2回目は84.9%に上昇があった。「×」は2部署が5項目全てを「×」評価にし、うち1部署は1回目評価時に「該当なし」の評価であった。チェックリストが2回目に改善がなかった部署の詳細確認と、外来部門における受持ち看護師の設定や看護計画立案に関して、今後も注視していく。また、項目8については、リーダー・サブリーダー連絡会での確認ができ、特に問題はなかったことが確認できた。
(3)院内成果発表の企画運営と、院外発表の支援を行っているが、今年度は院外発表をした4演題(全国・関東発表会各2演題)をtotaraに登載することを新たな試みとして企画した。
目的は、「固定チームナーシング体制におけるチーム活動(チーム目標達成のための小集団活動)の実践報告を共有する。また、院外発表の参考例とする。」として、2024年1月末から視聴できるようになり周知した。totara登載の評価は次年度の課題とする。
2)専門・認定看護師活動検討会
本委員会の目的は「附属病院の看護の質向上のため、専門性を高めて、自己ならびに相互の研鑽を図る」であり、以下の2項目の目標を設定し、活動を行った。
(1)看護の質の向上につながるように専門・認定看護師の活動支援を行い、昨年度よりも相談件数と指導件数が増加する。
①活動内容
専門・認定看護師に関連する院内の課題を抽出し、関連領域を踏まえて専門・認定看護師を8つのグループ(アピアランスケアグループ、がん患者指導管理料(イ)算定グループ、緩和ケアリンクナース育成グループ、早期栄養管理加算算定グループ、SAT/SBTグループ、術後疼痛管理グループ、小児・母性看護グループ、人材育成グループ)に分け、意見を吸い上げながら活動を行った。
専門・認定看護師の個人の活動計画に相談件数と目標件数の目標値を設定し、取り組んだ。指導・評価は所属部署の看護師長に依頼した。
②結果
2023年度の相談件数は1,459件、指導件数は268件(2023年:相談件数1,433件、指導件数203件)で昨年度より増加し目標は達成した。
グループ活動の概要及び実行率と目標達成率は下記の通りである。
- <アピアランスケアグループ>
アピアランスケアの実施状況を調査し、部署間の差異なく情報提供できるよう資料の作成等を実施した。また、人材育成としてアピアランスケア研修会(基礎編)の受講者2名を確保した。プロセス実行率、目標達成率ともに100%であった。 - <がん患者指導管理料(イ)算定グループ>
がん患者指導管理料(イ)の算定件数103件/月以上を目標に、がん領域の専門看護師・認定看護師で調整し、効率的に隙間なくIC同席者を確保できるよう担当表を修正した。担当表の修正時期が下半期になったためプロセス実行率は40%であったが、下半期の件数増加が認められており目標達成率は93%であった。 - <緩和ケアリンクナース育成グループ>
緩和ケアリンクナースが挙げた目標達成率の上昇:80%以上の部署で目標達成できるよう、緩和ケアリンクナース連絡会の開催や個別の相談対応などを行いプロセス実行率は100%であった。しかし、緩和ケアリンクナースが挙げた目標を達成できたのは、16部署中10部署で目標達成率は62.5%であった。 - <早期栄養管理加算算定グループ>
ICUの早期栄養管理加算の取得の推進と栄養管理内容の見直し、CCUの早期栄養管理加算取得の推進に取り組んだ。ICUでの加算算定額は1月末で5,959、500円、CCUは7月から加算取得を開始し、1月末で3,439,000円であり、プロセス実行率及び目標達成率はともに100%であった。栄養剤も同等の質で低コストの物に変更した。
HCUでの早期栄養管理加算の取得については、管理栄養士と加算取得要件の確認・調整に取り組み、プロセス実行率30%、目標達成率80%であった。次年度も取り組みを継続する。 - <SAT/SBTグループ>
ICU・CCU・HCU・EMCの4部署におけるSATとSBTの加算算定の推進に取得に取り組んだ。4部署併せてSATの算定件数は2,750件、SBTの算定件数は2,750件でプロセス実行率及び目標達成率は100%であった。SAT・SABの質的評価と対応が今後の課題である。 - <術後疼痛管理グループ>
術後疼痛管理チーム加算対象者の取得率100維持、整形外科のPOMVに関するCP変更、腎臓外科および口腔外科におけるレスキュー使用料の減少、7A、5A、5B病棟での勉強会実施と参加者の確認テスト正解率80%以上を目標に当該部署の医師・看護師と連携し取り組んだ。プロセス実行率100%であったが、腎臓外科および口腔外科におけるレスキュー使用料の有意な減少は得られず目標達成率は93.3%であった。 - <小児・母性看護グループ>
「母性小児分野の連携における家族支援の強化」に取り組み、勉強会の開催や周産期母子医療センター看護カンファレンスの取り決め事項の作成などを行った。プロセス実行率及び目標達成率は95%であった。 - <人材育成グループ>
目標(2)に同じ。
③課題
- 緩和ケアリンクナースのリンクナースの協力を得て、病棟における緩和ケアの質を上げるための活動を行う
- 術後疼痛・PONVの活動対象について小児整形外科に拡大することを検討する。
- SAT/SBTの実行率だけでなく質的評価の実施を検討する
- 看護外来の整備・調整を行う
- 母性小児領域の連携の強化として、介入事例の可視化に取り組む。また、子ども医療センターの看護上の課題に関するスタッフ教育を推進する。
(2)令和5年度の認定看護師養成校への入校者を3名以上確保する
①活動
優先領域:認知症看護、腎不全看護、皮膚排泄ケア、糖尿病
関連する認定看護師より推薦者を募り、所属部署の看護師長に推薦や支援など協力を依頼した。また、院内看護研究発表会で認定看護師2名に自分自身のキャリ形成と認定看護師としての活動について発表してもらい、totaraで視聴できるようにした。
②結果と課題
2024年度の認定看護師養成学校への入校者は6名(クリティカルケア看護、慢性呼吸不全看護、脳卒中看護、認知症看護、皮膚排泄ケア、生殖看護)確保できた。しかし、優先領域の糖尿病看護と腎不全看護は確保できなかったため、取り組みを継続する。
3)地域実践研修支援検討会
本検討会の目的は「地域実践研修において研修者が課題を達成できるように支援する」であり、以下の2項目の目標を設定し、活動を行った。2023年度の地域実践研修者(派遣者)は、日光市民病院7名(うち出向管理者1名)、那須南病院4名、西吾妻福祉病院3名、とちぎメディカル医療センターしもつが5名(うち出向管理者1名)、茨城県西部メディカル医療センター5名の計24名である。
(1)研修者が計画的に自己課題に取り組めるように支援する
研修者は、地域実践研修および所属部署の目標に沿った個人目標をそれぞれ1~2個ずつ設定している。目標の評価は、例年A、B、C評価としていたが、最終評価は、達成率(%)でも評価を行った。最終評価は、2月に実施し、地域実践研修の目標に関しては、A評価73%、B評価27%、達成率87%だった。所属部署の目標に関しては、A評価83%、B評価17%、達成率88%だった。
検討会の支援としては、初回面談時に目標設定の助言を行い、中間面談では後期に向けた課題が明確になるように助言した。次年度も研修を継続するスタッフに対しては、最終面談を行い、今年度の評価と次年度の課題を導き出すことができた。また、研修施設の管理者との指導者会議では、研修者の目標や取り組み状況を共有しながら研修者の目標を達成できるように支援できた。さらに、研修施設の看護部長との責任者会議では、研修者の受け入れ体制や研修施設が独自に企画する研修内容について情報交換する場を設けることができた。研修施設と当院がお互いに共益関係が構築でき、地域実践研修の充実が図れるように連携を図っていく。
(2)ラダー研修の課題に対する支援の在り方を検討する。
近年、ラダー研修の受講者が増加傾向にあり、ラダー研修の課題に対する支援の方法を検討した。研修施設に当院の管理者がいない場合は、ラダー研修の課題の支援を当院の担当者が行っている。助言するにあたりメールのやりとりだけでは伝達が困難なため、次年度以降はZOOMを利用することとした。ラダー研修の課題は、自部署での活動であることが多いため、研修施設の協力も不可欠である。研修施設でラダー研修の課題の相談や支援が受けられているか等を確認し、ラダー研修が受講しやすい環境の調整を行うことが検討会の課題である。
4)臨床実習指導検討会
本検討会の目的は、「臨床実習が効果的に行われるよう実習環境を整える」である。新型コロナ感染症が第5類となって以降も感染対策に留意し、安定して実習ができるように、目標を「臨床指導者が自己の目標を達成できるように支援する」、評価指標を「目標達成率80%以上」と設定し、以下の活動を行った。
(1)新規実習指導者が役割を理解し、スムーズに実践できるように支援する
4月に任命式を行い、学生の状況、臨床実習指導者の役割、臨床実習指導自己評価票の活用方法、臨床実習の具体的な進め方を説明し動機づけを行った。また、8月にワークショップを開催し、臨床指導者に必要な社会人基礎力について講義と演習を行った。演習では、自己の傾向や課題を理解したうえで、臨床指導者としての役割発揮や目標達成に向けた取り組みができるよう支援した。参加者は57名(経験者33名、新規実習指導者24名含む)で全体の58.1%であった。全員が「臨床実習指導者の役割を理解した」「社会人基礎力について理解を深めることができた」「社会人基礎力を踏まえて自己の課題を見出すことができた」と回答した。さらに、自由記載では「社会人基礎力を学生が身につけるためには、臨床指導者がロールモデルになる必要があることを理解できた」「自分の弱みが明確になり、どのように対応したらよいかイメージできた」との回答があった。
(2)臨床実習指導取り組みシートを活用し、役割達成ができるよう支援する
4月の任命式で「臨床実習指導取り組みシート」の活用方法について説明し、年度初めから自己課題に取り組み、役割発揮できるよう促した。8月のワークショップで、「臨床実習指導自己評価票」「臨床実習指導者役割達成のための取り組みシート」を各自が持参し、自己の課題を再確認した。自己の課題に対しての達成度は、平均値81.9%(前年79.5%)であり、目標は達成できた。また、「臨床実習指導者役割達成のための取り組みシート」には、目標達成に向けて実施した活動が記述されており、次年度に向けた新たな課題を見出している実習指導者もいた。
5)看護補助業務体制検討会
本検討会の目的は「看護補助員、病棟クラーク、メッセンジャー等の看護補助業務者の教育指導を企画・運営し、看護補助業務の質を高める」であり、以下の2項目の目標を設定し活動を行った。
(1)看護補助員・病棟クラークの集合研修を企画し実施する。
令和5年度は看護補助員・病棟クラークそれぞれに対して研修を企画し実施した。
①看護補助員対象の研修目的は「移乗に関するKYTを通して、安全に移乗を行うための知識・技術を習得することができる」、研修目標は「移乗介助に潜む危険に気づくことができる」「安全に関するルールが理解できる」とした。KYTとシミュレーションの手法を用い、3回開催し合計98名が参加した。受講後のアンケートの結果では、約98%の受講生が研修内容を理解し、実践に活かせそうだと回答していた。
②病棟クラーク対象の研修目的は「医療チームの一員としての接遇のスキルを活かし、困難事例への対応を考える」、研修目標は「接遇の5つの基本を理解できる」「自分自身の接遇に関して振り返りができる」「困難事例への対応を考えることができる」とした。講義とロールプレイの手法を用い、3回開催し合計42名が参加した。受講後のアンケート結果では、100%の受講生が研修内容を理解し、実践に活かせそうだと回答していた。
(2)2023年度看護補助員充実加算の算定の支援をする。
①「看護補助者の活動推進のための看護職員研修」を実施する。
看護職員研修に使用する資料を作成した。「看護チームにおける業務のあり方」をtotaraに掲載した。全看護職員が予定通り研修を受講した。
②各部署の体制整備を支援する。
看護補助員への直接ケアの指示と看護補助員の実施の記録について資料を作成し、周知をした。
日本看護協会出版「2021年度改訂版看護チームにおける看護師・准看護師及び看護補助者の業務のあり方に関するガイドライン及び活用ガイド」と自治医科大学附属病院看護師業務マニュアルを基に、看護補助員業務マニュアルと看護補助業務経験票の新規作成および改正を行い、該当部署へ配付した。
各病棟における看護補助員の直接ケア実施状況を調査した。次年度の看護補助員集合研修企画の参考とする。
(3)今後の課題
看護補助体制充実加算の算定を継続できるよう、「看護補助員の活用促進のための看護職員研修」等、各部署の体制整備支援を継続する。令和6年度診療報酬改定に関連した、看護職員および看護補助者の業務分担・協同を推進する。
7.専門看護師の活動
専門看護師は、「複雑で解決困難な看護問題を持つ個人、家族及び集団に対して水準の高い看護ケアを効率よく提供するための、特定の専門看護分野の知識・技術を深めた専門看護師を社会に送り出すことにより、保健医療福祉の発展に貢献し併せて看護学の向上をはかること」を目的とした日本看護協会が定める制度である。当院の専門看護師の分野別人数を表1に示す。専門看護師の役割は「実践」・「相談」・「調整」・「教育」・「研究」・「倫理調整」の6つであり、2023年度の各分野における活動は以下の通りである。
表5 専門看護師の分野と人数(2024年4月1日現在)
| 専門看護師の分野 | 人数 |
|---|---|
| がん看護 | 5名 |
| 急性・重症患者看護 | 6名 |
| 小児看護 | 3名 |
| 母性看護 | 1名 |
| 合計 | 15名 |
1)がん看護
(1)院内活動
- 外来治療センター内でがん化学療法看護認定看護師・がん性疼痛看護認定看護師とともに看護師外来を運営
- 多職種カンファレンス参加
- 外来治療センターカンファレンス 毎日
- Cancer Board Conference 月1回
- 緩和ケアチームカンファレンス 週1回
- 泌尿器科ケースカンファレンス 週1回
- 妊孕性温存ケースカンファレンス 2回/年
- 骨転移ボードカンファレンス 不定期
- がん相談支援センター兼務
- がん看護外来の運営
- がん放射線療法看護認定看護師とともにリンパ浮腫看護外来(下肢)の運営
- がんゲノム医療部構成員 がんゲノム医療部会参加 年間4回
- 新人看護職臨床研修 看護基礎技術研修 講師
- ラダーⅣトライ研修 看護展開研修【4】アドバイザー 5件
- がん患者指導管理料イ算定 351件
- がん患者指導管理料ロ算定 108件
- リンパ浮腫複合的治療料(重症の場合)109件、リンパ浮腫複合的治療料(重症以外)4件
- 緩和ケアチーム専従看護師緩和ケア診療加算1,944件、外来緩和ケア管理料100件
- 緩和ケアリンクナース運営
- 緩和ケアリンクナース部署別勉強会 2件
(2)院外活動
- 栃木県立衛生福祉大学校非常勤講師「病いと共に生きる看護」講義
- 看護師特定行為研修センター研修指導補助者
- 自治医科大学看護学部「がん看護学」講義
- 自治医科大学看護学部「成人看護学Ⅱ」講義
- 下野市医療介護連携事業に基づく社会福祉部会への協力(エンディングノート作成内容検討)
- 栃木県看護協会一般研修「がん看護における緩和ケア」講義
- 栃木県緩和ケア研修会 ファシリテーター
- 関越がんサポーティブケア研究会世話人
- がん就労支援Web Seminar Lecture 座長
- 3rd B-FLAT講師
- Colorectal Cancer Web Seminar~実臨床から学びを深める~講師
- 第11回ELNEC-Jコアカリキュラム看護師教育カリキュラムinとちぎ講師
- 栃木県看護協会Ⅰ・Ⅱ領域研修「地域包括ケアシステムにおける看護師の活動」講師
- 自治医科大学看護学部「多職種連携論Ⅰ」講義
(3)実習受け入れ
- 国立がん研究センター中央病院がん放射線療法看護認定看護師教育課程実習における退院支援部門の見学(令和4年11月16日)
- 岩手医科大学附属病院高度看護研修センター緩和ケア認定看護師教育課程緩和ケア病棟実習
(4)学会参加
- 第38回日本がん看護学会
- 第10回日本CNS看護学会
- 第27回日本緩和医療学会学術大会
- 第4回日本緩和医療学会関西支部学術大会
- 第27回日本在宅ケア学会学術集会
- 第61回日本癌治療学会学術集会
- 第21回臨床腫瘍学会
(5)研究活動
- 本真由美,玉木秀子,矢吹みどり他:がん臨床試験における患者の意思決定支援のための学習プログラムに参加した大学病院の看護師の学びの内容,第38回日本がん看護学会学術集会,2024(口演発表)
- 矢吹みどり,玉木秀子,山本真由美他:がん臨床試験における患者の意思決定支援のための学習プログラム開発―大学病院の看護師に対する実施評価―,第38回日本がん看護学会学術集会,2024(口演発表)
- 小島千恵美,中濱洋子,藤原紀子,吉村健一,玉木秀子,矢吹みどり,山本真由美他:がん臨床試験における患者の意思決定支援のための学習プログラム開発―がん専門病院の看護師に対する実施評価―,第38回日本がん看護学会学術集会,2024(口演発表)
- 小島千恵美,中濱洋子,藤原紀子,吉村健一,玉木秀子,矢吹みどり,山本真由美他:がん臨床試験における患者の意思決定支援のための学習プログラムに参加したがん専門病院の看護師の学びの内容,第38回日本がん看護学会学術集会,2024(口演発表)
- 皆川麗沙,櫻木雅子,小嶋理恵子,他:多職種・地域連携で支えた高齢乳癌患者の一例,第30回日本乳癌学会学術総会,2023(示説発表)
- 柴絵美,皆川麗沙:広汎子宮全摘術後の排尿訓練新基準の有用性の検証,第22回栃木県看護学会学術集会,2023(口演発表)
- 森貴子,飯塚由美子,小嶋理恵子他:「リンパ浮腫看護外来」の開設の取り組み,第38回日本がん看護学会学術集会,2024(口演発表)
- 飯塚由美子,森貴子,小嶋理恵子:リンパ浮腫に対する外科的治療を受ける患者の看護支援「―国内文献レビューからの検討―」,第38回日本がん看護学会学術集会,2024(示説発表)
- 山本理栄,皆川麗沙,飯塚由美子他:ReportoftheCancerSalonatJichiMedicalUniversityHospital-the9threportRieYamamoto(MentalHealthCareCenter,JichiMedicalUniversityHospital)自治医科大学附属病院がんサロンの活動続報―第9報―山本理栄(自治医科大学附属病院こころのケアセンター),第21回臨床腫瘍学会,(2024)示説発表
2)急性・重症患者看護
(1)院内活動
- 看護職キャリア支援センターメンバー(プログラム部門)
- ラダー研修:看護展開Ⅱ研修「フィジカルアセスメント2」企画運営
- 看護基礎技術研修:「救命救急」の企画運営
- 新入職医師に対するBLSプロバイダーコース開催6回
- 医療機器安全管理部会メンバー
- 院内急変時ワーキンググループメンバー
- 一般病棟看護師対象勉強会 10件
- 専門・認定看護師活動検討会メンバ
- 急性疼痛管理チームメンバー
術後疼痛管理チーム加算取得(2023年1月~12月)5,396件、5,396,000円 - 早期離床・リハビリテーションチームメンバー
早期離床・リハビリテーション加算取得(2023年4月~2024年1月)
ICU:2,669件、13,345,000円
HCU:2,357件、11,785,000円 - 早期栄養介入管理加算チームメンバー
ICU早期栄養介入管理加算(経腸栄養) 563件、2,252,000円
ICU早期栄養介入管理加算 1,483件、3,707,500円(2023年4月~2024年1月)
CCU早期栄養介入管理加算(経腸栄養) 456件、1,824,000円
CCU早 期 栄 養 介 入 管 理 加 算 646件、1,615,000円(2023年7月~2024年1月) - 院内人工呼吸器管理安全対策チームメンバー
呼吸ケアチーム加算取得(2023年4月~2024年2月) 27件、40,500円 - ラダーⅣトライ者研修看護展開研修【4】アドバイザー
(2)院外活動
- メディカル情報サービス 看護師教育セミナー「院内急変時の初期対応」講師
- 自治医科大学大学院看護学研究科 「フィジカルアセスメント特論」講師
- 自治医科大学看護学部 「成人実践看護学Ⅱ」講師
- 自治医科大学看護学部 「災害学」講師
- 自治医科大学看護学部 「多職種連携論」講師
- 獨協医科大学大学院看護学研究科 「フィジカルアセスメント」講師
- 東京慈恵会大学大学院医学研究科看護学専攻「クリティカルケア看護学演習Ⅳ」講師
- 日本集中治療医学会集中治療看護師委員会
- 日本クリティカルケア看護学会 理事および評議員、査読員
- 日本クリティカルケア看護学会 せん妄ケア委員会 委員
- 日本呼吸療法医学会 理事および評議員、査読員
- 日本手術医学会 教育委員
- 日本手術医学会 評議員
- 日本小児麻酔学会 評議員
- 日本手術看護学会 査読員
- 日本術後痛学会 評議員
- 日本臨床救急医学会 評議員
- 日本救急看護学会倫理委員会 委員
- 日本救急看護学会 評議員
- 日本救急医学会関東地方会 評議員
- 北関東救急看護研究会 副会長
- AHA BLSファカルティ
- PTEC地域世話人
- 第19回日本クリティカルケア看護学会学術集会座長(シンポジウム、交流集会)
- 第19回日本クリティカルケア看護学会学術集会パネリスト
- 第45回日本呼吸療法医学会学術集会座長(パネル、優秀演題セッション)
- 日本看護学会学術集会抄録選考委員
- 栃木県看護協会研修会 クリティカルな状況における患者家族の意思決定支援 講師
- 栃木県看護協会研修会 災害支援ナース養成研修講師
- 第54回日本看護学会学術集会座長(一般演題)
- 千葉県臨床工学技士会主催第13回人工呼吸セミナー 講師
- 日本クリティカルケア看護学会 せん妄ケアセミナー 講師
(3)実習受け入れ
なし
(4)学会参加
- 第25回日本救急看護学会学術集会
- 第26回日本臨床救急医学会総会・学術集会
- 第74回日本救急医学会関東地方会学術集会
- 第19回日本クリティカルケア看護学会学術集会
- 第51回日本集中治療医学会学術集会
- 第45回日本呼吸療法医学会学術集会
- 第54回日本看護学会学術集会
- 第37回日本手術看護学会年次大会
- 第43回日本看護科学学会学術集会
- 第10回日本CNS看護学会
- 第45回日本手術医学会総会
- 第23回 栃木看護学会学術集会
(5)研究発表
- 谷島雅子:Prac tice o f Nurse Education inTrauma Surgery Simulation,The 6th World TraumaCongress(第6回世界外傷学会 口演発表)
- 加藤翠,三須侑子,茂呂悦子:ICUに緊急入室し人工呼吸管理を受けた患者家族の経験―ICU入室中から退室後まで―,第19回日本クリティカルケア看護学会学術集会,2023.(口演発表,共同演者)
(6)執筆
- 茂呂悦子:クリティカルケアのやりがい,重症集中ケア,122(4),2023.
- 茂呂悦子:ICUレジデントブック 臓器管理Ⅲ臓器障害の管理 せん妄に対する看護ケア,メジカルビュー社,p.253-254,2023.(分担執筆)
- 福田侑子:ICUレジデントブック 臓器管理Ⅱ(治療編)ICUインターベンション 鎮痛・鎮静(非薬物的アプローチ),メジカルビュー社,p.186-189,2023.(分担執筆)
- 三須侑子:救急・ICUナースのための家族ケア特殊状況における家族ケア 終末期の面会ができない状況にある家族へのケア、メディカ出版、p.140-146、2024.(分担執筆)
3)小児看護
(1)院内活動
- 院内の看護師と小児に携わる専門職を対象とした勉強会企画・運営 1件
病棟対象の勉強会の講師 3件
ラダーⅣトライ研修 看護展開【4】看護研究アドバイザー 8件
(2)院外活動
- とちぎ小児看護研究会 監事・事務局
- 第32回日本外来小児科学会年次集会 ワークショップ 企画運営
- 栃木県小児慢性特定疾病児童等ビアサポート事業
- 栃木県小児委託小児在宅医療体制構築事業
- 認定看護師教育課程 小児プライマリケア分野 教育会委員
- 大阪公立大学大学院看護学研究科 小児看護学援助特論3 講師
- 認定看護師教育課程 小児プライマリケア分野 医療的ケア児への看護 講師
(3)実習受け入れ
- 順天堂大学大学院博士課程前期 専門看護師課程小児看護学実習
- 国立看護大学校研究課程部 小児看護専門看護師教育課程 成看護学実習A-Ⅲ実習
(4)学会参加
- 第33回日本小児看護学会学術集会
- 第10回日本CNS学会学術集会
- 第32回日本新生児看護学会学術集会
- 第51回日本小児神経外科学会
- 第43回日本看護科学学会学術集会
- 第70回日本小児保健協会学術集会
- 第33回日本小児整形外科学会学術集会
- 第32回日本外来小児科学会年次集会
(5)研究発表
- 川中子知里,川上直子,黒田光恵他:小児看護専門看護師による看護師へのサポートの評価.第10回日本CNS看護学会学術集会 示説発表
- 佐藤ひさ代,金田陽子,川中子知里他:小児・母性の連携による家族看護-小児・母性領域CN・CNSの協働企画の勉強会-.第10回日本CNS看護学会学術集会 示説発表(共同演者 川上直子,黒田光恵)
- 黒田光恵,中田悠喜,渡邉英明他:ペルテス病の子どもの生活の実態調査(第2報)-保・幼稚園と学校生活に関する保護者へのアンケート調査ー.第34回日本小児整形外科学会学術集会 口頭発表
- その他,学会発表 共同演者 4件
(6)雑誌等の執筆
- 中田悠喜,黒田光恵,滝直也他:ペルテス病の子どもの生活の実態に関するアンケート調整(第1報),日本小児整形外科学会雑誌,32(2),p157-163,2023.(共同執筆者)
- 厚生労働科学研究費補助金難治性疾患政策研究事業 遺伝性白質疾患・知的障害をきたす疾患の診断・治療・研究システム構築班:希少神経難病・知的障害の成人移行支援の手引き ‐ 遺伝性白質疾患を含む,診断と治療社,2023.(共同執筆者)
- 小林京子:新体系 看護学全書 小児看護学② 健康障害をもつ小児の看護 第7版,メジカルフレンド社,2023.(共同執筆者)
4)母性看護
(1)院内活動
- NCPR Aコース3回・Sコース3回開催
- 母性小児領域勉強会 1回開催
- 産科母体救急に関する勉強会 2回開催
- 産科妊婦への支援に関する勉強会 1回開催
- 妊娠期ケア103件、分娩時ケア32件 産褥ケア5件、家族ケア2件、地域連携2件その他21件
(2)院外活動
- 栃木県助産師会 勤務助産師部会長
- 第48回 栃木県母性衛生学会 査読
- 日本母性看護学会 GDMセミナー部会委員
- NCPR インストラクター
- J-CMELS インストラクター
- 栃木県看護協会 助産師相互研修 講師
(3)実習受け入れ
自治医科大学大学院 看護学研究科 博士前期課程母性看護学領域
(4)学会参加
- 第10回 日本CNS看護学会
- 第79回 日本助産師学会
- 第39回 日本糖尿病・妊娠学会年次学術集会
- 第48回 栃木県母性衛生学会
(5)研究発表
- 佐藤ひさ代ら:小児・母性の連携による家族看護―小児・母性領域のCN・CNSの協働企画の勉強会―,第10回日本CNS看護学会,2023(ポスター発表)
(6)執筆
なし
8.認定看護師の活動
認定看護師は、「特定の看護分野において、熟練した看護技術及び知識を用いて、水準の高い看護実践のできる認定看護師を社会に送りだすことにより、看護現場における看護ケアの広がりと質の向上を図ること」を目的とした日本看護協会による制度である。認定看護師の役割は、「実践」・「指導」・「相談」の3つであり、各分野と人数は表6に示す通りである。
表6 認定看護師の分野と人数(2024年4月1日現在)
| 認定看護師の分野 | 人数 |
|---|---|
| 緩和ケア | 2名 |
| がん性疼痛看護 | 2名 |
| 乳がん看護 | 1名 |
| がん放射線療法看護 | 1名 |
| 皮膚・排泄ケア認定看護 | 2名 |
| 糖尿病看護 | 1名 |
| 透析看護 | 1名 |
| 摂食・嚥下障害看護 | 3名 |
| 集中ケア認定看護師・クリティカルケア認定看護 | 3名 |
| 救急看護 | 1名 |
| 手術看護 | 2名 |
| 新生児集中ケア | 2名 |
| 小児救急看護 | 1名 |
| 感染管理 | 3名 |
| 合計 | 25名 |
1)緩和ケア
(1)院内活動
- 部署別勉強会開催 2件
(2)院外活動
- 栃木県緩和ケア研修会 講師・ファシリテーター
(3)実習受け入れ
岩手医科大学附属病院 高度看護研修センター 緩和ケア認定看護師教育課程 実習生2名
(4)学会参加
第28回 日本緩和医療学会学術大会
(5)研究発表
なし
(6)執筆
なし
2)がん性疼痛看護
(1)院内活動
- がん患者指導管理料イ加算算定 139件
- 勉強会開催(疼痛コントロール・がん患者の理解)2件
- 緩和ケアリンクナース連絡会企画運営 年3回開催
- がん患者 苦痛緩和のための病棟ラウンド 月2回
(2)院外活動
なし
(3)実習受け入れ
なし
(4)学会参加
- 第28回日本緩和医療学会
(5)研究発表
なし
(6)雑誌等の執筆
なし
3)乳がん看護
(1)院内活動
- 乳がん勉強会開催 2件
- 告知時支援 22件
- 意思決定支援 244件
- 治療継続支援 19件
- ボディイメージ変容の支援 19件
- リンパ浮腫支援 216件
- リハビリ支援 1件
- 家族ケア 3件
- 在宅療養支援 6件
- その他 0件
- がん患者指導管理料(イ) 217件
- がん患者指導管理料(ロ) 194件
- リンパ浮腫複合的治療料(重症) 202件
- リンパ浮腫複合的治療料(重症以外) 17件
- 相談 7件
- 指導 1件
(2)院外活動
- 第29回栃木ブレストケア研究会 講師
- Lilly Breast Cancer Web Conference多職種連携乳癌治療の会 講師
(3)実習受け入れ
なし
(4)学会参加
- 第31回日本乳癌学会学術総会
- 第38回日本がん看護学会学術集会
- 第19回日本乳癌学会関東地方会
- 第33回日本乳癌検診学会学術集会
(5)研究発表
なし
(6)執筆
なし
4)がん放射線療法看護認定看護師
(1)院内活動
- 看護実践 (放射線療法オリエンテーション、有害事象ケア、治療継続支援) 689件
リンパ浮腫看護外来(下肢)担当 138件
リンパ浮腫複合的治療料加算算定(重症132件、重症以外4件)
がん患者指導管理料(イ) 265件 - 有害事象ケアについての相談 7件、指導 26件
- リンパ浮腫ケアコンサルト 18件
- カンファレンス参加(放射線治療計画カンファレンス、放射線科・耳鼻科合同カンファレンス、放射線科・口腔外科合同カンファレンス、口腔外科病棟多職種カンファレンス、キャンサーボードカンファレンス、耳鼻科病棟放射線療法看護カンファレンス)
- 放射線療法看護勉強会/見学会 1回
(2)院外活動
- 自治医科大学看護学部「成人実践看護学Ⅲ」講師
- 第41回診療放射線技師研修会 講師
- 栃木県緩和ケア研修会 ファシリテーター
- 第25回日本放射線腫瘍学会小線源治療部会学術集会 座長
(3)実習受け入れ
- 静岡県立静岡がんセンター認定看護師教育課程(がん放射線療法看護)臨地実習
(4)学会参加
- 第36回日本放射線腫瘍学会学術大会
- 第38回日本がん看護学会学術集会
(5)研究発表
- 第38回日本がん看護学会学術集会「リンパ浮腫看護外来」の開設の取り組み
(6)執筆
なし
5)皮膚・排泄ケア認定看護師
(1)院内活動
- 褥瘡予防ケア 5,066件
- 褥瘡ハイリスク患者ケア加算算定 3,765件
- 褥瘡処置 363件
- 創傷処置 128件
- 瘻孔ケア 18件
- 失禁ケア 140件
- ストーマケア 949件
- ストーマサイトマーキング 117件
- 意思決定支援 34件
- ストーマ外来受診患者数 835件
- コンサルテーション 827件
- 院内勉強会開催 3件
- 褥瘡対策委員会
- 褥瘡対策チーム
- 褥瘡回診(ハイリスク)
- 二分脊椎カンファレンス
- ストーマ連絡会
- 排尿自立支援チーム回診
- 経肛門洗腸療法指導
- 新人看護職員臨床研修 看護基礎技術研修「褥瘡予防」企画運営
(2)院外活動
- 日本褥瘡学会評議員
- 栃木ストーマリハビリテーション講習会実行委員
- 栃木ストーマ研究会幹事
- 栃木県オストミー協会講習会 講師
- コロプラスト株式会社 WEBセミナー講師
- アルケア株式会社 研修会講師
- 株式会社ホリスター ダンサック事業部 WEBセミナー講師
- 自治医科大学看護学部老年看護学 講師
- 老人施設 勉強会講師
(3)実習受け入れ
- 看護師特定行為研修生 演習サポート
(4)学会参加
- 第25回 日本褥瘡学会(WEB)
- 第32回 日本創傷・オストミー・失禁管理学会(WEB)
- 第41回 日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会
- 栃木県ストーマ研究会
(5)研究発表
- 田口深雪:低位前方切除術後症候群に対する対策と治療~多職種協働の重要性~,第41回日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会総会,2024(共同演者)
(6)執筆
- 株式会社ホリスター ダンサック事業部 ストーマ症例報告
6)糖尿病看護
(1)院内活動
- 在宅療養支援(注射・血糖自己測定含む) 1,360件
- フットケア実施 30件
- 家族ケア 1件
- 外来CGM実施(FGM含む) 6件
- コンサルテーション 10件
- 入院CSII導入指導 2件
- 新人看護職臨床研修 看護基礎技術研修 講師
- 糖尿病合同カンファレンス 症例検討パネリスト
(2)院外活動
- 日本メドトロニック株式会社 ケアリンクレポート読み合わせ 講師
- 日本メドトロニック株式会社 ケアリンクセミナー 講師
- 栄養管理研修会 講師
- 栃木県立衛生福祉大学校 非常勤講師
- 栃木県看護実践力開発セミナー 講師
- 第一三共株式会社 生活習慣病の長期予後を考える 講師
- 興和株式会社 KOWA Webカンファレンス 座長
(3)実習受け入れ
なし
(4)学会参加
- 第66回日本糖尿病学会
(5)研究活動
なし
(6)執筆
なし
7)透析看護
(1)院内活動
- 腎臓病教室・とちまめ会運営 保存期19名/年
- 医師の依頼を受けた療法選択支援 1件
- 他科入院腹膜透析患者支援 2件
- 入院患者を対象とした保存期集団指導 22名/年
- 2E病棟対象勉強会開催 1回
(2)院外活動
- 茨城県結城看護専門学校 「成人看護学援助論Ⅳ(体液調整)」講師
- 自治医科大学附属病院看護学部 「チーム医療の実際」講師
(3)実習受け入れ
- 自治医科大学看護学部 対象の理解実習
(4)学会参加
- 第68回日本透析医学会学術集会
(5)研究
なし
(6)執筆
なし
8)摂食・嚥下障害看護
(1)院内活動
- 嚥下スクリーニング 5件
- 口腔ケア関連 2件
- 嚥下リハビリ支援 10件
- ポジショニング 1件
- 意思決定支援 11件
- 勉強会開催 2件
- がん患者指導管理料(イ) 11件取得
(2)院外活動
- 社会福祉法人熊晴会嚥下研修会講師
(3)実習受け入れ
- 群馬パース大学認定看護教育課程臨地実習
(4)学会参加
- 第29回日本摂食嚥下リハビリテーション学会学術大会
(5)研究活動
なし
(6)執筆
なし
9)集中ケア認定看護師・クリティカルケア認定看護
(1)院内活動
- 2E看護師対象、NPPVの看護の勉強会 1件
- ICU・CCU看護師対象、人工呼吸器管理と看護の勉強会 2件
- CCU看護師対象、胸部X線での気管チューブ位置確認に関する勉強会 1件
- ICU看護師対象、人工呼吸管理と看護の勉強会1件
- 新人看護職員研修「フィジカルアセスメント 呼吸・循環」企画運営
- 看護職クリニカルラダー研修 看護展開研修【1】「フィジカルアセスメント」講師
- SAT・SBT加算取得に対する準備
- 早期経腸栄養管理加算取得に対する準備
(2)院外活動
- 社団法人 集中ケア認定看護師会 監事
- 公益財団法人 地域社会振興財団 第1回チーム医療充実を目指したメディカルプロフェッショナル研修会「重症心不全患者の看護」講師
(3)実習受け入れ
なし
(4)学会参加
- 第45回 日本呼吸療法医学会学術集会
(5)研究活動
なし
(6)執筆
なし
10)救急看護
(1)院内活動
- 看護基礎技術研修:「救命救急」の企画運営
- 新人医師に対するBLSプロバイダーコース開催 6回
- 急変時の対応に関する勉強会の実施(3件)
- 院内内急変時ワーキンググループメンバー 院内急変事例の検証(146件)
(2)院外活動
- AHA BLS ファカルティ、JPTEC 地域世話人
- メディカル情報サービス主催 看護師教育セミナー「院内急変時の初期対応」講師
- 自治医科大学看護学部 「災害学」講師
- 自治医科大学大学院看護学研究科 「フィジカルアセスメント特論」講師
- 日本救急看護学会倫理委員会 委員
- 日本救急看護学会 評議員
- 日本臨床救急医学会 評議員
- 日本救急医学会関東地方会 評議員
- 北関東救急看護研究会 副会長
- 第26回日本臨床救急医学会総会・学術集会 一般口演 座長
- 第10回日本CNS看護学会 ポスター発表
- 栃木県看護協会 訪問看護師養成研修 フィジカルアセスメント 講師
(3)実習受け入れ
なし
(4)学会参加
- 第25回日本救急看護学会学術集会
- 第19回日本クリティカルケア看護学会学術集会
- 第74回日本救急医学会関東地方会学術集会
(5)研究発表
- 谷島雅子:Practice of Nurse Education in TraumaSurgery Simulation, The 6th World Trauma Congress(第6回世界外傷学会 口演発表)
(6)執筆
なし
11)手術看護
(1)院内活動
- 一般病棟看護師対象勉強会 4件(松沼2件、荒川2件)
- 急性疼痛管理チームメンバー術後疼痛管理チーム加算取得 5,396件、5,396,000円(2023年1月~12月)
- 専門・認定看護師活動検討会リーダー
- ラダーⅣトライ研修 看護展開研修【4】アドバイザー
- チーム医療充実を目指したメディカルプロフェッショナル研修 講師
(2)院外活動
- 日本手術医学会 教育委員
- 日本手術医学会 評議員
- 日本小児麻酔学会 評議員
- 日本手術看護学会 査読員
- 日本術後痛学会 評議員
- 日本看護学会学術集会 抄録選考委員
- 自治医科大学看護学部 「多職種連携論」 講師
- 第54回日本看護学会学術集会 座長(一般演題)
- 自治医科大学看護学部 「成人実践看護学Ⅱ」 講師
- 日本手術看護学会関東甲信越地区 役員
- 第34回日本手術看護学会関東甲信越地区 司会(認定看護師のワンポイントレクチャー)
- とちぎ手術看護情報交換会 役員
(3)実習受け入れ
なし
(4)学会参加
- 第37回 日本手術看護学会年次大会
- 第43回 日本看護科学学会学術集会
- 第45回 日本手術医学会総会
- 第23回 栃木看護学会学術集会
- 第54回 日本看護学会学術集会
- 第34回 日本手術看護学会関東甲信越地区
- 第70回 日本麻酔科学会学術集会
- 第51回 日本集中治療学会学術集会(3月14、15日参加予定)
(5)研究発表
なし
(6)執筆
- 日本手術医学会誌 第44巻3号 令和5年10月31日発行 特集企画「質向上と効率化を目指した術前外来up-to-date」 P27-31
12)新生児集中ケア
(1)院内活動
- 院内の看護師と小児に携わる専門職を対象とした勉強会企画・運営 1件
- 勉強会開催 9件
「NICUの看護」
「新生児の気管挿管介助の流れ 看護のポイント」
「赤ちゃんのおくるみとフレディフロッグの使い方」
「赤ちゃんの抱っこ」
「発達支援アセスメント」
「新生児の適応生理」
「ディベロップメンタルケア」
「ファミリーセンタードケア」
「超低出生体重児の急性期のケア ‐ ディベロップメンタルケアを中心に ‐ 」 - すくすくクラブ講師 2件
「タッチケア」
「赤ちゃんのスキンケア」 - 新生児集中ケア認定看護師活動報告
「新生児看護を楽しむ」 - 新生児蘇生法(NCPR)Aコースインストラクター 4件
新生児蘇生法(NCPR)Sコースインストラクター 4件 - 相談 37件
- 指導 48件
(2)院外活動
- 新生児蘇生法(NCPR)Sコースインストラクター 2件
- マロニエ医療福祉専門学校 新生児蘇生法(NCPR)Bコースインストラクター
- 第32回日本新生児看護学会学術集会実行委員
- 第7回小児在宅医療実技講習会 講師
- マロニエ医療福祉専門学校 小児看護講師
(3)実習受け入れ
なし
(4)学会参加
- 第32回 日本新生児看護学会学術集会
(5)研究
- 佐藤ひさ代,金田陽子,川中子知里他:小児・母性の連携による家族看護-小児・母性領域CN・CNSの協働企画の勉強会-,第10回日本CNS看護学会学術集会示説発表(共同演者須藤美咲)
(6)執筆
なし
13)小児救急看護
(1)院内活動
- 小児一次救命処置勉強会実施 5件
- 家族支援勉強会開催1件(母性・小児領域専門・認定看護師と共同開催)
- 小児呼吸ケアチーム活動
- 新人看護職員技術研修「フィジカルアセスメント:呼吸・循環」企画運営
- 所属部署における小児救急看護支援:急性期ケア 2件
成長発達支援2件
家族ケア 2件
事故予防支援:1件
(2)院外活動
- 二葉幼児園 小児救急蘇生法研修 講師
- マロニエ医療福祉専門学校看護学科 小児看護方法論講師
(3)実習受け入れ
なし
(4)学会参加
なし
(5)研究活動
なし
(6)執筆
なし
14)感染管理
(1)院内活動
- 感染リンクスタッフ勉強会企画運営 4回
- 新人看護職員技術研修「感染防止L-1、L-2」企画運営
- おおるり分教室勉強会企画運営 「感染対策の基礎知識」
- 看護補助員研修 14回
- ICUサーベイランス対象者 777件
- SSIサーベイランス対象者(下部消化管496件、整形外科377件、心臓血管外科132件)
- 加算ラウンド 毎週(本館/新館・子ども)
- ICTラウンド 8回
- AST活動 (会議:毎月、ラウンド:毎週)
- N95呼吸器防護具定量フィットテスト 107件
- 感染防止、隔離予防策、教育指導関係 193件
- 委託業者カンファレンス(清掃業者、中央材料室) 18回
- 清掃業者院内ラウンド
- 清掃業者研修 3回
(2)院外活動
- 私大協相互ラウンド(獨協医科大学病院)
- 相互ラウンド(獨協大学病院、茨城県西部メディカルセンター、新小山市民病院)
- 感染対策向上加算に関わる合同カンファレンス(第1~4回)
- TRICK合同カンファレンス(第1~6回)
- 獨協医科大学 感染管理認定看護師教育課程 講師
(3)実習受け入れ
なし
(4)学会参加
- 第37回 日本環境感染学会総会・学術集会
- 第11回 日本感染管理ネットワーク学会学術集会
- 第98回 日本医療機器学会
(5)研究発表
なし