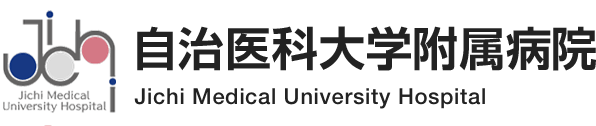糖尿病センター【アニュアルレポート】
1.スタッフ(2024年4月1日現在)
| センター長(兼) | (内分泌代謝科教授) | 矢作 直也 |
|---|
医員
内分泌代謝科
| 教授(兼) | 倉科 智行 |
|---|---|
| 准教授(兼) | 海老原 健 |
| 学内准教授(兼) | 岡崎 啓明 |
| 講師(兼) | 武井 暁一 |
| 学内講師(兼) | 武内 謙憲 |
| 助教(兼) | 武井 祥子 ※時短 |
| 病院助教(兼) | 犀川 理加 |
| 近藤 泰之 | |
| 櫻井 百恵 ※時短 | |
| シニアレジデント | 4名 |
| 派遣 | 2名 |
腎臓内科
| 教授(兼) | 長田 太助 |
|---|---|
| 秋元 哲 | |
| 特命教授(兼) | 里中 弘志 |
| 准教授(兼) | 岩津 好隆 |
| 増田 貴博 | |
| 講師(兼) | 吉澤 寛道 |
| 菱田 英里華 | |
| 助教(兼) | 岡 健太郎 |
| 病院助教(兼) | 若林 奈津子 |
| 神永 洋彰 | |
| 大野 和寿 | |
| シニアレジデント | 6名 |
眼科
| 教授(兼) | 蕪城 俊克 |
|---|---|
| 准教授(兼) | 高橋 秀徳 |
| 講師(兼) | 渡辺 芽里 |
| 伊野田 悟 | |
| 助教(兼) | 佐藤 彩 |
| 坂本 晋一 | |
| 恩田 昌紀 | |
| 粕谷 友香 | |
| 長岡 広祐 | |
| 病院助教(兼) | 案浦加奈子 |
| 守屋 穣 | |
| 野口久美子 | |
| 橋本 悠人 | |
| 吉田 花 | |
| シニアレジデント(兼) | 9名 |
リハビリテーションセンター
| リハビリテーションセンター長 教授(兼) | 森田 光哉 |
|---|---|
| リハビリテーション室長 | 南雲 光則 |
臨床栄養部
| 栄養管理室長(兼) | 堀内由布子 |
|---|---|
| 栄養管理室長補佐(兼) | 荒川由紀子 |
看護部
| 看護師長(兼) | 荒井 則子 |
|---|
2.糖尿病センター特徴
糖尿病センターは内分泌代謝科、腎臓内科、眼科、臨床栄養部、看護部の協力体制の下、2009年4月に発足した。同年4月、糖尿病療養指導の専門外来が開設された。
内分泌代謝科、腎臓内科、眼科、臨床栄養部、看護部、リハビリテーション科のスタッフで運営委員会を組織し、糖尿病合同カンファランスを開講している。2023年は2回実施した。
3.実績・クリニカルインディケーター
2023年(1月~12月)の実績は下記の通りである。
内分泌代謝科に入院した糖尿病患者は入院479名中204名だった。1型糖尿病25例、2型糖尿病148例、その他22例、妊娠糖尿病9例だった。
連続血糖モニターを活用した血糖コントロール評価を実施し(isCGM:外来142名)、インスリンポンプ療法を計64名に実施し、内21名はCGMとポンプ療法の合体したSensor augmented pump(SAP)を使用している。
腎臓内科に入院した553名のうち、糖尿病性腎症あるいは糖尿病を併存に持つ入院症例は142名であった。入院理由は透析導入、バスキュラーアクセス作成・修復、ネフローゼ加療、電解質異常や感染症の治療など多岐に渡った。バスキュラーアクセス作成を目的とした入院は14名であり、腹膜透析を含め新規透析導入を目的とした入院は24名であった。また、糖尿病性腎症と他の腎障害の鑑別が必要な例に対しては腎生検を施行している。本年は腎生検施行例79名中3名が生検により糖尿病性腎症と確定診断された(統計は、2023年1月1日より12月31日)。
眼科で実施された糖尿病網膜症に対する硝子体手術は約137件であった。他の施設に比較して若年の重症例が多く、患者教育を含めたケアが必要と思われる。
糖尿病センター合同カンファランス
2023年3月15日 糖尿病患者会
2023年10月25日 糖尿病合併症:眼疾患都AIの関わり
合同カンファランスでは毎回アンケートを実施し、テーマを選定している。可能な限り症例中心とし、多部門からの提言促進するパネルディスカッションや、院外からの招待講演を設け、院内外でのネットワークと診療コンセンサスの形成を目指している。
4.2024年の目標・事業計画等
センター全体としては、引き続き定期的に合同カンファランスを実施し、診療の連携を密にし、コンセンサスが不十分な診療領域にはマニュアルを作成して対応する。地域に潜在的に存在する患者数を考慮すると、地域との連携も不可欠であり、自治体や医師会と協力して、医療体制構築を行う。
網膜症を適切に管理できるシステムの確立には、定期的な眼底検査が必須であるが、眼科外来の混雑が大きな障害になっている。眼科外来を受診しなくても評価が可能な、無散瞳眼底カメラによる眼底検査システムが2011年6月から稼動しはじめた。患者が臨床検査部で無散瞳眼底カメラによる眼底写真撮影を受け、眼科医がJUMP上で判定しコメントを入力するシステムである。2023年12月までに約9,672名が撮影を受けており、内分泌代謝科に通院中の全糖尿病患者、腎臓内科の透析患者における眼底所見の把握を目指している。