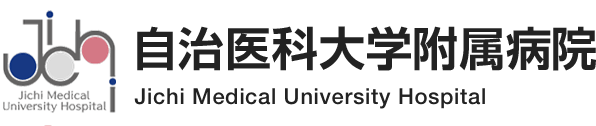小児泌尿器科【アニュアルレポート】
1.スタッフ(2024年4月1日現在)
| 科長 | (教授) | 守屋 仁彦 |
|---|---|---|
| 医員 | (講師) | 日向 泰樹 |
2.診療科の特徴
1)小児泌尿器科の特徴
当科スタッフは、成人を含む泌尿器科学の全般を修めた医師(泌尿器科専門医かつ指導医)により構成されており、腎泌尿生殖器の発生・機能・解剖への習熟が強みである。そのため、泌尿器科専門医として小児泌尿器科領域はもちろんのこと成人も含めた泌尿器科の領域である排尿・生殖・尿路管理に精通している。小児泌尿器科疾患に対する治療手段として内科的・外科的な両側面に対応可能であるとともに思春期以降の対応についても柔軟に行える体制にある。小児泌尿器科として専従スタッフを有する大学は我が国では数少ないが、最近は小児泌尿器疾患に対応できるスタッフを有する大学は増加傾向にある。しかしながら年齢・性別を問わずあらゆる疾患に対応できる施設は限られている。
当科では子ども医療センター医師としてあらゆる小児泌尿器科疾患に対応している。そのうえで、成長発達過程への理解や子どもを思う両親への配慮などの十分な訓練を積んでいるとともに、成人期医療への理解をもとにした成人期を見据えた診療を行うことが可能である。近年の小児医療全般の問題として、transition(慢性疾患の成人期移行医療)が取り上げられることが多いが、大学病院との相互乗り入れが可能な当科は、その領域においても先駆的な医療を提供する立場にある。さらに小児泌尿器科領域で行われる尿路再建術は成人期にみられる尿道狭窄や尿管狭窄などの尿路疾患に対しても応用可能な技術であり、成人に対する尿路再建術も成人泌尿器科・腎臓外科と協力しながら積極的に対応している。大学所属の小児泌尿器科という貴重な立場にあって、その責務を果たすべく、手術手技や診療指針に関する情報発信については、これを積極的、継続的に行っている。
2)整備状況
当科の外来診療の特徴として、①手術治療以外に内科的治療方法で診療が完遂される疾患が少なくない(尿路感染、排尿障害など)。②成長発達に応じた経過観察や生活指導など、中期長期にわたる継続的診療が少なくない、③泌尿生殖器という臓器診療はナイーブな一面があるのでこれに配慮する、などが挙げられる。長期的な問題点としては神経因性膀胱に対する排尿管理や尿道形成術後の排尿の問題、停留精巣における思春期以降の精巣機能、女児の外陰膣形成術後の長期フォローなどが課題となる。このような諸問題に対しては当科とともに成人泌尿器科、婦人科との協議を行い、transitionの実務を発展的に行っている。小児泌尿器科疾患の全般をカバーするためには、外来診療は単に入院手術診療を補足するものではなく、相互に補完しあう必要がある。手術を中心とした外科的診療は入院診療が主体となるが、排泄ケアなどが必要な疾患では外来での継続的な対処が主たる診療であり、その不足部分を入院診療で補うことで診療が継続される。良好な外来診療を継続させるためには、排泄ケアに習熟した外来スタッフの育成が必要であり、そのためには保険診療や看護ケアのコストパフォーマンスを高める政策的働きかけを学術団体などを通じて行う必要がある。その一方で、より高度な診療を提供するためには外来看護師教育を今後も行っていく必要がある。
入院診療においては、週1.75枠(隔週で、週1.5と2.0枠)で手術を行っている。COVID-19のパンデミックの影響による入院診療の停滞から徐々に回復してきている。当科では適応となる多くの手術を低侵襲で創の小さい腹腔鏡で施行している。これからも鏡視下手術やロボット手術といった技術革新を、より広範囲に安全かつ確実な形で取り入れることが求められる。今後の発展のためにも、成人泌尿器科や腎臓外科との連携による専門医養成トレーニングがますます重要となる。現在、日向医師が腎臓外科の手術に入り腹腔鏡手術の習得を目指している。今後は成人泌尿器科・腎臓外科との実務連携をさらに強化することで、各医師の教育機会を増加するとともに、臨床面では成人尿路再建術の協力や小児腎移植の施行など、さらなる発展を目指している。
2007年の開設以来、小児泌尿器科として当科の専門独立性が担保されてきたため、国内外で有数と言われるレベルの小児泌尿器専門施設として発展できたと自負している。また泌尿器科専門医教育の面においては、上に述べたような関連診療科との緊密な連携が不可欠であり、その体制が整備されているのが当科の特長である。自治医大でこそ可能な理想の診療、教育、研究体制と考えられ、今後も継続的に発展させたい。
3)当科対象疾患のあらまし
対象疾患の柱は、①腎尿路の先天異常、②小児性腺生殖器疾患、③小児の尿失禁を含む排泄障害、④成人を含む尿路再建術で、先天性疾患が多いものの尿路・性路再建術全般にわたる。成人に手術が必要な場合は、子ども医療センター外来を受診し、大学病院病棟に入院、子ども医療センターにて手術を行う。
全身性多発奇形症候群の一部分症としての腎尿路生殖器の先天異常も多く認め、関連各科とのチーム診療が不可欠である。また、専門施設が追うべき任務として、他院での治療困難例、中断例に追加して治療を完了させることもしばしばある。
・専門医
| 日本泌尿器科学会認定専門医・指導医 | 守屋 仁彦 |
|---|---|
| 日向 泰樹 | |
| 日本小児泌尿器科学会認定医 | 守屋 仁彦 |
| 日向 泰樹 | |
| 泌尿器腹腔鏡技術認定医 | 守屋 仁彦 |
| Da Vinci Console Surgeon Certificate | 守屋 仁彦 |
| 日本がん治療認定医機構認定医・指導医 | 日向 泰樹 |
3.診療実績・クリニカルインディケーター
1)新来患者数・再来患者数・紹介割合
| 新来患者数 | 265人 |
|---|---|
| 再来患者数 | 4,059人 |
| 紹介割合 | 82.0% |
2)入院患者数
142人
3)全手術件数
172件
3-1)手術症例病名別件数
| 先天性水腎症 | 4 |
|---|---|
| 膀胱尿管逆流症 | 4 |
| 停留精巣 | 35 |
| 尿道下裂 | 20 |
| 陰嚢水腫 | 8 |
| 合 計 | 67 |
3-2)手術式別件数
| 腎盂形成 | 4 |
|---|---|
| 腎摘出術(腹膜鏡下) | 0 |
| 膀胱尿管新吻合術 | 4 |
| 内視鏡的逆流防止術 | 0 |
| 停留精巣固定術 | 35 |
| 腹腔内以外 | 30 |
| 腹腔鏡下 | 5 |
| 尿道下裂形成術 | 20 |
| 女児外陰形成術 | 1 |
4)主な処置・検査
排尿時膀胱尿道造影、尿流動態検査(ウロダイナミクス)、膀胱尿道内視鏡検査、核医学検査、超音波検査
5)カンファレンス症例
- 外来患者・手術患者カンファレンス(火曜)
- 小児画像カンファランス(火曜)
- 二分脊椎カンファレンス(月1回月曜)
- 栃木小児泌尿器科症例カンファレンス(TPUCC)(不定期)
6)キャンサーボード
小児血液腫瘍グループ、小児外科、小児診断部などと合同で、年2~3回開催。
4.2024年の目標・事業計画等
- より低侵襲で確実な小児泌尿器科診療の実践
- 腎泌尿器外科講座内での若手中堅人材の横断的活用
- 円滑なトランジションのための成人泌尿器科や成人婦人科との診療連携
- 国際的な発信力の強化
- 競争的資金の獲得