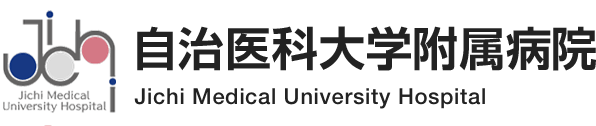血管内治療センター【アニュアルレポート】
1.スタッフ(2024年4月1日現在)
| 血管内治療センター長 | (教授) | 難波 克成(血管内治療センター、脳血管内治療部) |
|---|---|---|
| 脳血管内治療部 | 部長(教授) | 難波 克成 |
| 医員(病院助教) | 檜垣 鮎帆(脳血管内治療部) | |
| 大動脈治療部 | 部長(准教授) | 荒川 衛 |
| 医員(教 授) | 川人 宏次(心臓血管外科) |
2.血管内治療センターの特徴
血管内治療部は2005年4月に新設され、脳神経分野、全身分野の2分野が稼働を開始した。2006年3月に本館東の旧血管内治療部に移転した。
2010年11月に心臓血管分野が新設され、3分野による診療を開始した。
2012年11月に組織変更が行われ、血管内治療部が血管内治療センターに改編され、新たに「脳血管内治療部」、「放射線IVR部」、「大動脈治療部」の3つが創設された。
2015年に「心疾患治療部」が血管内治療センターに編入され、これまでの部門と併せて4部門で活動を開始した。
2018年9月に附属病院新館南棟において新たな血管内治療センターの稼働が始まり、院内に点在していた各部門がセンター内に集約された。放射線撮影装置を用いた治療部門が1ヶ所に集中することで部門横断的治療やスタッフの効率的配置が可能となった。
脳血管内治療部は、2006年3月に頭部専用血管撮影装置(Philips社製Allura)を導入し、診療にあたってきた。2012年5月には血管撮影装置のフラットパネルディテクタと画像処理ソフトを一新し、臨床性能と画像鮮明度を大幅に向上させた。
2018年の血管内治療センター移転に伴い、頭部専用血管撮影装置が一新され、最新鋭のPhilips社製Azurionが導入された。導入後の画質調整で世界最高レベルの高精細な画像が得られる状態となった。
スタッフは、2020年4月より大坂美鈴が脳神経血管内治療専修医として、トレーニングを開始し、1名増員となった。また、2020年10月に難波克成が学内教授から教授に昇進した。
診療内容は脳、脊髄、頭頚部の血管病変全般を対象とし、脳動脈瘤、脳動静脈奇形、脳動脈閉塞性病変、脊髄血管奇形、頭頚部腫瘍、頭頚部血管奇形などの診断および治療を行っている。観血的手術を行うことなく、非侵襲的に治療を行う画期的な先端医療を担っている。
2011年12月には、難波克成教授が日本脳神経血管内治療学会の指導医に認定された。2012年4月1日より自治医科大学附属病院が日本脳神経血管内治療学会認定研修施設に認定され、2023年度も認定が更新された。引き続き、栃木県におけるこの分野の発展に貢献する。
認定施設
- 日本脳神経血管内治療学会 認定研修施設
- 日本IVR学会 専門医修練機関
- 関連11学会構成ステントグラフト実施規準管理委会
- 認定ステントグラフト実施施設(胸部)
- 関連10学会構成ステントグラフト実施規準管理委会
- 認定腹部ステントグラフト実施施設
- 下肢静脈瘤に対する血管内レーザー治療実施施設
- 日本脈管学会認定研修指定施設
専門医・指導医
| 日本脳神経外科学会専門医 | 難波 克成 |
|---|---|
| 檜垣 鮎帆 | |
| 日本脳神経血管内治療学会専門医、指導医 | 難波 克成 |
| 日本脳神経血管内治療学会専門医 | 檜垣 鮎帆 |
| 心臓血管外科専門医、修練指導者 | 荒川 衛 |
| 日本血管外科学会認定血管内治療医 | 荒川 衛 |
| 胸部ステントグラフト実施医・指導医(Valiant, Gore TAG, Valiant Captiva, Relay Plus, TX-alpha) | 荒川 衛 |
| 腹部ステントグラフト実施医・指導医(Zenith, Gore Excluder, AFX Stentgraft System, Endurant, AORFIX, TERO) | 荒川 衛 |
| 腹部ステントグラフト実施医(Alto) | 荒川 衛 |
| 下肢静脈瘤に対する血管内レーザー焼灼術実施医、指導医 | 荒川 衛 |
3.診療業績・クリニカルインディケーター
脳血管内治療部
| 脳血管撮影件数 | 303件 |
|---|
手術症例病名別件数
| 脳動脈瘤 | 47例 |
|---|---|
| 動静脈瘻・脳動静脈奇形 | 13例 |
| 急性期脳血栓回収療法 | 10例 |
| 血管形成術 | 11例 |
| 脳腫瘍塞栓術 | 6例 |
| 脊髄血管奇形塞栓 | 1例 |
| 頭頚部顔面血管塞栓 | 6例 |
| その他 | 1例 |
| 総数 | 95例 |
大動脈治療部
| EVAR(追加EVAR含む) | 65例 |
|---|---|
| TEVAR(追加TEVAR含む) | 23例 |
| その他 | 4例 |
| 総数 | 92例 |
4.2024年の目標・事業計画等
研究活動
3Dプリンターで正確に再現した脳動脈瘤を脳血管内治療に応用する研究を開始した。脳血管内手術前に実際の治療を行うのと同じ構造を持つモデルでシミュレーションを行う方法を開発した。2016年にこの成果に基づき、脳血管内手術初心者を対象とした脳血管内手術の教育プログラムを実施し、好評を博した。これらの経験をもとに脳血管内治療教育コースを開催し、安全な治療の普及に努めたい。
2018年は新たな取り組みとして、人工知能を応用し脳MRA画像の高解像化を図る試みを始めた。現在、脳血管画像と脳MRA画像の画像対を用いて教師データを作成中である。パターンマッチングの手法で大量の画像対を処理できるように試みたが、画像対間で十分な対応関係の構築が困難であった。このため、手動で画像対の対応関係を構築する必要があり、時間を要している。この研究を進め、脳MRA高解像化により、脳神経血管疾患の診断率向上、低侵襲化を図りたい。
臨床活動
脳血管内治療部は開設以来、治療数が年々増加してきたが、2016年度ピークとして微減し、2017年度から2019年の症例数はおおむね140件程度で経過していた。2020年度からは100件前後に減少して経過し、2022年度の治療件数は95件であった。治療数減少の原因は、治療デバイスの進歩で以前なら複数回治療が必要であった症例が1回の治療で完結するようになったこと、治療薬の進歩でくも膜下出血後の脳血管攣縮が激減したこと、コロナウイルス感染症流行による心血管イベントの減少などが考えられる。
検査数に関しては脳MRAや脳血管3DCTAなどの非侵襲的検査法の発達に伴い、侵襲的検査である血管撮影は減少傾向にある。MRA、3DCTAには非侵襲性のメリットがあるものの時間的、空間的解像度は血管撮影に及ばず、真に血管精査が必要な症例には積極的に行い、正確な診断を下すことが患者利益につながる。非侵襲的血管検査の普及で、脳血管撮影は逆に専門性が高くなり、当施設のような脳血管内治療専門施設の重要性が増している。われわれは専門的見地より脳血管撮影を積極的に行う方針で、一時期220件であった検査数は300件を超えるようになった。
脳血管内治療部は、10年前より他医家紹介や患者さんの希望による受診が増加し、脳血管内治療が広く一般医家、市民に浸透してきた印象を受ける。今後の10年で低侵襲手術を期待する社会的要請から、症例数は増加すると見込まれる。専属スタッフ2名、専修医1名という制約の中で多くの治療、検査を行っている。
2023年も引き続き、治療、検査数の増加はもとより、検査、治療の質の向上を目標とする。
個々の症例の目標としては、急性期脳梗塞に対する脳血栓回収療法の普及を図りたい。栃木県は、脳血栓回収療法の普及率が全国平均と比較して、著しく低い。これは、この治療が一般医家、住人に十分認知されていないことが原因と考えられる。啓蒙活動を通じ、救える命、脳機能がある、ということを伝えたい。このためには行政の関与が必須であり、その方面への働きかけを行う予定である。また、頭頚部領域血管病変は各科が協力しての多面的治療が必要であり、積極的な連携を図りたい。
新館南棟に血管内治療センターに全部門が集約されたことによる効果を発揮できるように、各部門の横断的学習や協力体制の構築に努めたい。