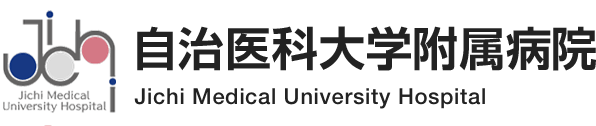てんかんセンター【アニュアルレポート】
1.スタッフ(2024年4月1日現在)
| センター長 | (教授) | 川合 謙介 |
|---|---|---|
| 副センター長 | (教授) | 小坂 仁 |
| 医員 | (教授) | 藤本 茂 |
| 森 墾 | ||
| 須田 史朗 | ||
| 竹下 克志 | ||
| 山田 俊幸 | ||
| (学内教授) | 五味 玲 | |
| (准教授) | 國井 尚人 | |
| (学内准教授) | 森田 光哉 | |
| 薬剤部長 | 今井 靖 | |
| 看護部長 | 福田 順子 | |
| 地域医療連携・患者支援部 | 西野 宏 | |
| 医員 | 中嶋 剛 | |
| 大谷 啓介 | ||
| 井林 賢志 | ||
| 佐藤 信 | ||
| 小島 華林 |
2.てんかんセンターの特徴
栃木県は全県で200万人の人口を擁しているが、てんかん専門医は14名しかおらず、てんかん専門医が限られ、診療科も小児科および脳神経外科に集中している(小児科および脳神経外科が多い)。2015年にてんかん地域診療連携推進事業の8拠点に採択され、2016年に自治医科大学てんかんセンターが設立されたことにより、多診療科・多職種の連携体制が始まり、地域連携が始まった。
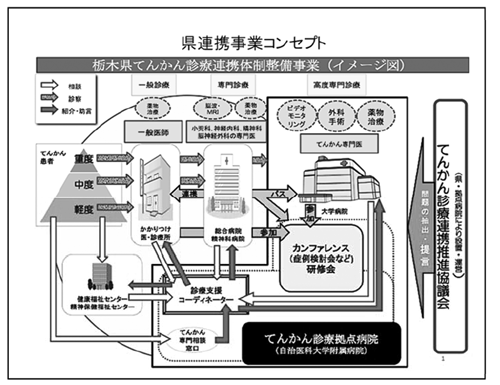
当施設では、連携事業の拠点医療機関として、てんかんに対する最先端の内科的治療やケトン食などの特殊治療、外科的治療を成人および小児症例を対象に行っている。また栃木県内のみならず北関東エリアを包括し域てんかん診療拠点として機能している。
自治医大てんかんセンターは多数の部門が参加し、包括的なてんかんセンターを目指しているが、連絡窓口を脳神経外科内に設置し、月1回、多科、多職種参加の症例検討会を行っている。県内のてんかん研修のため、他施設にも開かれ、過去50回で院内から延べ930名、院外から延べ70名参加した。昨年一昨年はコロナ禍により活動が制限されたが、それまでは院外からの参加者は周知に伴い、増加傾向であった。
病院外での活動として、栃木県庁やてんかん協会栃木支部との協力のもと、県内でのてんかん普及・啓発を目指した活動を行っている。市民講座は講演だけでなく、その時には個別相談も行っている。2019年度から教員対象のてんかん研修会を実施し、2020年2021年はWeb併催という形で行った。また、2020年度からは、特定看護師研修の一環として精神・神経症状に係る薬剤投与関連の実習生受け入れを開始した。
今年度は新型コロナウイルス拡大の影響は昨年と比較して少なかった。診療についても外来入院など一般診療は制限なく、患者数など診療指標もコロナ前の水準を超えている。昨年に引き続き感染予防や患者の不安を鑑み、電話再診を積極活用するなどの対応を行った。ビデオ脳波モニタリングを含むてんかん検査目的入院については明らかに増加した。
認定施設
- 学会認定包括的てんかん専門医療施設
- 日本てんかん学会専門医認定訓練施設
専門医
| 日本てんかん学会指導医 | 川合 謙介 |
|---|---|
| 山形 崇倫 | |
| 小坂 仁 | |
| 國井 尚人 | |
| 小島 華林 | |
| 井林 賢志 | |
| 石下 洋平 | |
| 日本てんかん学会専門医 | 川合 謙介 |
| 山形 崇倫 | |
| 小坂 仁 | |
| 國井 尚人 | |
| 小島 華林 | |
| 中嶋 剛 | |
| 石下 洋平 | |
| 大谷 啓介 | |
| 井林 賢志 | |
| 佐藤 信 | |
| 堀口明由美 | |
| 日本リハビリテーション医学会専門医 | 中嶋 剛 |
| 日本臨床神経生理学会専門医(脳波分野) | 川合 謙介 |
| 國井 尚人 | |
| 大谷 啓介 | |
| 石下 洋平 | |
| 井林 賢志 |
3.診療実績・クリニカルインディケーター
(前年4月1日~3月31日)
1 患者数、脳波記録数
| 小児科 | 成人科 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| てんかん外来新患数(年総数) | 60 | 123 | 183 |
| てんかん再来患者数(1日あたり平均) | 33.8 | 33.8 | 96.8 |
| てんかん入院患者数(年総数) | 262 | 262 | 653 |
| てんかん在院患者数(1日あたり平均) | 10.7 | 10.7 | 27.8 |
| ビデオ脳波モニタリング施行患者数(年総数) | 6 | 6 | 106 |
| ビデオ脳波モニタリング施行のべ日数 | 12 | 12 | 413 |
| 頭蓋内脳波記録施行患者数(年総数) | 0 | 4 | 4 |
| 頭蓋内脳波記録施行のべ日数 | 0 | 50 | 50 |
2 てんかん外科手術年間総症例数
| 件数 | |
|---|---|
| 1.側頭葉切除術 | |
| a.選択的海馬扁桃核切除術 | 0 |
| b.スペンサー法 | 0 |
| c.前側頭葉切除術 | 3 |
| d.病巣切除 | 2 |
| e.海馬MST(単独) | |
| f.その他(具体的に) | |
| 合計 | 5 |
| 2.側頭葉外皮質切除術(病巣切除を含む) | 3 |
| 3.多葉離断・切除術 | |
| 4.半球離断・切除術 | 0 |
| 5.脳梁離断術 | 2 |
| 6.定位的凝固術 | |
| 7.MST(単独) | |
| 8.慢性頭蓋内電極留置術 | 3 |
| 9.迷走神経刺激電極埋め込み術 | 2 |
| 10.ガンマナイフ | 0 |
| 11.その他(具体的に) :SEEG(ROSA使用) |
0 |
| :SEEG(au toguide使用) | 1 |
| てんかん外科手術年間総症例数 | 16 |
3 ケトン食治療
3人
4 治験 プロトコール
3件
参加人数 3 人
1)てんかん診療指標
①てんかん患者数の推移
この事業が始まった2015年から2022年まで7年間で、てんかんの初診患者数は213人から229人に、入院は573人から703人に増加した。2023年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響は限定的で、初診患者、入院患者ともに前年比で大幅な増加した。
②長時間ビデオ脳波検査
事業開始から年々増加し、2022年度は113件であった。今年度は、昨年時点でコロナ収束後の入院を希望された例もあり、2024年は137件と大幅に増加した。
③てんかん手術
2023年は24件を施行した。術式としては焦点切除術、頭蓋内電極留置、全脳梁離断術、迷走神経刺激装置植込術に加え、ロボットを使った精密な頭蓋内電極留置術が2例行われ昨年と合わせて7例実施している。特に小児科との連携が奏功し小児てんかん外科症例が増加している。
2)主な処置・検査
長時間ビデオ脳波モニタリング、神経心理検査、頭部MRI(機能MRI)、頭部CT、頭部3DCT、SPECT、PET、光トポグラフィー、脳血管造影検査
3)カンファレンス
a)脳神経外科内
月曜・水曜・金曜日 7時45分-9時 入院症例検討カンファレンス
火曜 14時-17時 教授回診、術前術後症例検討、研究報告、抄読会
b)他部門との合同カンファレンス
てんかんセンターカンファレンス:毎月1回
c)他施設カンファランス(テレビ会議システムでのオブザーバー参加)
東京大学附属病院てんかんセンターカンファランス:毎月1回
モンゴル日本病院てんかんカンファランス:毎月1回
d)その他
エピネット栃木プラス 2回/年
e)カンファレンス症例数
約50例/年
4.2024年の目標・事業計画等
当センターは2015年に厚生労働省により全国8か所(現在は30か所)の地域連携拠点に指定されている。日本てんかん学会により、より広域かつ高度な施設認定である包括的てんかんセンターとしても認定されている。設立から拠点病院の機能強化(ビデオ脳波モニタリングと手術の増加)、多職種・多科で他の医療機関にも開かれた定例症例検討会による医療連携と診療レベルの向上を行っている。てんかんセンターとして、単科診療のみでは診断と治療が困難な症例に対する学際的な検討を推進することで診療レベルの一層の向上を図っていく。また栃木県内のみならず北関東エリアを包括した広域てんかん診療拠点として、より一層の診療の拡充と質の向上を図るとともに、既設のエピネット栃木などを引き続き最大限活用し圏内医療施設、行政との有機的な連携を強化していく計画である。
最近の新規事業として、特定看護師養成(精神神経薬剤投与)、てんかんコーディネータ育成協力、CREST(戦略的創造研究推進事業)てんかん発作記録レジストリの作成、アジアオセアニアてんかん外科レジストリの国内とりまとめなどを行っている。
また、海外へのてんかん手術普及のために、日本モンゴル病院への手術指導を行っており、モンゴルでのてんかん外科のスタートアップに協力している。
ポストコロナに向けたさらなる診療レベルの拡充を図っている。2025年には日本てんかん学会総会を当施設主幹で開催予定であり、それらを見据えたさらなる地域でのてんかん普及、啓発活動を進めていく。
5.今年度事業達成度
拠点病院の機能強化(ビデオ脳波モニタリングと手術の増加)、多職種・多科で他の医療機関にも開かれた定例症例検討会による医療連携と診療レベルの向上、てんかん連携事業周知目的のパンフレット作成、県警と連携した運転免許の実態調査、県内のてんかん診療の現況把握のための実態調査、全国の地域でのてんかん診療実態調査、教育機関へのてんかん実態アンケート、教員向けてんかん研修会を行った。今年度は新型コロナウイルス感染は収束し、事業や会議などを再開可能であった。また診療についても外来入院など一般診療は制限しなかったため影響はなく、ビデオ脳波モニタリング入院や、手術件数については昨年と比較し増加した。JEPICA(てんかんセンター連絡協議会)総会を2023年2月10〜1日、開催し久しぶりの現地メインでの開催であったこともあり多数のご参加をいただいた。2025年には日本てんかん学会学術総会を当施設主幹で開催予定である。それらを見据えさらなる地域でのてんかん普及、啓発活動を進めていく。